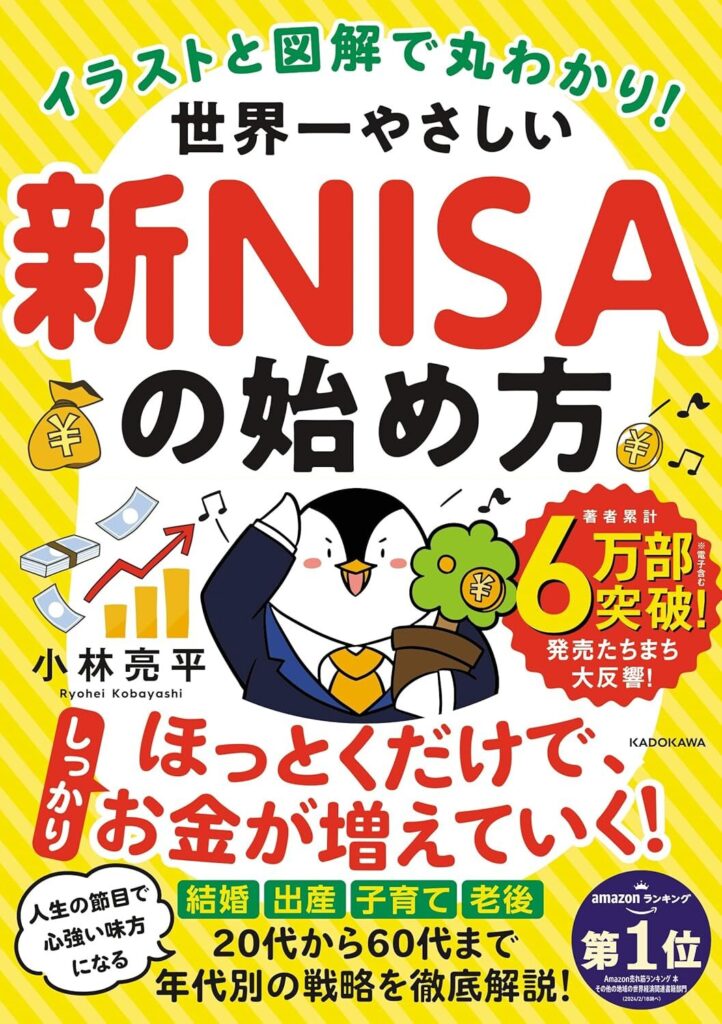
2024年に刷新された「新NISA」制度──その名前は聞いたことがあるけれど、「実際にどう使えばいいの?」「何から始めればいいのかわからない……」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな不安や疑問をやさしく解きほぐし、知識ゼロの初心者でも制度の全体像から活用法、投資の実践ステップまでをスムーズに学べるのが、小林亮平さんによる書籍『イラストと図解で丸わかり! 世界一やさしい新NISAの始め方』です。

著者は、元銀行員であり、金融教育系YouTuberとしても知られる「BANK ACADEMY」の運営者。
難解に思われがちな制度や投資の話を、豊富な図解と親しみやすい言葉でわかりやすく解説しています。
年代別の戦略提案や、実際に寄せられたQ&Aへの丁寧な回答など、単なる制度紹介を超えた実用的な内容が満載。
今すぐ始めたい人も、これから考えたい人も、自分に合った一歩を踏み出すための「やさしい地図」が、この一冊に凝縮されています。

合わせて読みたい記事
-

-
新NISAについて学べるおすすめの本 6選!人気ランキング【2026年】
2024年から新たにスタートした「新NISA制度」。これまでのNISA(少額投資非課税制度)とは異なり、制度が大幅に見直され、投資できる金額の上限や非課税期間、利用できる投資商品などがより柔軟に、そし ...
続きを見る
書籍『イラストと図解で丸わかり! 世界一やさしい新NISAの始め方』の書評

書籍『イラストと図解で丸わかり! 世界一やさしい新NISAの始め方』は、2024年から始まる新NISA制度について、初心者でも理解しやすいように解説した一冊です。
本書の特徴や魅力を、以下のポイントでご紹介します。
- 著者:小林 亮平のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
これらの視点から、本書の魅力を詳しく見ていきましょう。
著者:小林 亮平のプロフィール
小林亮平氏は、元銀行員という経歴を持ち、現在は資産運用に関する情報発信を中心に活動する人気YouTuberです。大学卒業後に三菱UFJ銀行へ入行し、金融の現場で経験を積んだ後、独立して「BANK ACADEMY」というチャンネルを開設しました。このチャンネルでは、NISAやiDeCo、ふるさと納税といった資産形成に役立つ制度について、初心者にも理解しやすいよう、かみ砕いた解説を動画で発信しています。
YouTubeの登録者数は70万人を超え、わかりやすさと親しみやすい語り口が多くの支持を集めています。SNSや講演活動、メディア出演なども積極的に行っており、金融教育の分野で高い信頼を得ている人物です。動画だけでなく、ブログや書籍でも情報を発信しており、読者や視聴者からの質問に対して丁寧に回答する姿勢も、多くの人から共感を集めています。

本書の要約
『イラストと図解で丸わかり! 世界一やさしい新NISAの始め方』は、新しくなったNISA制度、いわゆる「新NISA」について、制度の全体像から活用法までを網羅的に解説している一冊です。この制度は、2024年からスタートし、従来のNISAと比べて非課税投資枠の拡大や非課税期間の無期限化など、大きな変更点が加えられました。本書では、そうした制度の変更点を一つひとつ丁寧に取り上げながら、投資初心者でもつまずかずに理解できるよう、文章の語り口やビジュアル面にまで細やかな配慮がされています。
本書の大きな特徴は、制度のしくみを解説するだけにとどまらず、それを「どう使うか」に重点を置いている点です。たとえば、新NISAの2つの投資枠(つみたて投資枠と成長投資枠)をどう組み合わせるとよいのか、どのような投資信託を選べばリスクを抑えながら長期的な資産形成につなげられるのかといった、実践的なアドバイスが数多く盛り込まれています。さらに、20代、30〜40代、50〜60代といった年代別の章構成により、自分のライフステージに合った戦略を学ぶことができるのも本書の強みです。
読み進めるにつれ、「自分にもできるかも」という気持ちが自然と芽生えてくるような構成になっており、知識ゼロの状態から新NISAをしっかりと理解し、自信をもって投資をスタートさせるための道しるべになってくれるでしょう。

本書の目的
本書が目指している最も大きな目的は、新NISAという制度がより身近で、実際に活用できるものとして多くの人に伝わるようにすることです。「制度について何となく聞いたことはあるけれど、難しそう」「自分にはまだ早い」「投資って損しそうで怖い」といった漠然とした不安を払拭し、誰でも安心して第一歩を踏み出せるように丁寧に背中を押してくれます。
特に、新NISAは仕組みこそシンプルですが、実際に活用するとなると、証券口座の開設、商品選び、投資額の決定、投資の方法(積立 or 一括)、出口戦略など、さまざまな判断が必要です。本書では、それら一つひとつの選択肢について背景から丁寧に説明されており、読者が自分にとって最適な判断を下せるように導いてくれます。加えて、年代別の戦略では、若年層なら時間を武器にした長期積立、中年層なら教育費や住宅資金とのバランス、シニア層なら安定性と流動性を重視した運用スタイルなど、具体的かつ現実的な提案がなされており、自分のライフスタイルと照らし合わせながら読み進めることが可能です。
このようにして本書は、ただ制度を知るだけの「読み物」ではなく、制度を活かして資産形成を進めるための「行動の手引き」として設計されていることが分かります。

人気の理由と魅力
『イラストと図解で丸わかり! 世界一やさしい新NISAの始め方』が多くの読者に支持されている理由は、その構成力と読者目線のやさしさにあります。まず、最大の魅力は、専門知識がなくても読み進められる工夫が随所に施されている点です。たとえば、NISAや投資信託といった金融用語も、最初にわかりやすく解説されたうえで、以降の章では繰り返し丁寧に扱われており、読みながら自然と用語が頭に入ってきます。
また、読者が実際に「どう行動すればいいか」が具体的に示されていることも、本書の大きな魅力です。ただ制度の説明をするだけでなく、実際にどの証券会社で口座を開けばいいのか、どんなファンドを選べばいいのか、投資金額はどう考えればいいのかといった、踏み込んだ情報まで提供されています。しかもそれが、情報の押しつけではなく、読者自身の選択を後押しする形で語られているため、安心して読み進めることができます。
さらに、著者の小林氏が長年にわたりYouTubeで培ってきた「初心者に伝える力」が、本の構成にも活かされています。語りかけるような文体と、実際の質問に基づいたQ&Aの章は、まるで自分のために書かれたような感覚を抱かせてくれます。動画では一方通行になりがちな情報提供が、本という形になることで何度でも見返せるツールとなり、知識の定着にもつながっています。

本の内容(目次)

本書は、新NISAの基本から実践的な運用方法までを段階的に学べる構成となっており、初心者でも体系的に理解を深めていけるよう丁寧に設計されています。
以下に挙げる章立てを通じて、制度の全体像から年代ごとの運用戦略、さらには運用時の落とし穴や疑問への対応までを網羅しています。
- 第1章 新NISAっていったい何なの?
- 第2章 新NISAでおすすめの商品は?
- 第3章 新NISAを実際に始めてみよう
- 第4章 知らないと怖い、新NISAの落とし穴は?
- 第5章 20代向けの新NISA投資戦略
- 第6章 30~40代向けの新NISA投資戦略
- 第7章 50~60代向けの新NISA投資戦略
- 第8章 新NISAのよくある質問にまとめて回答
それぞれの章は、特定のテーマに特化しながらも全体の理解につながるよう巧みにリンクされており、順番通りに読んでも、気になる箇所から読み進めても、学びやすい設計がなされています。
第1章 新NISAっていったい何なの?
この章では、まず「NISAとは何か」という投資未経験者でも理解できる基礎知識から丁寧に解説されています。これまでのNISA制度には、つみたてNISAや一般NISAなど複数の枠が存在していましたが、2024年の制度改正により、よりシンプルかつ強化された「新NISA」がスタートしました。これまでの制度との違いや変更点についても詳しく比較されており、何がどう変わったのかを明確に理解できる構成になっています。
特に注目すべきは、非課税期間が「無期限」になった点と、生涯非課税投資枠が1800万円に設定された点です。これにより、これまでよりも長く、そして大きな金額を非課税で運用できる可能性が広がりました。加えて、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になったことも、新たに導入された柔軟性のひとつです。こうした新制度の魅力を、著者は図解や事例を交えながら、誰でも理解できるように解説しています。

新NISAはただの制度変更ではなく、長期的な資産形成を支えるインフラの強化と言えます。
まずは仕組みをしっかり理解することで、「使わないともったいない」という実感が得られるはずです。
第2章 新NISAでおすすめの商品は?
この章では、実際に新NISAで購入できる商品がどのようなものであるか、そしてどんな基準で選ぶべきかを丁寧に案内しています。中でも、初心者にとって重要なポイントは、「リスクを抑えつつ、安定的な成長を期待できる商品をどう選ぶか」という視点です。
本書では、まず投資信託を中心に紹介し、とりわけインデックスファンドに注目しています。インデックスファンドとは、日経平均株価やS&P500といった市場の平均に連動するように設計された投資信託のことで、個別株のように銘柄を選ぶ手間がかからず、分散投資によってリスクを抑えられる特長があります。特に「全世界株式」や「米国株式」のファンドについては、なぜそれが支持されているのか、どのようなリスクがあるのかといった点まで踏み込んで解説されています。
為替リスクや信託報酬といった専門的な概念についても、かみ砕いた説明があり、読者が「分からないまま進めてしまう」ことがないように配慮されています。配当を重視する人のためには、高配当株式の選択肢にも触れられており、多様なスタイルに応じた提案がなされている点も印象的です。

投資信託は一見シンプルに見えて、実は中身の違いがパフォーマンスに大きく影響します。
どの商品を選ぶかは、制度以上に重要なポイントです。
第3章 新NISAを実際に始めてみよう
この章では、いよいよ実際に新NISAで投資を始めるための手順が紹介されています。制度の概要や商品選びを理解しても、実際に始める段階でつまずいてしまう人は少なくありません。そこでこの章では、証券口座の開設方法、必要書類の準備、NISA口座の選び方など、基本的な準備作業についてわかりやすく案内されています。
また、投資に充てる金額の決め方や、積立投資と一括投資の違いについても丁寧に解説されています。たとえば、積立投資は毎月少しずつ投資する方法で、価格変動リスクを平準化できるメリットがあります。一方で、一括投資は最初にまとまった金額を投入することで、タイミングが良ければ大きなリターンも期待できます。自分の性格や資金状況に応じた選び方を理解することで、無理なく投資を継続することが可能になります。
さらに、投資を始めた後は「できるだけ手間をかけない」ことが推奨されており、いわゆる「ほったらかし投資」という考え方も紹介されています。このアプローチは、仕事や育児で忙しい人にとって非常に相性が良く、長期的な視点で資産を育てるのに適しています。最後には、新NISAで得た資産をどうやって取り崩すか、つまり出口戦略についても触れられており、スタートからゴールまでを見通せるようになっています。

投資の難しさは「始めるまで」にあると言われます。
口座開設と少額投資から始めることで、思っていたよりもずっと簡単だと感じられるはずです
第4章 知らないと怖い、新NISAの落とし穴は?
この章では、新NISAを利用するうえで注意すべきポイントや、初心者が陥りがちな失敗について解説されています。投資というと、成功する可能性ばかりに目が行きがちですが、現実には間違った判断をしてしまうこともあります。たとえば、「満額使わないともったいない」という思い込みから無理に大きな金額を投資してしまい、家計が苦しくなるようなケースです。自分の生活を犠牲にしてまで投資をすることは、結果として資産形成の妨げになってしまいます。
また、インターネットやSNSで話題になっている人気のファンドを、内容をよく理解しないまま選んでしまうリスクについても触れられています。ファンドにも性格があり、自分の目的やリスク許容度に合わない商品を選ぶと、想定外の値動きに耐えられず途中でやめてしまうことになりかねません。さらに、長期運用が前提である新NISAだからこそ、相場の上下に一喜一憂せず続けるメンタル面の大切さも強調されています。
損失が出たときに感じる焦りや後悔も、事前に知っておくことで冷静に対処できるようになります。また、制度的に18歳未満が利用できない点なども紹介されており、家族での資産形成を考えている場合は注意が必要です。こうした「知っておけば避けられるミス」をあらかじめ学ぶことができるのが、この章の大きな役割です。

制度は万能ではありません。
「非課税」という言葉に惑わされず、ルールとリスクを理解したうえで、冷静に使いこなすことが重要です。
第5章 20代向けの新NISA投資戦略
この章では、20代という若い世代が新NISAを活用することで得られる大きなメリットについて解説されています。投資において最も大きな武器の一つは「時間」です。若いうちに投資を始めることで、複利の効果を最大限に活かすことができ、長期的な資産形成において有利なポジションを築くことができます。複利とは、利益が元本に上乗せされてさらに利益を生むという仕組みで、時間が長ければ長いほど資産の増加スピードが加速します。
また、「少額の投資では意味がないのでは?」という疑問にも真っ正面から向き合い、月々数千円からでも十分な成果が見込めることを、具体的なシミュレーションを交えて説明しています。また、20代のうちに満額の投資枠を活用することで、将来的には早期リタイア(FIRE)も視野に入れられる可能性があるという考え方も提示されており、未来への選択肢が広がることが伝わってきます。
投資初心者に向けては、インデックスファンドなど安定した成長が見込める商品が推奨されており、リスクの取りすぎを避けながら着実に資産を増やしていくための方針が丁寧に説明されています。さらに、20代のうちに投資と向き合うことで、お金の使い方そのものに対する意識も高まり、将来にわたる資産形成の土台を築くことができると述べられています。

20代での投資は、金額以上に“時間”という最大の資産を活用する行動。
早く始めるほどリターンも大きくなります。
第6章 30~40代向けの新NISA投資戦略
30代から40代は、仕事や家庭といった生活面でも責任が大きくなる時期であり、同時に教育費や住宅ローン、老後資金といったお金の悩みも具体化してくる年代です。この章では、そうした人生のステージに応じた新NISAの活用方法を提案しています。たとえば、子どもの進学に備えて教育資金を積み立てたい、あるいは自分の老後資金を計画的に準備したいという目的に対し、どのように制度を使えば効果的かをわかりやすく解説しています。
特にこの世代は、ある程度の余裕資金を持っている場合も多く、まとまった金額で投資を始めたいというニーズにも応えています。成長投資枠の活用法や、積立投資とのバランスの取り方についても詳しく触れられており、短期的な生活費と長期的な資産形成を両立させるための視点が散りばめられています。
また、30〜40代の読者は「リスク管理」にも関心が高まる時期です。資産を増やすだけでなく、「減らさないための工夫」についても具体的に言及されており、保守的な運用を志向する人にとっても役立つ内容が多く盛り込まれています。

この年代の投資は、「守り」と「攻め」のバランスが重要になります。
制度を使いこなすだけでなく、自分のライフプランとしっかり結びつけることが、最も賢い活用法です。
第7章 50~60代向けの新NISA投資戦略
50〜60代というと、投資のスタートには遅すぎるのではないかと感じる方もいるかもしれません。しかしこの章では、むしろ今からでも資産運用を始める意義があることを、安心感のある語り口で伝えています。すでに退職金や貯蓄がある人にとっては、資産の保全とともに適度な成長を目指す投資が現実的です。この章では、「守りながら育てる」ことをキーワードに、リスクを抑えた運用方針が提案されています。
具体的には、安定配当を出す銘柄への投資や、値動きの少ないバランス型ファンドなど、年齢やライフスタイルに合わせた選択肢が紹介されています。また、流動性を確保すること、すなわち必要な時にすぐお金に換えられることの重要性についても丁寧に説明されています。加えて、著者の実父の実際の運用例が掲載されており、同年代の読者にとってリアルな参考資料となっています。
この年代では、無理な高リターンを狙うのではなく、「安心して老後を迎えるための手段」として新NISAを活用する考え方が求められます。制度の枠を理解しながら、少しずつでも利益を出していくためのコツが、分かりやすく紹介されているのがこの章の魅力です。

50代からの投資は、「残された時間」と「安心した老後」のバランスを取る戦いです。
短期間でも制度を賢く使えば、十分な価値が得られます。
第8章 新NISAのよくある質問にまとめて回答
最終章では、読者が新NISAについて持ちがちな疑問に対して、Q&A形式で実践的な回答が並びます。「つみたてNISAをやっていたけどどうなるの?」「ジュニアNISAとの違いは?」「途中で金融機関を変えることはできる?」といった、制度面の疑問から、「暴落時はどう対処すべき?」「配当は受け取るべき?再投資すべき?」といった運用上の細かい悩みまで、非常に網羅的にカバーされています。
特に注目したいのは、生涯投資枠の復活のルールや、成長投資枠を使うタイミングの考え方といった、制度の細かい運用に関する部分です。これらは公式サイトなどでもわかりにくい説明が多いため、本書のように具体例や日常感覚に寄せた言い回しで丁寧に解説されていることは、読者にとって非常にありがたいポイントと言えるでしょう。
質問のひとつひとつが独立して読めるように構成されており、何か不明点が生じたときにすぐ参照できる使い勝手の良さも本書の大きな魅力のひとつです。読み終えたあとも、リファレンスとして手元に置いておきたいと感じる章です。

疑問を解消できることは、投資継続のカギになります。
「わからないからやめる」ではなく、「調べればわかるから続けられる」状態を、本書はしっかりと支えてくれます。
対象読者

本書は、「投資を始めたいけれど何から手をつけていいのか分からない」という人をはじめ、制度改正により一新された新NISAの活用法を学びたい人、そして家族単位で将来のお金を計画的に備えたい人まで、幅広い層に向けて書かれています。
具体的には以下のような読者におすすめです。
- 投資をこれから始めたい初心者の方
- 新NISAの制度変更について知りたい人
- 自分に合った年代別戦略を立てたい人
- 忙しくて投資に時間をかけられない会社員
- 夫婦や家族で資産形成を考えている人
それぞれの立場に合わせて、必要な知識と実践のヒントがやさしく、そして実用的に紹介されており、「難しそう」と感じていた人でも自然と理解が深まるような構成になっています。
投資をこれから始めたい初心者の方
これまで投資に触れてこなかった人にとって、「新NISA」という言葉はどこか縁遠く、難しそうに聞こえるかもしれません。しかし、本書はそうした投資未経験者を対象に、最初の一歩を踏み出せるよう丁寧に導いてくれる構成となっています。制度の仕組みから実際の始め方、口座の開設方法や銘柄選びのポイントまで、すべてがやさしい言葉と図解で説明されており、専門用語が分からなくてもスムーズに読み進めることができます。
特に、「どうせ少額じゃ意味がないのでは?」と不安を感じている初心者に対して、本書は「早く始めることが最も大きなリターンにつながる」という投資の基本をわかりやすく伝えてくれます。長期的な資産形成においては、金額よりも時間の方が圧倒的に重要であり、初心者でもできる範囲から始めることの意義がしっかりと説かれています。

投資初心者は「分からないから始められない」と思いがちですが、本書を読めば「分かるからやってみたい」に変わります。
知識ゼロでも安心してスタートできる内容です。
新NISAの制度変更について知りたい人
2024年から大幅に改正された新NISA制度は、非課税枠の拡大や期間の無期限化、生涯投資枠の導入など、過去のNISAとは大きく異なります。そのため、すでに旧NISAを利用していた人にとっても、「何がどう変わったのか」をしっかり理解しておくことが重要です。本書では、こうした制度変更の要点を、ひとつひとつ丁寧に解説しています。
たとえば、「成長投資枠とつみたて投資枠はどう違うの?」「旧NISAの投資分はどう扱われるの?」といった実務的な疑問にも、Q&A形式や図解を使って分かりやすく答えており、制度の全体像と細部の両方がしっかりと見えてきます。制度変更をただのニュースとして受け止めるのではなく、実際の投資にどう活かすかまでを学べる点が、本書の大きな特徴です。

新制度の正しい理解は、賢く使いこなすための第一歩です。
本書なら、曖昧だった情報がしっかりとつながり、制度の全体像を自然と理解できるようになります。
自分に合った年代別戦略を立てたい人
新NISAを活用して資産形成を進めるにあたって、年齢やライフステージに応じた戦略を立てることは非常に重要です。たとえば、20代と50代では、投資にかけられる時間も目的も大きく異なります。本書では、その点を踏まえ、20代・30〜40代・50〜60代といった年代別に、新NISAの活用法を詳細に解説しています。
若い世代には、複利効果を最大限に活かすための積立戦略が提案されており、将来的なFIRE(早期リタイア)を視野に入れた投資計画まで言及されています。一方で、中高年層に向けては、リスクを抑えつつ資産を安定的に育てるための方法や、流動性の確保といった現実的なテーマが扱われています。自分の年齢や生活状況に合わせて読み進めることで、「自分にとって無理のない、納得できる投資スタイル」を見つけることができる構成です。

年齢や家族構成、収入状況によって最適な投資戦略は異なります。
本書はその違いを丁寧に教えてくれるので、自分にぴったりの設計が見えてきます。
忙しくて投資に時間をかけられない会社員
仕事や家事に追われる日々の中で、投資にまで手を回す余裕がないという人は少なくありません。しかし、投資は「時間をかけた人が勝つ」わけではなく、「正しい仕組みを選び、ほったらかしでも育てられるように設計する」ことがカギになります。本書では、そうした時間のない人でも安心して取り組める「ほったらかし投資」の考え方が紹介されています。
特に、毎月決まった金額を自動的に投資する「積立投資」は、働きながらでも実践しやすく、価格の変動リスクを平準化できるというメリットがあります。さらに、長期運用を前提とした新NISA制度なら、時間を味方にした投資スタイルがぴったり合います。忙しい中でも「何もしないのではなく、自動で増える仕組みを持つ」という安心感を得たい方には、本書の内容が強く響くはずです。

投資は「時間をかけるもの」ではなく、「仕組みで続けるもの」です。
仕事で忙しい人ほど、最初の設計を丁寧に行うことが成功への近道です。
夫婦や家族で資産形成を考えている人
将来の生活設計を考えるうえで、家族全体での資産形成を視野に入れることはますます重要になっています。本書では、夫婦で新NISA口座を開設するメリットや、子育て期に必要な資金をどう準備するかといった、家庭単位での運用戦略も丁寧に解説されています。個人での資産形成にとどまらず、家族全体で「どうお金と向き合うか」という視点を持てる内容になっている点が特徴です。
特に、夫婦でそれぞれ別々に非課税枠を持てるという新NISAの制度的な利点を活かすためには、事前の話し合いや計画が欠かせません。本書ではそのための指針やヒントがわかりやすく示されており、共働き世帯や子育て世帯にとって非常に実践的な内容となっています。お金の話題を家庭内でオープンにするきっかけにもなる一冊です。

資産形成は個人だけの問題ではありません。
夫婦や家族で協力して取り組むことで、安心感と将来設計の精度が格段に高まります。
本の感想・レビュー

制度の変更点をしっかり解説
私は数年前から一般NISAを使ってきたので、2024年から制度が大きく変わると聞いて、ある程度の知識はあるつもりでいました。ただ、細かい点や「生涯投資枠って実際どうやって使うのか」といった具体的な運用面では曖昧な理解しかなく、自信を持って家族に説明できるほどではありませんでした。
この本の素晴らしいところは、まさにその「中途半端な知識」を整理してくれる点にあります。旧制度と新制度の違いを一から十まで並べ立てるのではなく、実際に活用するうえで必要となる知識に絞って、明快に対比させてくれている。表で比較されている箇所などは一目で理解できるようになっており、「自分が何を知っていなかったのか」がはっきりと分かるのです。
また、制度そのものの説明に終始せず、それがどんなふうに活用につながるのか、実際の投資行動にどう反映されるのかまで丁寧に触れている点も印象的でした。制度の概要と実践的な使い方の“橋渡し”になっている、数少ない本だと思います。単なる解説書ではなく、現場で役立つガイドという感覚です。
図解のわかりやすさが神レベル
金融とか税制って、ただでさえ難しいイメージがあるのに、それが文章だけで説明されていたら、もうお手上げなんです。これまで何度も「NISAの本に挑戦してみよう」と思って買ってみたものの、読むうちにどんどん混乱して、途中でギブアップしていました。でも、この本は最初のページから「これなら読める」と思わせてくれる工夫が詰まっていました。
特にありがたかったのが、各章で出てくるカラフルな図やイラストの存在です。たとえば制度の仕組みを説明するときに、文章では伝わりにくい「非課税枠の使い方」や「つみたて投資枠と成長投資枠の違い」といったポイントを、図にまとめてくれていて、読むというより“見る”ことで理解が深まりました。ページをめくるたびに、自然と目に飛び込んでくるビジュアルが、知識を自分の中に根づかせてくれる感覚です。
図や表が多いと子ども向けの本のように思われるかもしれませんが、決して幼稚ではなく、むしろ必要最低限の情報が整理されていて、知識ゼロの人でも無理なく入っていける。むしろこういった「わかりやすさ」は、初心者にとって何よりの“配慮”だと改めて実感しました。
動画視聴者にはおなじみの信頼感
僕はバンクアカデミーのYouTubeチャンネルを毎週観ていて、小林さんのファンです。だからこの本が出ると聞いたときは、正直「動画と同じ内容じゃないのかな?」と少し不安もありました。でも、読んでみて驚いたのは、彼の話し方やテンポの良さが、そのまま文章に落とし込まれていたことです。口調も優しく、読みながら「ああ、あの動画の雰囲気そのままだ」と何度も思いました。
動画ではどうしても説明しきれなかった細かい部分や、「あとでメモしたかったな」と思った情報も、書籍では網羅的に整理されていて、しっかりと学び直せる構成になっています。むしろ動画ではサラッと流していた部分が、本ではより深く、丁寧に書かれていて、両方をセットで活用することで理解が格段に深まりました。
それともうひとつ。やはり動画を見てきた自分にとって、紙面での小林さんの語りかけは、非常に親しみを感じます。「あなたにもできますよ」「難しく考えすぎなくていいんです」と言ってくれているような一文に出会うたび、安心しながら読み進められました。
投資初心者の不安がスーッと消える
正直に言うと、投資って自分には無縁だと思っていました。お金に関する話題が苦手で、ましてやNISA制度なんて、名前だけ知ってる程度。でも最近、子どもの進学や老後の生活のことを考えるようになり、「このままで大丈夫なんだろうか…」という不安がずっと心に引っかかっていました。
そんな中で出会ったのがこの本です。タイトル通り「やさしい」内容であることはもちろんですが、それ以上に驚いたのは、読みながら気持ちがラクになっていったこと。難しい言葉が出てきたらすぐに補足が入り、制度の話も実生活に寄り添った目線で書かれているから、ひとつひとつの知識が「自分のための情報」としてスッと入ってきました。
読み終わった後、「私でも始めていいんだ」と心から思えたのは初めての経験です。完璧じゃなくても大丈夫、まずは少しずつ慣れていけばいい――そんなメッセージが本全体を通して伝わってきて、気がつけば前向きな気持ちになっていました。
家族で読むと話題にしやすい
私は今年で退職を迎え、これからは年金と貯金を中心に生活していくことになります。ただ、それだけでは心もとないという思いがあり、息子に勧められて新NISAを調べ始めました。ただ、ネットで得られる情報は専門用語ばかりで分かりづらく、「やっぱり自分には無理か」とあきらめかけていたんです。
この本を読んでまず感じたのは、「こういう本を若い世代だけでなく、年配の人にも届けてほしい」ということ。文章は平易で、制度の説明もやさしく、何より読んでいてストレスを感じませんでした。そして何よりうれしかったのは、読み終えた後に、息子とNISAについて自然に会話できたことです。今まで資産のことはなんとなく話しづらかったのですが、本という共通の話題があることで、距離がぐっと縮まりました。
夫婦間でも、「私たちの老後資金、どうしていこうか」と話すきっかけになりました。情報を得るだけでなく、人との会話や関係性にまで影響を与えてくれる本は、なかなかないと思います。
年代別戦略がまさに実用書
NISAの話題はずっと気になっていたのですが、「若い人向けなんじゃないか」と勝手に思い込んで、どこか自分には縁がないと感じていました。ところがこの本には、30〜40代向けの戦略がしっかり用意されていて、読んでいるうちに「これは私に必要な知識だった」と気づかされました。
教育費や住宅ローン、老後資金の準備など、ライフステージに応じた視点で「どう投資すればいいか」が明確に書かれているので、ただのお金の話ではなく、自分の人生設計と直結してくる実用的なアドバイスとして響いてきました。
特に、時間の使い方やリスクのとり方に関しては、自分の年齢だからこそ意識すべきことがあると気づかされました。この本を読まなければ、ずっと「何から手を付ければいいかわからない」という不安のままだったかもしれません。読んだあと、具体的に行動に移せる内容になっている点が、本当にありがたかったです。
Q&Aが役に立ちすぎる
僕は投資の勉強を始めたばかりで、「新NISAってお得らしい」という程度の知識しかありませんでした。だけど実際に口座開設を検討し始めると、細かい疑問が次から次へと湧いてきて、「これってどうすればいいんだ?」とネットで検索する毎日。でも断片的な情報ばかりで、全体像がつかめずにもやもやしていたんです。
この本のQ&Aセクションを読んだとき、本当に「これが知りたかった!」という気持ちでいっぱいになりました。「つみたてNISAからどう移行すればいいの?」「成長投資枠っていつ使えばいいの?」など、まさに自分が疑問に感じていた部分がピンポイントで丁寧に解説されていたんです。
答え方も、難しい言葉を避けながらもきちんと根拠があって、ただ「安心させるため」ではなく、納得して行動できるように書かれているのが好印象でした。読者の立場に寄り添ってくれていることが伝わってくる、そんな一冊です。
出口戦略まで解説があるのが安心
今まで何冊か投資の本を読んできましたが、「始め方」の説明があっても「やめ方」や「出口」の話は書いていないものが多く、ずっとモヤモヤしていました。新NISAに関しても、使い始めることには多くの情報があっても、「いつ・どうやって取り崩すか」という話はほとんど見かけませんでした。
この本は違いました。ちゃんと出口戦略に触れてくれている。しかもそれが終盤にさらっと紹介されているのではなく、運用後のフェーズとしてしっかりと一章で組み込まれているのが素晴らしいと思います。自営業という立場上、収入の波があるので、必要なタイミングで資産をどう取り崩していくかを意識する必要があるのですが、そこに実用的な視点で言及されていたことが非常に助かりました。
ただ投資をするのではなく、目的と出口をセットで考える重要性を、改めて認識できたのは大きな収穫でした。安心して始められるだけでなく、将来への備え方まで示してくれる。そういう意味で、この本は“終わり”まで責任を持って案内してくれるガイドだと感じました。
一歩踏み出せたきっかけになった
私は正直、投資の世界にはずっと縁がないと思っていました。生活も年金とパート収入でなんとか成り立っていて、資産運用という言葉にはどこか「自分には関係ない」と線を引いていました。でも、ニュースで物価の上昇や老後資金の不足について耳にするたび、心のどこかで不安が膨らんでいたのです。
そんなときに、友人に勧められて読んだのがこの本でした。最初は難しいかもしれないと身構えていたのですが、読み進めるうちに「これは私のような人のための本なんだ」と感じるようになりました。言葉がやさしく、焦らせるような表現がなくて、「あなたのペースでいいんですよ」と寄り添ってくれている気がしました。
読み終えたあと、思い切って証券口座を作りました。まだ投資は始めたばかりですが、あの一冊がなければ、最初の一歩を踏み出せなかったと思います。この年齢になっても、新しいことを学ぶのは遅くないと気づかせてくれた本でした。
まとめ

この書籍を読み終えたあと、どんな気づきが得られ、どのような行動につなげられるのか――読後の視点を整理するために、最後に重要なポイントを振り返っておきましょう。
以下の3つの観点から、読者の理解と今後の実践に役立つ内容をお届けします。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれの内容は、これから新NISAを始める方にとって心強い道しるべとなるはずです。
未来の自分のために、いま何をすべきか。そのヒントをこのパートで確認していきましょう。
この本を読んで得られるメリット
投資を始めたいけれど不安がある、制度の仕組みが難しそうで一歩が踏み出せない──そんな人にとって、本書はまさに“最初の一冊”として最適です。
ここでは、本書を通じて得られる主な利点を具体的にご紹介します。
制度の全体像が視覚的に理解できる
投資初心者がつまずきがちな制度の理解を、図解とイラストを用いて視覚的に伝えてくれるのがこの本の大きな特長です。抽象的な説明ではなく、具体的な場面や数字、フローに落とし込んで示されているため、どんな人でも直感的に仕組みを理解することができます。「制度が複雑で手が出せない」と感じていた人でも、自然と内容が頭に入り、知識が定着する構成になっています。
実践につながるステップが丁寧に紹介されている
読み進めるだけで「では次に何をすればいいのか」が明確になる構成が取られている点も見逃せません。たとえば、証券口座の選び方、毎月の投資金額の決め方、積立方法の種類とその特徴など、実務に直結する情報が整理されており、「本を読み終えたらそのまま行動に移せる」という実用性が備わっています。単なる解説書ではなく、読者の“動き”を想定したつくりです。
年代別の戦略が自分事として響く
多くの投資本が一般論で終わってしまう中、この本は20代から60代までのライフステージごとの戦略を丁寧に提示してくれます。「いまの自分には何ができるのか」「将来に備えてどんな選択肢があるのか」が明確になることで、投資への距離感がぐっと縮まります。若年層には将来の可能性を、シニア層には今からでも遅くないという前向きなメッセージが伝わる構成です。
不安や疑問に対する答えがあらかじめ用意されている
Q&A形式の章では、新NISAを始める際に多くの人が感じるであろう疑問が網羅的に取り上げられています。たとえば、「旧NISAはどうなるの?」「途中で売却したらどうなる?」といった制度に関する不安から、「暴落時はどう対応すべきか」といった運用面の不安まで、すでに答えが本の中に準備されているため、読みながら解決できる安心感があります。
手元に置いて繰り返し使える実用性がある
一度読んで終わりではなく、必要な時に必要な項目だけを読み返せる構成も大きな魅力です。特に、制度の細かい規定や用語、出口戦略に関する記述などは、投資を進めていく中で何度も確認したくなる情報です。本書はそのような使い方を前提に作られており、実用書としての価値が非常に高い一冊です。

新NISAという制度は、知識を持つだけで得られる利益が大きく変わります。
この本は、その知識を無理なく自分のものにし、行動へつなげるための“道しるべ”となります。
読後の次のステップ
本書を読み終える頃には、新NISAの仕組みがしっかりと理解でき、自分自身のライフステージに合わせた投資の全体像もつかめているはずです。しかし、知識を得ただけでは資産は増えません。大切なのは、理解したことをもとに具体的な行動を起こすことです。
ここでは、本を閉じたあとにどのようなステップを踏めば、新NISAを着実に始められるのかを紹介します。
step
1証券口座を開設する
最初に取りかかるべきは、新NISAに対応している証券会社での口座開設です。ネット証券をはじめとする多くの金融機関がNISA専用口座の受付を行っており、本書ではその中でも初心者にやさしいサービス内容の業者が紹介されています。開設にはマイナンバーカードや本人確認書類が必要となりますが、オンラインでの手続きも可能で、思ったよりも手間はかかりません。まずはここからスタートすることで、具体的な第一歩が踏み出せます。
step
2自分の投資予算と積立額を決める
新NISAは年間360万円までの非課税投資が可能ですが、全額を使い切る必要はありません。大事なのは、自分の生活費や貯蓄状況を把握し、無理なく継続できる金額を見極めることです。本書では「月3万円の積立を30年続けると、利回り5%で約1,395万円になる」といったシミュレーションが提示されており、数字をもとに将来を見据えた計画を立てるヒントが得られます。収入と支出のバランスを考慮して、日常生活に負担をかけない金額でスタートすることが大切です。
step
3投資対象を選び、運用を始める
実際に運用を始める際には、どの投資信託や株式に資金を振り分けるかを決めなければなりません。本書では「全世界株式インデックスファンド」や「米国株式インデックスファンド」など、初心者でも取り組みやすい商品が丁寧に解説されており、それぞれのメリット・リスクについても明示されています。また、投資信託の購入方法や設定手順についても具体的に説明されているため、初めてでも迷うことなく進められるようになっています。
step
4投資を継続する仕組みを整える
運用を始めたあとは、なるべく手間をかけずに継続できるよう、自動積立の設定を活用することがおすすめです。これにより、毎月決まった日に決まった金額が自動で投資されるため、日々の忙しさにかまけて放置することもありません。本書は「投資は始めたあとの仕組みづくりが大切」と繰り返し伝えており、読者が長期運用に対する不安を感じずに済むよう、運用継続のコツや心構えまで含めて教えてくれます。
step
5将来を見据えて「出口戦略」も考える
投資を始めた直後から、最終的にどう資産を取り崩していくかを考えるのは難しく感じるかもしれません。しかし、新NISAは非課税枠の復活がない制度であるため、売却のタイミングや資金の使い道をあらかじめイメージしておくことは非常に重要です。本書では「出口戦略」の章において、資産を減らさずに引き出していく方法や、ライフイベントに応じた売却の仕方が紹介されており、長期的な視野を持つきっかけになります。

投資において最大のリスクは、「何もしないこと」です。
本を閉じたあと、すぐに行動を始めるかどうかが、未来の資産形成に大きく影響します。
総括
新NISA制度のスタートは、これまで資産運用に縁がなかった人にとっても、将来のお金について真剣に考える良いきっかけになっています。しかし同時に、「何がどう変わったのか」「自分には関係あるのか」「始めるには何をすればいいのか」といった戸惑いも多く見受けられます。そうした中で、知識ゼロからでも迷わず制度を理解し、行動に移せるように導いてくれるのが、本書『イラストと図解で丸わかり! 世界一やさしい新NISAの始め方』です。
この本の最大の特徴は、新NISAの全体像を図解とやさしい文章で整理しながら、読者が自分に合った使い方を見つけて、実際に運用を始められるように設計されている点にあります。制度の仕組みをただ説明するだけでなく、どう活用すれば資産が育つのか、どんな商品を選ぶべきかといった実務的なアドバイスまでを自然な流れで学ぶことができる構成は、まさに「行動につながる一冊」と言えるでしょう。
また、20代から60代まで、ライフステージごとに戦略を提案している章立ては、自分の現状と将来に合った考え方を見つけやすく、読者それぞれに必要な知識が過不足なく提供されています。初心者がつまずきやすいポイントにはQ&Aで先回りして答えてくれており、読了後には安心感と実践意欲がしっかりと身についているはずです。
資産形成は短期間で結果を出すものではなく、コツコツと積み重ねていくものです。その第一歩として、この本は「読みやすさ」「分かりやすさ」「実用性」のすべてを兼ね備えており、投資の世界へ入るための頼れるガイドブックとなってくれます。制度を正しく理解し、自分の生活に無理なく取り入れるための確かな知識を、この一冊から得ることができるでしょう。

「新NISAって難しそう」と感じていた人にこそ手に取ってほしい、そして「これなら私にもできる」と実感してほしい、そんな想いが込められた実用書です。
今後の人生におけるお金との付き合い方を変えるきっかけとして、この本は確かな価値を提供してくれるに違いありません。
新NISAについて学べるおすすめ書籍

新NISAについて学べるおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 新NISAについて学べるおすすめの本!人気ランキング
- イラストと図解で丸わかり! 世界一やさしい新NISAの始め方
- 1時間でマスター!マンガと図解でわかる 新NISAの教科書
- 60分でわかる! 新NISA 超入門
- 9割の“普通の人”の最適解!「逆算ほったらかし」新NISA投資術
- 50歳ですが、いまさらNISA始めてもいいですか?
- 新NISAで始める!年間240万円の配当金が入ってくる究極の株式投資

