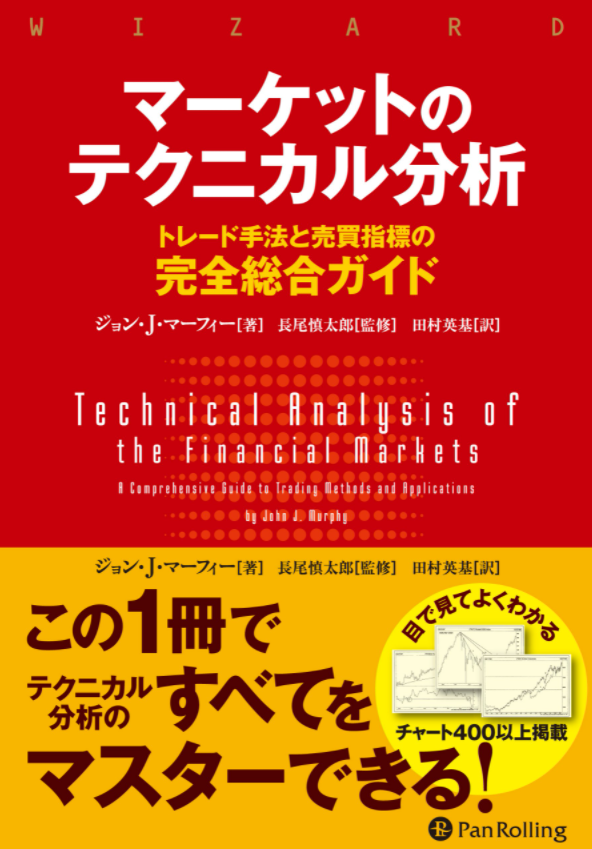
投資の世界で成功するためには、情報の波に流されず、確かな分析力と判断力が求められます。その核心を担うのが「テクニカル分析」です。『マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド』は、テクニカル分析の草分け的存在であるジョン・J・マーフィー氏によって書かれた、まさにその分析手法の“決定版”ともいえる一冊です。

本書は、チャートの見方や価格パターンの読み解き、トレンド分析の基礎から、上級指標・トレーディング戦略・システム構築に至るまで、幅広い内容を網羅しています。
400を超える豊富な実例チャートをもとに、視覚的にも理解しやすく構成されており、初心者からプロ志向の投資家まで、あらゆるレベルに対応しています。
もしあなたが、株式やFX、先物市場において自信を持って取引を行いたいと考えているなら、この本はその“地図”となり、“羅針盤”となるでしょう。
テクニカル分析を「知っている」から「使いこなす」へ。ここから、本当のトレード力が身につきます。

合わせて読みたい記事
-

-
テクニカル分析の勉強におすすめの本 7選!人気ランキング【2026年】
株式投資やFX、仮想通貨など、あらゆる金融商品のトレードにおいて重要なスキルのひとつが「テクニカル分析」です。チャートの動きから相場のトレンドや売買のタイミングを見極める力は、初心者から上級者まで、す ...
続きを見る
- 書籍『マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド』の書評
- 本の内容(目次)
- 第1章 テクニカル分析の哲学
- 第2章 ダウ理論
- 第3章 チャートの仕組み
- 第4章 トレンドの基本概念
- 第5章 主要な反転パターン
- 第6章 継続パターン
- 第7章 出来高と取組高
- 第8章 長期チャート
- 第9章 移動平均
- 第10章 オシレーターとコントラリーオピニオン
- 第11章 ポイント・アンド・フィギュア
- 第12章 ローソク足
- 第13章 エリオット波動理論
- 第14章 サイクル
- 第15章 コンピューターとトレードシステム
- 第16章 マネーマネジメントとトレード戦術
- 第17章 株式と先物の関連性―市場間分析
- 第18章 株式市場の指標
- 第19章 要点整理―チェックリスト
- 付録A 上級テクニカル指標
- 付録B マーケットプロファイル
- 付録C トレードシステム構築の要点
- 付録D つなぎ足
- 対象読者
- 本の感想・レビュー
- まとめ
書籍『マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド』の書評

このセクションでは、読者が本書を手に取る価値を総合的に理解できるよう、筆者の経歴から本の構成、目的、魅力に至るまでを幅広く紹介していきます。とくに、テクニカル分析に初めて触れる方にとっては、書き手の信頼性や実績、そして本が目指すところを知ることが安心材料になるでしょう。
以下の5つのポイントから解説を進めていきます。
- 著者:ジョン・J・マーフィーのプロフィール
- 著者:John J. Murphyのプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
このように多角的に見ることで、単なる学習書ではなく「一生使える実務書」である理由が浮かび上がってきます。
著者:ジョン・J・マーフィーのプロフィール
ジョン・J・マーフィーは、アメリカを代表するテクニカルアナリストであり、長年にわたって金融市場の分析に従事してきた人物です。彼のキャリアは、メリルリンチの先物部門でテクニカル分析ディレクターを務めたことに始まり、数々の実績を重ねてきました。その後、1980年代にはニューヨーク・インスティテュート・オブ・ファイナンスで講師として教鞭をとり、後進の育成にも力を注ぎました。
彼の影響力は金融機関の内部にとどまらず、一般投資家にまで広がります。特に、1986年に出版された『テクニカル・アナリシス・オブ・ザ・フューチャーズ・マーケット』は、世界中のアナリストやトレーダーに愛読され、数々の教育機関でテキストとして採用されてきました。FRBのレポートでも引用された経歴を持つことからも、その信頼性と権威の高さが伺えます。

著者:John J. Murphyのプロフィール
英語圏でのJohn J. Murphyの評価は極めて高く、彼の名は「市場間分析の父」として世界中のプロトレーダーに知られています。特に注目されるのが、異なる金融市場の関係性を読み解く「Intermarket Analysis(市場間分析)」という考え方の普及に尽力してきた点です。
彼はStockCharts.comでチーフテクニカルアナリストを務める一方で、マーケットの教育コンテンツをオンラインや出版物を通じて発信し続けています。また、彼の著書はアメリカだけでなく世界各国で翻訳されており、日本語にも多数の著作が存在します。実際、多くのプロフェッショナルや公認テクニカルアナリストの試験参考書としても活用されています。

本書の要約
『マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド』は、テクニカル分析に関するあらゆる知識を網羅した、まさに“百科事典”的な一冊です。その内容は、チャートの読み方といった基礎中の基礎から、価格パターン、トレンド分析、指標の活用法、さらにはエリオット波動理論や市場間分析といった高度なトピックに至るまで、幅広い領域をカバーしています。
本書の構成は全19章と4つの付録から成り、段階的に学べるように工夫されています。最初の章ではテクニカル分析の哲学や位置付けといった“思考の土台”を築き、その後にダウ理論やトレンド分析、ローソク足、移動平均など、具体的な分析手法へと進んでいきます。さらに、中盤以降にはオシレーターや出来高分析、エリオット波動理論など、より応用的かつプロフェッショナルな技術が登場します。
特徴的なのは、その圧倒的な図解数。400点を超えるチャートが掲載されており、文章だけでは理解しづらい動きや形状も視覚的に学べるようになっています。たとえば「ヘッド・アンド・ショルダーズ」や「ボリンジャーバンド」など、名前だけ聞くと難しそうな理論でも、実際のチャートで確認しながら読めるため、頭にすっと入りやすいのです。
また、最後の付録では、マーケットプロファイルやSTARCバンド、つなぎ足の作り方、トレードシステムの構築方法など、通常の入門書では触れられない上級テーマにも言及しており、長く手元に置いておきたくなる構成になっています。

本書の目的
本書が目指すのは、読者が「テクニカル分析の理論を理解する」ことだけではありません。最終的には、学んだ理論を「自分の売買判断に使える知識」に変えること、それこそがこの書の本質的な目的です。つまり、ただの知識の習得ではなく、「相場でどう生かすか」「利益を上げるためにどう使うか」という“実戦力”の育成に主眼が置かれています。
そのため、各章は単なる用語解説や定義の羅列ではなく、必ず「実際のチャートでどのように確認するのか」「どんな場面で使えるのか」「どのような誤用に注意すべきか」といった具体的な活用法が記載されています。例えば「ダブルボトム」や「トライアングルパターン」といったチャート形状がなぜ重要なのか、どのタイミングでエントリー・エグジットすべきかが詳細に説明されており、実践を意識した作りになっているのです。
また、特筆すべきは「市場間分析」や「マネーマネジメント」の章。これらは単なるチャート読解ではなく、相場全体を俯瞰するための視点を与えてくれます。たとえば、金利の上昇が株式市場や為替市場に与える影響、原油価格がどのように株価に影響するか、というように、複数の市場をつなげて考える方法を体系的に教えてくれます。
加えて、テクニカル指標を組み合わせた「システムトレード」の考え方や、その構築手法にも触れられており、最終的には読者自身がルールベースの戦略を組み立てて、検証・運用できるようになるところまで導いてくれます。

人気の理由と魅力
『マーケットのテクニカル分析』がこれほど長期にわたって評価され続けているのは、その「普遍性」と「実用性」の高さにあります。まず特筆すべきは、テクニカル分析に必要な知識が一冊でほぼ網羅されている点です。多くの投資書籍は、指標解説、心理分析、リスク管理などに分かれており、複数冊を読み分ける必要がありますが、本書はそれらを一元化しています。
400点を超えるチャートはすべて実際の市場データを用いており、読者が実際に目にするであろう状況を想定して説明されています。そのため、「実際の相場でどう使うか」が明確になっており、知識だけでなく“応用力”も鍛えられます。視覚的にわかりやすく、かつ説明も論理的であることから、初心者にとっても安心して学べる構成です。
章立てにも工夫があります。初学者がつまずきがちなポイントを順序立てて配置し、段階的に難易度を上げていく構成になっているため、「最初の1冊」としても非常に優秀です。一方で、上級者にとっては付録や後半のチャプターが特に価値を持ちます。たとえば、STARCバンドやケルトナーチャネル、マーケットプロファイルなど、現場で即使える高度なテクニックも豊富に紹介されています。
さらに、金融のプロフェッショナルたちからの信頼も厚く、国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)のCMT試験の参考書としても採用されています。このことは、単なる投資本としてではなく「プロの世界でも通用する教科書」であることを示しています。

本の内容(目次)

書籍『マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド』は、テクニカル分析の基礎から応用までを網羅的に解説した一冊です。初心者から上級者まで、あらゆるレベルのトレーダーにとって有益な内容が詰まっています。
以下に、本書の主要な章立てを紹介します。
- 第1章 テクニカル分析の哲学
- 第2章 ダウ理論
- 第3章 チャートの仕組み
- 第4章 トレンドの基本概念
- 第5章 主要な反転パターン
- 第6章 継続パターン
- 第7章 出来高と取組高
- 第8章 長期チャート
- 第9章 移動平均
- 第10章 オシレーターとコントラリーオピニオン
- 第11章 ポイント・アンド・フィギュア
- 第12章 ローソク足
- 第13章 エリオット波動理論
- 第14章 サイクル
- 第15章 コンピューターとトレードシステム
- 第16章 マネーマネジメントとトレード戦術
- 第17章 株式と先物の関連性―市場間分析
- 第18章 株式市場の指標
- 第19章 要点整理―チェックリスト
- 付録A 上級テクニカル指標
- 付録B マーケットプロファイル
- 付録C トレードシステム構築の要点
- 付録D つなぎ足
これらの章を通じて、読者はテクニカル分析の理論的背景から具体的な手法、さらには実践的な戦略までを体系的に学ぶことができます。
第1章 テクニカル分析の哲学
この章では、テクニカル分析の「考え方」や「前提条件」が紹介されています。著者ジョン・J・マーフィーは、テクニカル分析の基本的な哲学を「市場の動きはすべての情報を織り込む」とする立場から解説を始めます。つまり、価格の変動にはすでに経済指標や企業ニュースなど、あらゆる情報が反映されているという前提です。
テクニカル分析とファンダメンタルズ分析(企業の業績や経済動向を重視する手法)との違いも説明されており、それぞれのメリット・デメリットに触れています。また、分析のタイミングをどう捉えるか、異なる時間軸での応用可能性、対象市場の違い(株式と先物など)にも対応できる柔軟性が強調されています。
特に興味深いのは、テクニカル分析が「予測ツール」というよりも「確率的判断の支援ツール」であると捉えている点です。これは、「未来を当てる」のではなく、「条件が揃ったらこう動く可能性が高い」と考えるための分析手段であるという姿勢を示しています。

テクニカル分析は占いではありません。
「今あるデータに基づいて最も可能性が高い選択肢を見極める」ためのツールです。
第2章 ダウ理論
この章では、テクニカル分析の起源ともいえるダウ理論が詳しく説明されています。チャールズ・ダウが19世紀に提唱したこの理論は、相場の動きには規則性があるという前提に立ち、現在も多くの分析手法の根幹を成しています。
理論では、市場は3種類のトレンド(主要トレンド、中間トレンド、小トレンド)で構成されており、特に“主要トレンド”が投資判断において最も重視されるべきだとされます。また、終値を基に市場の方向性を判断することや、トレンドの継続には高値・安値の更新が必要であるといった原則も紹介されています。
さらに、ダウ理論の応用として、株式だけでなく先物市場や指数分析にも活かせるという点も強調されています。市場全体の健康状態を測るために、複数の指標(例えばダウ工業平均と輸送株平均)が連動して動いているかを確認するという考え方も紹介されています。

ダウ理論を学ぶことは、テクニカル分析全体の“地図”を手に入れるようなものです。
多くの現代的手法はこの理論に基づいているため、理解は不可欠です。
第3章 チャートの仕組み
チャートはテクニカル分析の“言語”とも言える存在であり、価格の変化を視覚的にとらえるための道具です。この章では、チャートの基本構造と、それぞれの特徴や用途が丁寧に解説されています。
代表的なものとして、「ローソク足チャート」「バーチャート」「ラインチャート」などがあります。ローソク足は日本発祥で、一本の棒に始値・高値・安値・終値の4つの情報が詰まっているため、短期間の値動きと市場心理を直感的に把握しやすいという利点があります。
また、チャートの目盛りには「算術目盛り」と「対数目盛り」の2種類があり、それぞれ価格変化の捉え方が異なります。たとえば、100円から200円と、1,000円から1,100円への値動きは、算術では同じ距離に見えますが、対数では前者のほうが大きな変化として表示されます。
さらに、取引量(出来高)や、先物市場特有の「取組高」も併せて表示することで、価格変動の裏にある市場の熱量や需給関係を把握できます。

チャートは“価格の履歴書”です。
その構造を正しく理解することで、過去から未来の兆候を読み取る力が養われます。
第4章 トレンドの基本概念
この章では、「トレンド」という言葉の定義と、その捉え方が解説されています。上昇、下降、横ばいの3方向のトレンドがあり、それぞれが短期・中期・長期の時間軸で存在します。
また、「支持線(サポートライン)」と「抵抗線(レジスタンスライン)」という、価格が跳ね返されやすい水準の考え方も紹介されます。これらの線は、トレンドの転換や継続を判断する上で非常に重要な役割を果たします。
トレンドラインやチャネルラインの引き方も具体的に解説されており、「3点以上を結ぶことで信頼性が高まる」といったルールも説明されています。さらに、フィボナッチ比率やギャン理論など、より数学的なアプローチも触れられ、トレンド分析が単なる「線引き」ではないことが分かります。

トレンドは“市場の流れ”を読む鍵。
水面下の流れを読み解くように、ラインの引き方にも技術と経験が求められます。
第5章 主要な反転パターン
この章では、チャートパターンを通して「トレンドがどのように終わり、反転するか」を読み解く技術が解説されています。特に有名なパターンとして「ヘッド・アンド・ショルダーズ」や「ダブルトップ」「ダブルボトム」などが紹介されます。
これらのパターンは、価格の動きが特定の形を作ることで、「これまでの流れが変わる兆し」を示してくれるものです。出来高との組み合わせによって、その信頼性はさらに高まります。パターンの形成過程や、形成後の価格目標(どこまで動くか)を計算する方法など、実践的な知識も丁寧に説明されています。
また、理想的なパターンばかりでなく、複合パターンや変則的な動きも紹介されており、チャート分析がいかに“現場感”のある判断を必要とするかがよく伝わってきます。

反転パターンは“相場の疲れ”を示すサインです。
チャートを見慣れることで、相場の変化をいち早く察知できるようになります。
第6章 継続パターン
この章では、現在のトレンドがそのまま続く可能性を示す「継続パターン」について取り上げられています。トレードの現場では、トレンドが転換するのか、それとも持続するのかを見極めることが非常に重要です。本章では、チャート上でその判断に役立つ典型的なパターンを学びます。
主な継続パターンには、トライアングル(対称・上昇・下降)、フラッグ、ペナント、ウエッジ、レクタングルなどがあります。これらの形状は、価格が一時的に休憩している「保ち合い状態」を意味しており、方向感を取り戻したときに再び元のトレンド方向に動く可能性が高いとされます。
また、「継続型ヘッド・アンド・ショルダーズ」など、反転パターンに似ていながらトレンドが継続するという例外的なパターンも取り上げられており、チャート読解における柔軟な視点が求められることが強調されています。

継続パターンは“トレンドは続く”という市場の心理を視覚化したもの。
パターンが完成するまで焦らず待つことが成功への鍵です。
第7章 出来高と取組高
テクニカル分析において、価格だけを見るのではなく「出来高(ボリューム)」や「取組高(建玉の量)」を確認することは極めて重要です。本章では、これらの数値がトレンドの信頼性を裏付ける手段として解説されています。
出来高は、ある価格水準でどれほど多くの市場参加者が取引を行っているかを示します。トレンドが強いときは出来高も増加し、逆に出来高が伴わない上昇や下落は信頼性に欠けるとされます。また、先物市場に特有の取組高も紹介されており、こちらは未決済のポジション数を示すため、投資家のポジション構造を読み解く手がかりになります。
さらに、COT(Commitment of Traders)レポートやオプション市場の指標(プット・コール・レシオなど)を活用したセンチメント分析も取り上げられており、実戦的な視点が豊富に盛り込まれています。

価格の裏に“どれだけ人が動いたか”を見るのが出来高。
多くの支持がある動きなのかどうかを確認できる、いわば信任投票の結果です。
第8章 長期チャート
この章では、短期的な値動きに惑わされず、大局を把握するための「長期チャート」の活用法が紹介されています。特に投資家やポートフォリオマネージャーにとって、長期の視点は不可欠です。
長期チャートでは、週足や月足といったスパンでの動きを分析することで、主要なトレンドや周期的なパターンを捉えることができます。さらに、先物市場においては「つなぎ足(連続チャート)」の使い方も解説されており、期近限月の価格差を吸収しながらトレンド分析を可能にする技術として紹介されています。
この章では、長期的な視野がなぜ重要か、またそれをどのように活用すべきかについての思考方法も共有されています。インフレ調整や構造的な価格変動の影響も踏まえた分析視点が求められることが強調されています。

長期チャートは“森を見る視点”。
目先の動きに惑わされず、大きな流れを読み解くためには不可欠なツールです。
第9章 移動平均
この章では、価格の変動を平均化してなめらかな線で表示する「移動平均(Moving Average)」の活用法が体系的に紹介されています。移動平均はトレンドの有無や方向性をつかむために非常に広く使われており、初心者からプロまで欠かせない基本指標の一つです。
単純移動平均(SMA)、指数平滑移動平均(EMA)、適応移動平均(AMA)などさまざまな種類があり、それぞれに特徴と使い分けがあります。たとえば、EMAは最近の価格により大きな重みを置くため、短期トレードに向いています。
さらに、移動平均を応用した「移動平均エンベロープ」や「ボリンジャーバンド」なども取り上げられており、価格の上下変動幅を把握する手段として有効です。ボリンジャーバンドは価格のボラティリティ(変動性)に応じて幅が変化するため、過熱感や反転のサインを読み取ることができます。
また、移動平均とフィボナッチ数列の関係、相場サイクルとの連携、最適化の是非といった高度なトピックにも踏み込んでおり、応用力の幅を広げる内容となっています。

移動平均は“相場の地形図”のようなもの。
現在の位置が高地なのか谷間なのかを教えてくれる、基本にして最強のツールです。
第10章 オシレーターとコントラリーオピニオン
この章では、トレンドが明確でない場面や過熱感を測るのに有効な「オシレーター系指標」と、一般投資家の心理を逆手に取る「逆張りの発想」が解説されています。
オシレーターとは、相場が「買われすぎ」か「売られすぎ」かを判断するための指標で、代表的なものとしてRSI(相対力指数)、MACD(移動平均収束拡散法)、ストキャスティクス、CCIなどがあります。これらは、特にレンジ相場やトレンドの転換点において力を発揮します。
一方で、「コントラリーオピニオン」とは、一般大衆の意見に逆らう投資戦略で、極端に強気・弱気になったときこそ転換点が近いと見る考え方です。投資家センチメント指数やプット・コール・レシオなどを使って、市場参加者の心理状態を分析するのが特徴です。
この章では、オシレーターと逆張りの考え方を組み合わせることで、より精度の高いタイミング判断が可能になることが示されています。

オシレーターは“感情のメーター”。
市場の熱狂や悲観を冷静に見極めるための重要な視点を提供してくれます。
第11章 ポイント・アンド・フィギュア
この章では、価格変動に注目した独自のチャート手法である「ポイント・アンド・フィギュア(P&F)」を取り上げています。このチャートは、時間の経過を一切無視し、純粋に価格の上昇と下降だけを記録するため、トレンドの明確化に優れています。
P&Fチャートは「X」と「O」で構成され、それぞれ価格の上昇・下降を意味します。たとえば、一定の価格幅(ボックスサイズ)で価格が上昇すれば「X」を追加、反対に下落すれば「O」の列に切り替えます。このようにして描かれるチャートは、ノイズが少なく、視覚的にトレンドや反転のポイントが捉えやすくなります。
また、P&Fチャートは独自のパターン認識や目標価格の計算方法も備えており、トレード戦略の一環として活用可能です。特に3枠反転ルールや水平カウント法による目標値の算出は、多くのプロトレーダーにも利用されています。

時間にとらわれず“価格だけ”に集中できるのがP&Fチャートの魅力。
シンプルだけど奥が深い分析手法です。
第12章 ローソク足
本章は、日本発祥で世界的にも普及しているローソク足チャートに特化した内容です。執筆はローソク足分析の第一人者、グレッグ・モリスが担当しています。視覚的な美しさと情報量の多さから、世界中のトレーダーに支持されています。
ローソク足は一本で「始値・高値・安値・終値」の4つの情報を持ち、陽線(上昇)と陰線(下落)を色で区別することで、直感的に値動きの強弱が理解できます。たとえば、実体の長さはトレーダーの勢いを示し、上下のヒゲは迷いや反転の兆しを読み取る材料となります。
また、複数のローソク足を組み合わせたパターン分析(たとえば包み足、ピンバー、たくり線など)も本章の中で詳しく解説されています。さらに、ノイズの排除や精度向上のために、特定の条件でフィルターをかける方法にも触れており、実戦的な使い方を学べます。

ローソク足は“市場の感情を映す鏡”。
価格の動きに込められた売り手・買い手の意図を可視化する最強のチャート表現です。
第13章 エリオット波動理論
本章では、相場のリズムや構造を説明するために提唱された「エリオット波動理論」が紹介されています。これは、相場はランダムに動いているのではなく、ある一定の“波”のパターンを繰り返すという考え方です。
理論によれば、市場の動きは「推進波(5波)」と「調整波(3波)」のセットで形成され、全体で8つの波によって構成されるとされています。これを基に相場の現在地や今後の動きを予測しようとするのがエリオット理論の基本です。
また、フィボナッチ数列との関係性も深く、波の長さやタイミングを測るためにフィボナッチ比率(0.618や1.618など)が使われます。さらに、エリオット波動はトレンドと連動するため、ほかの指標と組み合わせることで強力な分析ツールとなります。

波動理論は“市場のリズム”を知る鍵。
音楽で言えば、メロディーではなく“拍子”を感じ取るようなものです。
第14章 サイクル
この章では、相場における周期的な動きを分析する「サイクル理論」について述べられています。相場の変動には、短期・中期・長期という異なる時間スパンのサイクルが存在し、それらが組み合わさることで現在の価格の動きが生まれているとされます。
たとえば、「月末に株価が上がりやすい」「米大統領選の翌年に株価が強い」などの傾向も、一定のサイクルによる現象と解釈されます。これを利用することで、相場の“時間的なリズム”を読むことが可能となります。
この章では、複数のサイクルを重ね合わせて相場の転換点を予測する方法や、季節性サイクル、大統領選サイクル、最大エントロピースペクトラル分析(MESA)など、高度な手法も紹介されています。

サイクル分析は“相場の時計を読む技術”。
タイミングを測ることで、トレードの無駄を減らし、精度を高められます。
第15章 コンピューターとトレードシステム
この章では、コンピュータの力を活用して売買ルールを自動化・機械化する「トレードシステム」の構築法とその考え方が解説されています。現代のトレーダーにとって、戦略の検証や実行のためにテクノロジーの力を借りることは不可欠です。
まず、必要なハードウェアやソフトウェア、データの取得方法といった基本インフラについて解説し、次に各種テクニカル指標を組み合わせた売買アルゴリズムの作り方を説明しています。たとえば、MACDと移動平均を併用して売買シグナルを定義し、それをバックテストする工程が紹介されています。
ウエルズ・ワイルダーによる「パラボリックSAR」や「ディレクショナルムーブメントシステム(DMI)」のような古典的なシステム指標も取り上げられており、実践的なシステム構築の基礎が身につきます。
また、「最適化の落とし穴」や「過剰適合(オーバーフィッティング)」への注意喚起もされており、単なるテクニックではなくリスク管理や信頼性の検証を重視する姿勢が貫かれています。

トレードシステムは“感情を排除したルールの集合体”。
継続的に勝ち続けるには、仕組みとしての戦略設計が必要です。
第16章 マネーマネジメントとトレード戦術
この章は、いかに優れたテクニカル分析手法を身につけても、それを実際のトレードに落とし込む「戦術」と、資金を守るための「マネーマネジメント」が伴っていなければ意味がないことを教えてくれます。言い換えれば、勝つための「知識」だけでなく、負けないための「戦略」が不可欠なのです。
成功するトレーダーが守っている三大原則は、「戦術の明確化」「資金配分の適正化」「感情の制御」。まず、マネーマネジメントの中心概念としてリスク・リワード・レシオ(損失に対してどれくらいの利益が見込めるかの比率)が解説され、1回のトレードで許容する損失額をあらかじめ設定する重要性が強調されます。
また、同時に保有するポジションの種類や数量を分散させる「多元化」のアプローチや、勝ち続けている時・連敗している時の心理とその対処法にも踏み込んでいます。さらに、成行・指値・逆指値など注文の種類、日中足チャートの活用、日中ピボットポイントを用いたデイトレード戦術など、現場で即使える技術も豊富です。
株式・投資信託・アセットアロケーション戦略など、投資対象を問わない応用法も提示されており、戦略から実践への橋渡しとして本章は非常に実用性が高い内容になっています。

マネーマネジメントは“生き残るための武器”。
トレード技術と同じくらい、資金を守るスキルが重要です。
第17章 株式と先物の関連性―市場間分析
本章では、個別市場だけを見るのではなく、「市場同士の相関関係」から相場の大局を読み解く「市場間分析(インターマーケットアナリシス)」という高度な技法を扱います。著者ジョン・J・マーフィーが先駆者として広めた手法であり、異なる市場の動向を組み合わせて投資判断に活かします。
たとえば、株式と債券、商品市場と通貨(特に米ドル)、金利とコモディティなど、相互に連動しやすい市場の関係性を分析することで、ある市場の動きが別の市場の先行指標となることがあります。たとえば「債券利回りが上昇すると株式市場が下落する」といった関係は、よく知られる例です。
セクター分析、相対力指数(RS)、トップダウンアプローチなども本章に含まれ、マクロ的な視点からのアプローチを学ぶことができます。特に、資金の流れがどこからどこへ移動しているのかを読むことは、現代のグローバル市場では不可欠な視点です。

市場間分析は“相場の相関地図を描く技術”。
一つの市場だけに固執しないことで、見えてくるチャンスがあります。
第18章 株式市場の指標
ここでは、個別銘柄ではなく「市場全体の健康状態」を把握するための「内部指標(マーケットブレドゥス)」を中心に取り上げています。値上がり・値下がり銘柄数、新高値・新安値、出来高、騰落ラインなど、市場の内部構造を把握するのに役立つ指標が解説されます。
たとえば、日経平均株価が上昇しているのに騰落ラインが下降している場合は、「見かけ上の上昇」であり、市場の実体は弱い可能性があると判断できます。これは、大型株だけが上昇し、中小型株は売られているなど、市場の偏りを示す警告信号となります。
また、マクレランオシレーターやアームズインデックス(TRIN)といった専門的な指標も、初心者にも理解できるように平易に解説されており、実際にチャートでどう活用すればよいのかが分かる構成になっています。特に、センチメント分析と組み合わせたときの精度向上は大きな魅力です。

市場内部のデータは“相場のバイタルサイン”。
価格だけでは分からない本当の体調を知る手がかりになります。
第19章 要点整理―チェックリスト
本書の最後の章では、これまでに学んできた知識を実際のトレードに応用するための「チェックリスト」として総復習が行われています。トレードの前に確認すべき項目、戦略の組み立て方、リスクの見積もり方などが体系的に整理されており、初心者にも非常に有用です。
また、公認テクニカルアナリスト(CMT)の資格や、テクニシャン・アソシエーションといった国際的な団体についても紹介されており、本格的にこの分野を学びたい読者にとっての道しるべとなる情報が提供されています。
さらに、FRB(米連邦準備制度理事会)がテクニカル分析を公的に調査対象として取り上げた例など、分析手法としての信頼性や国際的な評価についても触れられています。これはテクニカル分析が単なる“占い”ではなく、実務的にも裏付けられたスキルであることを証明しています。

チェックリストは“実戦への羅針盤”。
すべての理論と技術は、実行に移して初めて価値を持ちます。
付録A 上級テクニカル指標
この付録では、テクニカル分析をより高度な次元に引き上げるための専門的な指標群が紹介されています。ここに登場する指標は、一般的な移動平均やRSIとは異なり、トレンドの強弱や価格帯のバランスを繊細に捉えるものです。
たとえば、「DI(Directional Indicator)」は、トレンドの方向性とその強さを示す指標で、トレンドフォロー戦略の基本として知られる「ADX」と組み合わせて使われます。「HPI(Horizontal Price Index)」は、価格の横方向への動きを数値化し、ボックス相場(横ばいの相場)での動きの分析に役立ちます。
さらに、「STARCバンド」や「ケルトナーチャネル」といったバンド系の指標も紹介されています。これらは価格の標準的な変動幅を視覚的に捉えるためのツールで、ボリンジャーバンドとは異なる計算方法を用いるため、異なる視点からの分析が可能になります。

基本指標に慣れたら、こうした“職人ツール”に挑戦。
相場の“微細な息づかい”を読み取れるようになります。
付録B マーケットプロファイル
マーケットプロファイルは、単なる価格と時間の情報ではなく、「市場参加者の心理」と「価格帯ごとの取引ボリューム」をグラフィカルに示す分析手法です。日々の値動きをアルファベットの記号(TPO)で表し、価格の“滞留時間”を可視化するのが特徴です。
この手法の最大の魅力は、“どこで多くの取引が行われたか”という「市場の関心ゾーン(バリューエリア)」を直感的に把握できる点です。従来のローソク足チャートでは見えにくかった「価格帯の厚み」を視覚的に理解できることで、サポート・レジスタンスの信頼性も高まります。
マーケットストラクチャー(構造)、プロファイルの形状分類(ノーマル、P字型、b字型など)、値幅の広がりやプロファイルパターンの特徴などが整理されており、特に短期売買において効果的な情報をもたらします。

マーケットプロファイルは“市場心理の地図”。
価格ではなく“熱量”を見るという視点を手に入れましょう。
付録C トレードシステム構築の要点
この付録では、完全自動化あるいは半自動化された「トレードシステム」の構築方法が、5つのステップで体系的に紹介されています。裁量ではなくルールベースで取引するための設計図とも言える内容です。
ステップ1では、まずトレードにおける「アイデア」を明確化することから始まります。「移動平均のゴールデンクロスで買い」などの仮説を立て、それをもとに、ステップ2では客観的なエントリー・エグジットルールに落とし込みます。
次に、ステップ3でチャート上でルールを視覚的に検証(バックテストの前段階)、ステップ4では実際にプログラム化して過去データで検証(シミュレーション)を行います。そして、最終的にステップ5で検証結果を分析し、改良・採用を判断します。
この付録は、エンジニア志向のトレーダーや、システムトレードを目指す人にとって、実践的な設計手順を学べる貴重なガイドとなっています。

感情を排した“ルールトレード”は再現性が命。
検証→改良→再検証の繰り返しが、勝率を底上げします。
付録D つなぎ足
最後の付録では、先物取引において不可欠な「つなぎ足(continuous chart)」の作成方法と、その活用法が説明されています。つなぎ足とは、限月ごとに異なる先物契約を連続して1本のチャートとしてつなぎ合わせたものです。
先物取引は満期(限月)で清算されるため、通常のチャートでは期間ごとに価格のギャップが発生します。このギャップを除去して長期的な価格推移を滑らかに表示するために用いられるのがつなぎ足です。
この付録では、「期近限月足」「2番限足」「ギャン・コントラクト」「期間固定つなぎ足」など、複数のつなぎ方の種類が紹介されており、それぞれのメリット・デメリットが丁寧に比較されています。
たとえば、期近限月をベースにしたつなぎ足は、流動性の高い最新の動きに敏感である一方、価格ギャップが頻繁に発生するリスクがあります。逆に、期間固定型は安定感があるが、タイミングのズレが生じる場合もあります。

先物の分析には“つなぎ足”が不可欠。
連続性があるからこそ、本当のトレンドが見えてくるのです。
対象読者

この本は「テクニカル分析に関心のあるすべての人」に向けて書かれていますが、その中でも特に次のような読者層に大きな価値を提供します。
自分がどのタイプに当てはまるのかを意識しながら読み進めることで、より深く本書の内容を活用できるでしょう。
- テクニカル分析を本格的に学びたい投資初心者
- トレードの勝率を上げたい中級トレーダー
- 株式・FX・先物を横断的に理解したい投資家
- プロのテクニカルアナリストを目指す人
- チャートの理論を深く理解したいプログラムトレーダー
それぞれの対象読者に向けて、本書がどのような価値をもたらすか、以下で詳しく解説していきます。
テクニカル分析を本格的に学びたい投資初心者
投資に初めて触れる人にとって、チャートの線や指標はまるで異国の言語のように見えるかもしれません。本書は、そんな「わからない」が「なるほど」に変わる入り口を提供してくれる存在です。なぜ価格は動くのか、ローソク足の形にはどんな意味があるのか、サポートラインとレジスタンスラインはどのように機能するのか。これらの疑問を、400枚以上の豊富なチャートと明快な解説で丁寧に紐解いてくれます。
難しい専門用語が出てきても、言葉の意味だけでなく、なぜそれが重要なのか、どのように実際の取引に役立つのかまで説明されており、「理解できた」と実感しながら読み進められる構成です。まさに、投資のリテラシーを一から学びたい人にとっての最良の“教科書”です。

トレードの勝率を上げたい中級トレーダー
すでに投資経験があり、日々の売買に取り組んでいる中級トレーダーにとっての課題は、「勝ったり負けたりが続いて安定しない」「なんとなくチャートを見ているだけになっている」といった悩みです。本書は、そうした読者に確固たるトレード戦略と理論的裏付けを与えてくれます。
RSIやMACD、ボリンジャーバンドといった定番のテクニカル指標をただ紹介するだけでなく、どう組み合わせれば相場の強弱を読み取れるか、どんな相場状況に向いているかといった“使いこなし方”に踏み込んで解説してくれる点が非常に実践的です。また、継続パターンや反転パターンのチャート分析は、エントリーとイグジットの判断に直結するため、トレードの精度を上げるうえで大きな武器となります。

株式・FX・先物を横断的に理解したい投資家
現代の投資家は、株式市場だけでなく、為替(FX)や商品先物、さらには指数やETFといった多様な市場にアクセスできる環境にあります。しかし、それぞれの市場の構造や動きのクセを知らないままテクニカル分析を行っても、思わぬ誤解や失敗を招くことがあります。
本書はもともと先物市場をベースに構成された内容を、株式・金利・通貨など広範なマーケットに対応させる形で進化しています。市場ごとの特性を踏まえた分析のポイントや、市場間の関連性(たとえば、ドルと金価格、株と債券の関係など)も解説されており、マクロな視点で相場全体を読み解く力を養うことができます。

プロのテクニカルアナリストを目指す人
本書は米国のCMT(Chartered Market Technician)など、公認テクニカルアナリスト資格の試験対策にも使われているほどの信頼性を誇る一冊です。テクニカル分析の哲学からスタートし、ダウ理論、エリオット波動、サイクル分析、さらにはマーケットプロファイルといった高度な分析手法に至るまで、学術的な水準で網羅されています。
各理論の歴史的背景や考案者の意図、計算式の意味など、単なるノウハウ本とは一線を画す奥行きのある解説が特徴で、読者は分析の「なぜそうなるのか」に納得しながら学べます。将来、分析を職業にしたいと考えている人や、クライアントへの説明責任が求められるような立場の方には、必携の資料と言えるでしょう。

チャートの理論を深く理解したいプログラムトレーダー
テクニカル指標を使った自動売買(アルゴリズムトレード)や、戦略構築を行うプログラムトレーダーにとって、本書はコードを書く前に読むべき一冊です。なぜなら、単に「数字の条件」を満たすだけで勝てるわけではなく、その指標が何を前提としているかを理解しなければ、機械的な戦略がすぐに破綻してしまうからです。
本書には、DI、HPI、STARCバンド、ケルトナーチャネルなどの応用的な指標の理論背景と使用条件がしっかり解説されています。さらに、トレードシステムを構築する際のフロー(発想・ルール化・バックテスト・評価)まで丁寧に指南されており、戦略の開発から運用までを一貫してサポートしてくれます。

本の感想・レビュー

この本があれば他はいらない
テクニカル分析の本はこれまでにも10冊以上読んできましたが、どれも一長一短で「この1冊にすべてがまとまっている」と思えるような本にはなかなか出会えませんでした。入門書は基礎知識しか載っておらず、応用書はそれなりに深いけれども体系的ではない。そんな中でこの本に出会い、まさに「すべてがここにある」と感じました。
内容の網羅性は圧巻です。分析の哲学から始まり、チャートの種類、トレンドやパターン分析、そして高度な指標やトレード戦略、さらにはマネーマネジメントに至るまで、テクニカル分析に関わるすべての要素が順序立てて解説されています。
なかでも素晴らしいのは、各章の論理構成とチャートの豊富さ。単に知識を羅列するだけでなく、初心者が躓きやすいポイントを押さえ、図解を交えながら丁寧に説明してくれるので、読むたびに「なるほど」と納得できます。これだけの質と量を兼ね備えた本は他に知りません。今では、何か分からなくなったときは、まずこの本を開くのが習慣になっています。
本格的にトレードで稼ぎたい人の必読書
私は数年前から兼業トレーダーとして活動していますが、なかなか安定的な利益が出せず、自分の手法にどこか曖昧さがあることを感じていました。いろいろと情報を漁るうちに、SNSで「テクニカル分析のバイブル」と呼ばれるこの本の存在を知り、迷わず購入しました。
最初に読み始めたときは、その情報量に圧倒されました。しかし、読み進めるうちに感じたのは、この本が単なる知識の詰め込みではなく、「どう実戦に落とし込むか」という実用面に重点を置いているということです。特にトレンド分析や価格パターンの見極めに関する章は、自分の裁量判断を確かな根拠で支えてくれる内容でした。
それまで私は、感覚的なエントリーを繰り返し、失敗すればその原因が分からないまま放置していたのですが、この本のおかげで「なぜそのタイミングだったのか」「どう改善すべきか」を自分で検証できるようになりました。本気でトレードで収益を上げたいなら、この書籍を無視するわけにはいきません。基礎から応用までが一貫してつながっているので、何度読んでも発見があります。
チャートを読む力が格段に上がる
投資歴はそれなりに長いのですが、テクニカル分析の理解にはずっと自信がありませんでした。チャートは見ているけれど、「なんとなく上がりそう」「ここで反転しそう」といった曖昧な判断を繰り返していたんです。でも、この本を読んでから、そんな直感頼みの姿勢がガラリと変わりました。
チャートパターンやトレンドラインの引き方、ローソク足の意味など、一見すると当たり前に思えることでも、その背景にある原理や相場心理を丁寧に解説してくれているので、単なる「形の暗記」ではなく「なぜそう動くのか」が明確になります。おかげで、自分の分析に自信が持てるようになり、実際にトレードの質も向上しました。
特に印象的だったのは、チャートを複数の時間軸で見る重要性や、トレンドの持続性を見極めるための複合的な分析手法の紹介です。これを意識するようになってから、無駄なトレードが減り、利益の安定感が増してきました。
マネーマネジメントの項も実用的
トレードで一番大切なのは「資金管理」とはよく聞きますが、具体的に何をどう管理すればよいのか分からないまま、ずるずると損失を重ねる日々が続いていました。そんな中で出会ったこの本のマネーマネジメント章は、私にとってまさに転機となりました。
まず、損失を前提にした戦略の立て方がとてもリアルです。たとえば「どの程度のドローダウンを許容するか」「どこで損切りするべきか」といった、現実的なトレードの中で迷いやすいポイントについて、理論と実例を交えながら説明されています。特にリスク・リワード・レシオの重要性や、ポジションサイズの調整法は、これまで意識すらしていなかった自分を恥じるほどでした。
実際に、本の内容を取り入れてトレードを見直した結果、損失の幅が狭まり、心理的にも冷静さを保てるようになったのを実感しています。「勝つ」こと以上に「負けない」ことの大切さを教えてくれた、非常に現実的で実用性の高い内容でした。
市場のつながりが理解できるようになった
私はこれまで、チャート分析といえば「その銘柄単体の値動きを読む」ことだと思っていました。しかし、本書を読んでから、市場というのは相互に強く関係しているということを初めて意識するようになりました。第17章の「市場間分析」は、その理解を深めてくれる格好の教材です。
たとえば、株式市場と金利市場、あるいは為替とコモディティの相関関係について、各市場がどのように影響し合いながら動いているかを、視覚的なチャートとともに解説してくれています。これにより、ひとつのマーケットだけを見て判断することの危うさや、より広い視野での分析の必要性に気づかされました。
この知識を得てからは、ニュースの見方やファンダメンタルズの捉え方にも深みが出てきたように感じます。単なる「株の値動き」を追うのではなく、全体の流れの中で自分がどこに立っているのかを把握できるようになったことで、戦略の組み立てもより理にかなったものになりました。
勉強して実際に成果が出た
正直に言えば、最初は分厚すぎて挫折しかけました。でも、「これを読み切れば、きっと何かが変わる」と信じて、毎日少しずつ読み進めました。結果的に、この本との出会いが私の投資スタイルを180度変えてくれたんです。
最初に変わったのは、自分のトレードに対する向き合い方。感覚ではなく、論理的に「なぜそう動くのか」「どう対応すべきか」を言語化できるようになりました。それまでは勝ったり負けたりの繰り返しで、安定した成果には程遠い状態でしたが、本書を通して学んだテクニカル分析の基礎と応用を繰り返し実践することで、トータルの収益が徐々にプラスへと転じていったのです。
とくに、移動平均やオシレーターの部分は繰り返し読み込みました。チャートの中で何が起こっているのかを冷静に分析できるようになり、過剰な売買も減りました。本を読んで、勉強し、それを実践し、結果が出る——その経験は、自分にとって大きな自信となっています。
プロのトレーダーも参考にするレベル
私は機関投資家向けのディーラーとして10年以上のキャリアがあります。これまで数多くの投資書籍に目を通してきましたが、本書ほど内容が洗練され、かつ深度と網羅性のバランスを保っているものは稀です。現場で即使える知見が豊富で、むしろプロこそ読むべき一冊だと感じました。
特筆すべきは、チャート分析を表面的な形状の話で終わらせていない点です。背景にある市場心理や需給の力学を丁寧に描いており、形だけを真似しても意味がないということを、本質的に理解させてくれます。また、ローソク足のセクションにしても、単なるパターンの紹介にとどまらず、どのような状況でどのように解釈すべきかといった判断の文脈が明確です。
さらに、相場のダイナミクスを多角的に捉えるための上級指標やマーケットプロファイルの記述も、深みがあり非常に参考になりました。この本は、プロフェッショナルの現場でも通用する分析フレームの基礎体力を養ってくれる稀有な存在です。
長く手元に置きたい「辞書」的存在
私は普段から複数のトレード本をデスク脇に置いて必要なときに開くタイプですが、最近ではこの1冊ばかり手に取っています。それほどまでに信頼できる内容であり、まさに「チャート分析の百科事典」といえる一冊です。
どのページを開いても、深く体系化された解説と豊富な図表が目に入ります。特に、パターン分析やトレンド分析の章は、実際のチャートに応用する際の判断材料としてとても役立っています。必要なときに、必要な知識を、すぐに引き出せる。それがこの本の最大の強みだと思います。
書かれていることは決して「簡単なトレードテクニック」ではありません。むしろ、原理原則に基づいた思考法であり、読むたびに新たな発見があります。一度読み終えても終わりではなく、何年も付き合っていける信頼の一冊です。
まとめ

この書籍は、単なる知識の詰め込みではなく、テクニカル分析という手法を実践的に活用できるようになることを目的としています。そのために、本章では読者がこの本から得られる価値や今後の活用法、そして最終的な位置づけを整理していきます。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれの内容を確認することで、読了後にどのような行動をとるべきか、そしてこの一冊の意味を明確にできます。
この本を読んで得られるメリット
投資やトレードの世界では、ただチャートを眺めるだけでは勝つことはできません。何を見て、どう判断するかという「分析力」こそが差を生みます。本書『マーケットのテクニカル分析』は、その分析力を養うための体系的な知識と実践的な視点を与えてくれる、非常に貴重な一冊です。
以下では、本書を読むことで得られる主なメリットを、より具体的にご紹介します。
テクニカル分析の体系が一気通貫で理解できる
本書の最大の特長は、テクニカル分析の全体像を「断片的」ではなく「体系的」に学べる点です。多くの入門書が特定のインジケーターやチャートパターンだけに焦点を当てるのに対し、本書は価格の動き、出来高、トレンド、チャート形状、サイクル理論、市場心理といった多岐にわたる視点を網羅しています。そのため、単なる知識の寄せ集めに終わらず、各要素の意味や関連性が自然と理解できるよう構成されています。
実践的なチャートの読み方が身につく
理論を知るだけでは、相場では通用しません。本書には400以上のチャート事例が掲載されており、リアルな相場でどのように分析を行い、どのように売買判断を下すのかを視覚的に理解できます。これにより、読者は「パターンを見つけて意味を読み取る力」を養うことができ、自分自身の目でマーケットの転換点やトレンドの継続を判断できるようになります。
幅広いマーケットに対応できる応用力がつく
本書は、もともと先物市場を対象にしていた前著を改訂し、株式、FX、金利、指数など多様な金融商品に対応できるよう内容が拡張されています。このため、どの市場に取り組む投資家にとっても、応用可能な知識と手法が得られます。特に市場間の相関関係やクロスマーケット的な視点は、現代の分散投資やリスク管理を考えるうえで不可欠な要素です。
トレード戦略構築の基礎が整う
移動平均やオシレーターなどの指標に加え、資金管理やリスクコントロールについても丁寧に扱われているため、「分析だけでなく、戦略としての全体像」が掴めます。テクニカル分析を実際の売買行動につなげる際に何が必要か、どのように判断基準を定めるべきかなど、戦術面でも多くのヒントを得られるはずです。
自分なりの投資手法を確立するための道しるべになる
最後に、本書は読者に対して「唯一絶対の正解」を押し付けるものではありません。さまざまな分析手法やアプローチを紹介した上で、それぞれのトレーダーが自分に合ったスタイルを見つけられるよう促してくれます。複数のアプローチを比較し、自分の性格や目的に合った戦略を選択・検証するプロセスを支援してくれる点でも、この本は非常に実用的です。

テクニカル分析は「知識」と「視点」と「経験」の三位一体で成り立つ。本書はそのすべてを段階的に学べる、数少ない包括的なガイドブックです。
独学では到達しにくい“判断力”のレベルに、最短距離で近づける構成になっています。
読後の次のステップ
本書『マーケットのテクニカル分析』を読了することで、あなたは分析手法や市場の構造に関する深い知識を手に入れることになります。しかし、知識は使ってこそ意味があるものです。学んだ理論や技術を実戦に落とし込むことで、初めて“自分の技術”として定着します。
以下では、読了後にどのようなアクションを取るべきかを順を追ってご説明します。
step
1自分のトレードスタイルを定義する
読了後の第一歩として、自分がどのようなトレーダーになりたいかを明確にしましょう。長期保有を基本とするスイングトレードを目指すのか、短期で売買を繰り返すデイトレーダーになるのか、それとも中長期のファンダメンタルズと組み合わせてテクニカルを補助的に使いたいのか。どのスタイルを選ぶかによって、活用すべきチャートの時間軸や指標が変わります。まずは本書で得た知識の中から、自分にフィットする戦略を見極める作業が重要です。
step
2チャートを見ながらアウトプットする
次に行うべきは、「知識を知識のままで終わらせない」ことです。本書に登場するパターンやインジケーターを、実際のチャート上で検証してみましょう。現在の相場はもちろん、過去のデータをさかのぼって「このポイントでどのようなパターンが現れたか」「指標はどう反応したか」を確認することが、理解を深めるうえで非常に効果的です。ノートやブログなどに自分なりの分析記録を残すと、後々の成長にもつながります。
step
3少額からリアルトレードを開始する
理論と検証の段階を終えたら、いよいよ実際のマーケットに挑戦する段階です。ただし、最初から大きな資金を投入するのではなく、少額でいいのでリアルマネーでのトレードを始めましょう。デモトレードと異なり、実際の資金を使ったトレードは心理面に大きく影響します。恐怖や欲望といった感情がどう行動に現れるかを体験しながら、本書で学んだリスク管理の技術を活かすチャンスでもあります。
step
4分析結果をもとに検証と改善を繰り返す
一度トレードを始めたら終わりではなく、そこからが本当の意味での「学習の始まり」です。トレードごとの記録を残し、自分の判断がどこで正しく、どこで間違っていたのかを冷静に振り返りましょう。勝ち負けだけを見るのではなく、「なぜその判断をしたのか」「本書の知識とどう違ったか」といった視点で分析することが、トレーダーとしての成長を大きく促してくれます。

知識を「知っている」だけで終わらせず、「使える」レベルに昇華するには、検証→実践→記録→改善のサイクルが欠かせません。
書籍を読み終えた後が、本当の学びのスタート地点です。
総括
『マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド』は、単なるチャート解説書ではありません。これは、トレードに必要な知識とスキルを体系的に積み上げるための、いわば「一冊で学ぶ専門学校」のような存在です。本書の特長は、圧倒的なボリュームと実用性にあります。数百に及ぶチャートと、実践的な事例解説によって、読者は抽象的な理論にとどまらず、現実の市場でそれをどう活かすかを学ぶことができます。
テクニカル分析というと、多くの初心者は「難しいグラフを読むスキル」や「一部の専門家だけの知識」といった印象を抱きがちです。しかし本書は、そうしたハードルを一つひとつ丁寧に取り払い、理論の背景から応用までを順を追って説明しています。特にトレンド、パターン認識、オシレーター、出来高の読み方などは、初学者にとって最初の関門となる部分ですが、本書では実際の相場データを使って視覚的に学べるため、理解が格段に進みます。
また、著者であるジョン・J・マーフィーの視点が非常に興味深いのは、テクニカル分析を単なる売買のタイミング測定ツールとしてだけでなく、「市場の心理を読み解く方法」として提示している点です。これは、技術的な分析を人間の行動パターンと結びつけることで、より精度の高い予測を可能にするという、長年の実践から得られた知見と言えるでしょう。
そして何よりも重要なのは、この本が「終わりではなく始まり」を意識して書かれていることです。読者は本書を読むことで、マーケットをどう見るか、何を信じるか、どのようにリスクを管理するかといった、投資家としての土台を築くことができます。そのうえで、自分のスタイルに合わせたトレード戦略を模索するフェーズに自然と移行できる構成になっているのです。

投資の世界において成功する人とそうでない人の違いは、情報の量ではなく「情報をどう使うか」にあります。
『マーケットのテクニカル分析』は、そうした意味で、情報の使い方を学ぶための「実戦型の教科書」として、初心者から上級者まで幅広い層にとっての必読書です。
今後、チャートに向き合うすべての瞬間に、この一冊が背中を支えてくれる存在となるでしょう。
テクニカル分析の勉強におすすめ書籍

テクニカル分析の勉強におすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- テクニカル分析の勉強におすすめの本!人気ランキング
- マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド
- 日本テクニカル分析大全
- 手法作りに必要な“考え”がわかる データ検証で「成績」を証明 株式投資のテクニカル分析
- 真・チャート分析大全 ──王道のテクニカル&中間波動編
- 勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2
- テクニカル分析 最強の組み合わせ術
- ずっと使えるFXチャート分析の基本 (シンプルなテクニカル分析による売買ポイントの見つけ方)

