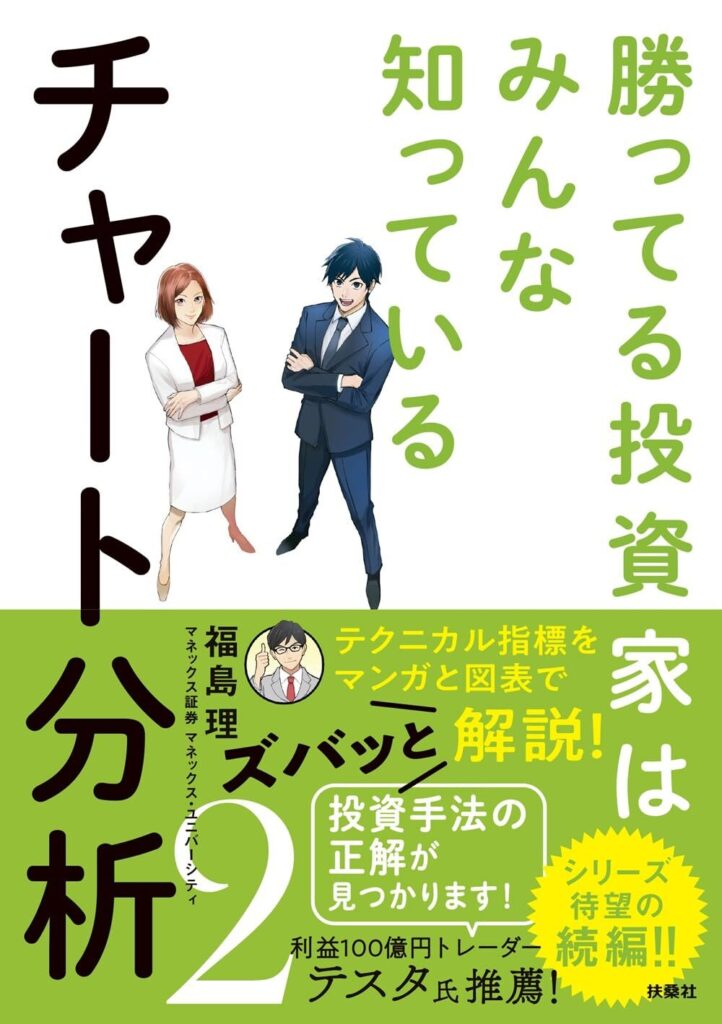
「株やFXを始めてみたけれど、何を基準に売買すればいいのか分からない」――そんな悩みを抱える投資家にとって、チャート分析は“投資の地図”となる技術です。
『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2』は、テクニカル分析の入門書として多くの読者に支持された前作の続編。今回は、DMIやパラボリック、RCI、移動平均乖離率など、より実践的かつ応用的な指標を中心に、投資判断をより深く、正確にするための知識が網羅されています。

カリスマトレーダー・テスタ氏の推薦にも裏付けられた信頼性の高い内容で、チャートが読めるようになるだけでなく、“使いこなせる”ようになる一冊。
投資初心者の方にも分かりやすい図解とマンガで構成されており、経験者にとっても分析手法の見直しやスキルアップに役立つ内容が満載です。

合わせて読みたい記事
-

-
テクニカル分析の勉強におすすめの本 7選!人気ランキング【2026年】
株式投資やFX、仮想通貨など、あらゆる金融商品のトレードにおいて重要なスキルのひとつが「テクニカル分析」です。チャートの動きから相場のトレンドや売買のタイミングを見極める力は、初心者から上級者まで、す ...
続きを見る
書籍『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2』の書評

投資において「チャート分析」は、単なる価格のグラフを見る技術ではありません。それは、投資家心理を読み解き、相場の“波”に乗るための羅針盤です。本書『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2』は、そんなチャート分析を「本気で使える武器」に変えるために書かれた一冊です。
この書評では、以下の視点から解説して。
- 著者:福島 理のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれ詳しく見ていきましょう。
著者:福島 理のプロフィール
福島 理(ふくしま ただし)氏は、1974年生まれの投資教育の第一人者であり、現在はマネックス証券の教育部門「マネックス・ユニバーシティ」の室長として活躍しています。もともとは理系出身で、大学卒業後は大手機械メーカーに入社。技術職として働いていた彼は、2000年のITバブル崩壊をきっかけに資産運用の必要性を痛感し、独学で投資の勉強を始めました。
その中で出会ったのが「チャート分析」でした。金融商品の価格変動には人の心理が反映されるという事実に衝撃を受け、以後テクニカル分析を徹底的に学習。トレード経験を積む中で「知識」だけではなく「再現性のある行動原則」の重要性を痛感し、分析と実践を往復しながら理論を磨いてきました。
その後、証券会社に転職し、個人投資家向けの教育に従事。現在ではセミナー講師、書籍執筆、YouTube解説などを通じて、万人に理解できる「テクニカル分析の民主化」を掲げて活動を続けています。彼は日本テクニカルアナリスト協会の国際認定資格「CFTe(Certified Financial Technician)」も保持しており、その専門性は国内外で証明済みです。

本書の要約
『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2』は、タイトル通り「勝っている」個人投資家たちが実際に使っているチャート分析手法を、より実践的・戦略的に学べる続編です。本書では、第一弾で扱ったローソク足や移動平均線などの基本的なテクニカル指標にとどまらず、DMI(Directional Movement Index)、パラボリック、RCI、移動平均乖離率、酒田五法、サイコロジカルラインといった、やや高度な分析手法が登場します。
これらの指標は、単体で使っても効果はありますが、本書ではそれらを組み合わせて使う方法、つまり「シグナルの質を高めるための融合的なテクニカル分析」の考え方が中心に据えられています。ただ指標を学ぶのではなく、「どう活用するのか」に踏み込んでいるのが本書の大きな特徴です。
また、各章の冒頭には実生活に置き換えたマンガが用意されており、指標の概念を感覚的に理解しやすく工夫されています。読者はマンガでテーマを直感的に把握した上で、本文の解説を読むことで、理論と実践の橋渡しをスムーズに行えるようになっています。

本書の目的
この書籍の根幹にあるのは、「投資判断に迷わない力を育てる」という明確な目的です。マーケットの変動には、経済指標や企業業績だけではなく、投資家の心理や集団行動といった“目に見えない要素”も大きく影響します。そうした複雑な相場の中で、自信を持って判断を下せるようになるためには、複数のテクニカル指標を適切に使い分け、状況に応じて組み合わせていく判断力が必要になります。
著者は、相場に「これだけで勝てる」という魔法のような手法が存在しないことを明言し、だからこそ「複数の視点を持つこと」「それらを自分のスタイルに落とし込むこと」が重要だと説いています。本書に登場する指標は、トレンドの有無や強さを示すもの、買われすぎ・売られすぎを示すもの、投資家の感情に焦点を当てたものなど、それぞれ性質が異なります。これらを通して、読者は「相場の空気を読む目」を養うことができます。
つまり本書の目的は、テクニカル分析を知識として学ぶだけでなく、「生きた判断力」として身につけること。そのために必要な知識・視点・考え方が、実例を交えてわかりやすく構築されているのです。

人気の理由と魅力
本書が多くの読者から支持されているのは、単に情報量が豊富だからではありません。その最大の魅力は、「わかる」から「できる」に自然と進めるように設計されている点にあります。テクニカル分析は、多くの入門書で語られているものの、「現実の相場でどう使うのか」まで踏み込んだ解説は案外少ないのが実情です。その点で、本書は完全に実践重視。チャートの一部分を切り取ったような例ではなく、現実の相場の流れに即した形で解説されており、「机上の空論ではない」信頼感があります。
また、各章のはじめに用意されたストーリーマンガも高く評価されています。難解になりがちな投資理論を、身近な生活や行動と重ね合わせることで、視覚的・感覚的に理解できる構成は、初心者にとって大きな助けになります。そして、用語集やQ&Aページが巻末に用意されていることで、途中で疑問にぶつかってもすぐに調べられるという安心感もあり、読み進めやすさにも配慮された内容です。
さらに、著名なトレーダーであるテスタ氏の推薦も、本書の信頼性を裏付けています。テスタ氏は100億円を超える利益を挙げた実績を持つカリスマトレーダーであり、彼の「この本で勉強すれば、自分なりの正解が見つかる」というコメントは、多くの投資家にとって心強い後押しとなっています。

本の内容(目次)

『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2』は、チャートを“読む”だけでなく“使いこなす”力を身につけるために構成された、極めて実践的な学習書です。その内容は段階的かつ網羅的に構成されており、読者が確実にレベルアップできる仕組みになっています。
以下の10章構成を通じて、テクニカル指標の使い方だけでなく、組み合わせ方や投資家心理との関係までも深く理解できます。
- 第1章 チャート分析の種類と魅力
- 第2章 DMI
- 第3章 パラボリック
- 第4章 RCI
- 第5章 移動平均乖離率
- 第6章 サイコロジカルライン
- 第7章 酒田五法
- 第8章 テクニカル指標の組み合わせで勝率UP!
- 第9章 ファンダメンタルズ分析にも役割が!
- 第10章 チャート分析 Q&A
それぞれの章は独立して学べる構成であり、読者が自分の課題や疑問に応じて柔軟に読み進められるようになっています。
第1章 チャート分析の種類と魅力
この章では、チャート分析の基本的な分類と、それぞれが投資判断に与える影響を解説しています。特に焦点が当てられているのが「トレンド相場」と「レンジ相場」の違いです。トレンド相場とは、価格が一方向(上昇または下降)に動いている状態で、レンジ相場はある一定の価格帯の中で上下している状態を指します。
ここで重要なのは、どちらの相場にも適した分析方法があるということです。例えば、トレンド相場には「トレンド系」の指標、レンジ相場には「オシレーター系」の指標が効果的とされています。このような相場環境の違いを理解せずに指標を使うと、間違った判断をしてしまう危険性があるのです。
また、どのテクニカル指標が人気なのか、実際の投資家が何を使っているのかという情報もあり、現場感覚を養うのにも役立ちます。これから本書で紹介される分析手法を学ぶ前に、全体像を把握するための土台作りとして、この章は非常に重要です。

第2章 DMI
DMI(Directional Movement Index)は、「トレンドがあるかどうか」「その強さはどれほどか」を数値で示してくれる指標です。相場にトレンドが存在するかを見極めることは、最も基本的かつ重要な判断材料の一つですが、初心者にとっては抽象的で難しく感じられる部分でもあります。そこでDMIが活躍します。
この指標は、「+DI(プラスDI)」「−DI(マイナスDI)」「ADX(Average Directional Index)」という3本の線で構成され、それぞれが異なる情報を提供します。+DIが上昇圧力、−DIが下降圧力、そしてADXがトレンドの強さを示します。特にADXは、売買の“勢い”を測るのに非常に有効で、だましのサイン(誤った売買シグナル)を回避するためにも役立ちます。
具体的な活用としては、+DIが−DIを上回り、かつADXが上昇しているときが「買いシグナル」となります。これにより、感覚や勘ではなく、客観的なデータに基づいた売買判断が可能になります。

第3章 パラボリック
パラボリックは、価格の転換点(トレンドの終わりと始まり)を見極めるのに特化した指標です。特徴的なのは、チャート上にドット(点)として表示され、価格の上や下に現れることで売買シグナルを視覚的に伝えてくれる点です。たとえば、価格の下にドットがあれば「買い」、上にあれば「売り」という判断ができます。
この指標のもう一つの大きな特徴は「ドテン売買」と呼ばれる、ポジションの切り替えを促すシグナルを出すことです。すなわち、上昇が終わりそうになったら売りに、下降が終わりそうになったら買いに転じるタイミングを明示してくれるのです。
ただし、パラボリックには弱点もあります。それは「レンジ相場」に弱いという点です。方向性がない相場では頻繁に売買シグナルが出てしまい、結果的に損失が増えるリスクがあります。そのため、他のトレンド系指標と組み合わせて使うことが推奨されます。

第4章 RCI
RCI(Rank Correlation Index)は、一定期間の価格の動きと時間の流れを順位付けして、その相関関係から売られ過ぎ・買われ過ぎを判断する逆張り系の指標です。価格が上がり続けるとRCIの値は+100%に、下がり続けると-100%に近づきます。
この指標の最大の特徴は、時間という“目に見えない要素”を分析に取り込むこと。短期と長期のRCIを同時に見ることで、短期的な過熱感と中長期のトレンドとのズレを察知できるのです。
また、「±80%ラインを超えたら反転の兆し」といった具体的な目安が示されているため、初心者でもエントリーポイントのイメージがしやすい構成になっています。

第5章 移動平均乖離率
移動平均乖離率は、現在の価格が移動平均線からどれだけ離れているか(乖離しているか)をパーセンテージで示す指標です。価格が移動平均から大きく上に乖離していると「買われ過ぎ」、大きく下に乖離していると「売られ過ぎ」と判断されます。
この乖離率を利用することで、「今の価格が異常な水準にあるかどうか」を判断でき、特に逆張りのタイミングを計る際に有効です。たとえば、過去のチャートを検証して「この銘柄は5%以上乖離すると反転しやすい」といった“クセ”を見つければ、投資判断の精度を高めることができます。
ただし、値動きが小さい相場ではシグナルが出にくくなることもあるため、トレンド系指標との併用がおすすめです。

第6章 サイコロジカルライン
第6章では、投資家心理の強弱を数値化し、視覚的に把握するための「サイコロジカルライン」が取り上げられています。この指標は、一定期間のうちで上昇した日数の割合から「買われすぎ」や「売られすぎ」といった状況を判断するオシレーター系指標です。
内容説明によれば、本書ではこのサイコロジカルラインを使って、トレンドの転換点を一目で把握するための実践的な使い方が紹介されており、銘柄や相場環境に合わせて「自分で適切な値を設定する」ことの重要性にも言及されています。
また、目次の記述から、心理的なバイアスがチャートにどう表れるかという観点も取り上げられており、読者が感覚だけに頼らず、数値で心理を分析する視点を得る構成になっていることが分かります。

第7章 酒田五法
酒田五法は、日本のローソク足分析の原点とされる伝統的な手法で、本間宗久によって体系化されたとされています。この章では、五法の概要と基本的な考え方、代表的なローソク足のパターンが紹介されています。
三川、三山、三空などのパターンにより、相場の反転や継続の兆しを読み取る方法がまとめられており、チャートの形状に意味を見出す視点が養われます。特に「三川明けの明星」「三川宵の明星」などは、相場の天底を示唆する代表的なサインとして紹介されています。
また、ローソク足の形状だけでなく、その背景にある投資家心理や流れを読む感覚も重視されており、「形から先を読む」という分析姿勢が伝えられています。

第8章 テクニカル指標の組み合わせで勝率UP!
単一の指標では判断が難しい局面に対応するため、複数のテクニカル指標を組み合わせることで、売買の精度を高める方法がこの章で解説されています。この章では、具体的な組み合わせ例として「移動平均線+MACD」「ボリンジャーバンド+MACD」「パラボリック+RCI」「一目均衡表+DMI」などが取り上げられています。
これらの組み合わせによって、売買タイミングをより明確にし、指標単独での弱点を補完することが可能になります。万能な指標は存在しないという前提のもと、それぞれの特性や得意な相場局面に合わせて選定・活用する重要性が強調されています。
また、2~3種類の指標を組み合わせることで、相場の方向性や勢い、反転の兆候など、複数の視点からの判断が可能になる点も示されています。

第9章 ファンダメンタルズ分析にも役割が!
チャート分析をメインに据えた本書においても、ファンダメンタルズ分析の重要性は無視できないと説かれています。この章では、企業の業績や経済指標など、チャートには表れない“内面的な要素”についての考え方がまとめられています。
特に、PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、ROE(自己資本利益率)などの基本的な財務指標について解説されており、それぞれが投資判断の指標となる仕組みが簡潔に説明されています。また、決算発表や世界情勢の変化といったファンダメンタルズが、テクニカル指標と相互に作用する点にも触れられています。
保存期間が長くなるほどテクニカルの有効性は増す一方で、中長期の視点ではファンダメンタルズの変化が重要になることも、バランスの取れた視点として提示されています。

第10章 チャート分析 Q&A
最後の章では、読者がチャート分析を実践する際に感じるであろう疑問を取り上げ、Q&A形式で丁寧に答えています。たとえば「時間軸はどう設定すればよいか」「設定値が合わずシグナルが少ない場合はどう対応するか」「大型株と中小型株で指標の使い方は変わるか」といった、非常に実践的な内容が網羅されています。
さらに、「異なる指標が相反するシグナルを出した場合はどちらを優先すべきか」や、「長期トレードにおけるパラメータ設定の考え方」など、読者が現場で迷いそうな場面を先回りして補足しています。
この章は、前の章で学んだ知識をどう活用し、自分のトレードスタイルに合わせて調整していけばいいのかを学ぶ“実践編”として位置づけられており、特に初心者にとっては心強いサポートとなる構成です。

対象読者

本書『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2』は、単に投資の知識を増やすためだけの本ではありません。読者一人ひとりが、「自分に合った投資スタイル」を見つけ、実践に活かすための道しるべとなる実用書です。
とくに次のような読者にとっては、本書は非常に有効なサポートとなるでしょう。
- 投資をこれから始めたい初心者の方
- テクニカル分析を学び直したい個人投資家
- 株、FX、仮想通貨のトレードに興味がある方
- 投資心理とチャート分析の関係に興味がある人
- マーケットの変化に強くなりたい全ての個人投資家
それぞれの読者層が、この本を通じて何を得られるのか、次で詳しく解説していきます。
投資をこれから始めたい初心者の方
これから投資を始めたいと思っている初心者にとって、最初のハードルは「何をどう学べばいいのか分からない」ということです。本書はまさに、その最初の一歩を支えるために作られています。投資に不可欠なチャート分析を基礎から応用まで段階的に解説しており、難しい専門用語は図解やマンガを用いて、直感的に理解できる工夫が施されています。
また、ローソク足や移動平均線といった基本的な指標はもちろん、DMIやRCIなどの実戦的な手法にも触れており、初学者でも段階的にスキルアップできる構成になっています。複雑なテクニカル分析も、「なぜそれが重要なのか」「どんな場面で使うのか」という目的が明確に示されているため、無理なく学習を進めることが可能です。

テクニカル分析を学び直したい個人投資家
一度はチャート分析に触れたことがあるけれど、実際のトレードで活かしきれていない――そんな経験を持つ個人投資家も少なくないでしょう。本書は、そうした方が自分の手法を見直し、より実践的な視点からテクニカル分析を学び直すのに最適です。
「万能な指標は存在しない」という前提に立ち、それぞれの指標の特性を理解したうえで、どう組み合わせれば効果的な売買判断に繋がるのかを丁寧に解説しています。特に、チャート分析Q&Aでは「異なる指標が違うシグナルを出したときの判断法」や「時間軸の選び方」といった、現場でのリアルな悩みにも答えが提示されており、再学習に必要な実務的視点が詰まっています。

株、FX、仮想通貨のトレードに興味がある方
本書で紹介されているチャート分析の技術は、株式市場にとどまらず、FX(外国為替証拠金取引)やビットコインをはじめとする仮想通貨など、さまざまな金融商品のトレードに応用可能です。どの市場でも、価格の変動には人間の心理が関与しており、それを読み取る手段としてテクニカル分析は共通して機能します。
たとえば、トレンド系指標であるDMIは、値動きの方向と勢いを可視化し、通貨や仮想通貨などボラティリティの高い市場で役立ちます。また、RCIやサイコロジカルラインといったオシレーター系指標は、短期的な反発や過熱感を判断するのに効果的で、仮想通貨のような急騰急落の激しい商品にも対応できます。

投資心理とチャート分析の関係に興味がある人
「なぜそのタイミングで相場は動いたのか?」「なぜ多くの投資家が同じようなタイミングで売買するのか?」――こうした疑問は、チャート分析の先にある“投資心理”の理解によって初めて明らかになります。本書では、サイコロジカルラインや酒田五法といった、心理面に注目した指標にもフォーカスしており、相場に現れる“集団心理”の傾向を読み解くことができます。
酒田五法は、江戸時代から続くローソク足分析の技術で、価格の形や並び方から売買のサインを見抜くものであり、そこには「人間の感情」が色濃く反映されています。また、サイコロジカルラインは、買われすぎ・売られすぎの状態を数値で示すことで、「どのタイミングで反転しやすいか」を判断する材料として使えます。

マーケットの変化に強くなりたい全ての個人投資家
私たちが投資を行う環境は、常に変化しています。地政学リスク、経済政策の変更など、どれも相場に大きなインパクトを与えます。こうした「変化」に対して感情的に反応するのではなく、データと分析に基づいた冷静な判断を下せるようになる――それが本書の大きな価値です。
特に、DMIやパラボリックなどのトレンド系指標を使えば、「今の相場に方向性があるのか」、あるいは「レンジ状態で力が拮抗しているのか」を判断することができます。相場の“現在地”を把握することができれば、リスクの取り方も自ずと明確になるはずです。

本の感想・レビュー

初心者でも読める
私はこれまで投資に対して「難しそう」「自分には無理かも」と思い込んでいました。特にチャート分析なんて、数字や線が並ぶグラフを読み解くイメージがあって、完全に敬遠していたんです。でも、この本を読んで、その思い込みは見事に裏切られました。良い意味で、です。
本書の冒頭には、実生活の出来事にたとえたマンガが載っていて、まずそこでスッと引き込まれました。マンガで始まるというだけで心理的なハードルが下がりますし、そこから解説へと自然につながっていく構成は、本当に親切だと思います。
専門用語も一切置き去りにせず、初めて触れる人にも分かるようにていねいに説明されています。「DMI」や「RCI」といった言葉は、最初はまったく意味不明だったのに、読み進めるうちに「なるほど、そういうことだったのか」と納得できる瞬間が何度もありました。
投資の入門書はたくさんありますが、「投資を知らない人の気持ちにちゃんと寄り添ってくれる本」って実は少ないと思います。この本は、その点で本当に信頼できる一冊です。
図解が豊富
チャート分析の本と聞くと、正直「文字ばかり」「読みづらい」という印象を持っていました。でもこの本を読んで、その考えが完全に変わりました。理由は、図解の豊富さと配置のわかりやすさです。
ひとつひとつの指標について、具体的なチャートの画像や視覚的な説明がしっかりと載っていて、文字だけでは伝わらない感覚的な部分まで、きちんと補ってくれます。視覚的な情報があるだけで、理解度が格段に違います。
特に印象的だったのは、複数のテクニカル指標を組み合わせた際のシグナルの出方が図解で示されていた点です。文章で「こうなったら買い」と書かれていても、初心者にはイメージが難しいものですが、実際のチャート画像と並んでいれば一目瞭然。ああ、こういう場面で判断するのかと、感覚的に掴むことができました。
情報の配置もごちゃごちゃしておらず、整然としていてとても読みやすかったです。図を多く載せつつも、ページが窮屈にならないレイアウトにはセンスを感じました。これなら、初学者だけでなく、復習したい人にもおすすめできます。
マーケットの心理が分かる
私は投資歴が5年を超える個人投資家ですが、ここまで投資家心理に言及しているチャート分析の本にはなかなか出会えませんでした。だからこそ、この本に出会ったときは、久しぶりにワクワクしました。
たとえば、サイコロジカルラインや酒田五法の解説では、単なる数値の動きではなく、「人はこういう場面でどう感じるのか」「その感情がどういう売買行動に繋がるのか」といったところまで踏み込んでいます。
テクニカル分析の本って、どうしても“ツールの使い方”に終始しがちなんですが、本書では、その奥にある“人間の本能”や“感情の流れ”に光を当てています。この視点を持つことで、チャートの「線や数字」だったものが、「人の行動の痕跡」に見えるようになりました。
マーケットは人間の集合体です。その心理がどんなかたちでチャートに現れるのかを学べたことで、これからの投資に対する見方がぐっと深まりました。
複数の金融商品に使える
私は株だけでなく、FXや仮想通貨など、複数の金融商品に興味を持っているタイプの投資家です。だからこそ、ある特定の市場にしか通用しない知識ではなく、もっと汎用性のある理論を学びたいと思っていました。
その点でこの本は、まさに自分が求めていた内容でした。どのチャプターを読んでも、指標の解説が「株に限定されていない」んです。基本的な概念や指標の動きは、市場を問わず共通するものが多く、それがしっかり伝わってきます。
巻頭でも、「チャート分析は株だけでなく、FXや仮想通貨でも活用できる」と明言されていて、その通りの内容構成になっているのが好印象でした。私のように複数の金融商品にまたがって投資をしている人にとって、こういう本は貴重です。
指標の選び方や組み合わせ方も解説されているので、読み終えた直後から、すぐに自分の投資スタイルに応じた応用が効きます。「どんな商品にも通じるチャート力」を鍛えるには、非常に実用的な一冊です。
Q&A形式が便利
投資の勉強をしていると、どうしても出てくるのが「細かい疑問」です。そんなときに、一からネットで調べるのは時間も手間もかかります。でもこの本には、その“ちょっとした疑問”にすぐ答えてくれるQ&A形式のパートが用意されていて、それがとてもありがたかったです。
特に、トレードスタイル別の時間軸の選び方や、異なる指標から異なるシグナルが出たときの対応の仕方など、現場で起こりうるリアルな問題に対して、簡潔で的確な回答がまとめられています。
このパートが巻末にあるおかげで、読後も「ちょっと確認したい」と思ったら、すぐに該当箇所を見つけられます。読み物としてだけでなく、実用書としての機能も果たしてくれているのが素晴らしいと思いました。
チャート分析が楽しくなる
これまで、チャート分析の勉強といえば、私にとっては“苦行”でした。画面に並ぶローソク足や指標の名前を見ては、うんざりする日々。でも『チャート分析2』は、その「つまらない」「難しい」というイメージを一変させてくれました。
読んでいてまず驚いたのは、冒頭にマンガ形式の導入があること。学習本なのに、導入が柔らかい。すっと読みやすくて、しかも内容のポイントをしっかり押さえているから、いきなり身構えずにすむんです。ページをめくるたびに、「次は何が出てくるんだろう?」という好奇心が湧きました。
この本は、教科書のように一方的に解説するのではなく、読者の「分かりたい気持ち」に寄り添ってくれているように感じます。図表も多く、視覚的に理解できる場面が多いから、自然と頭に入ってくるんです。
投資の勉強って、本来こうであるべきだなと思いました。「楽しい」という気持ちは、続けるうえで何より大事。この本を読んで、初めてチャート分析を「もっと学びたい」と思えるようになりました。
著者の実体験がリアル
投資の本を読むとき、私が最も重視しているのは「著者の現場感」です。理屈だけ並べる本では、現実の相場に対応できない。けれど、本書の福島理さんは、そこがまったく違いました。
随所に見られる解説は、実際のマーケットを経験した人でなければ書けないような視点が詰まっています。具体的な手法の説明にも、抽象的な話だけでなく、「なぜこの指標が必要なのか」「どんな背景で使われるのか」といった現実的な視野が通っていて、ただの理論ではない重みを感じました。
中でも印象的だったのは、チャート分析を「万能なツールではない」と明確に書いてあること。これは、テクニカル分析を盲信させるような本とは一線を画す姿勢です。実体験に基づいた、誠実なアドバイスとして響きました。
机上の空論ではない、リアルな投資現場に通じた本だからこそ、信頼して読み進めることができました。著者の声が、静かに背中を押してくれるような本です。
他の分析本とは一線を画す
テクニカル分析の本は、もう何冊も読みました。でも、正直どれも似たり寄ったりの内容で、「結局、どれを読んでも同じなのでは?」という気持ちになっていたのが本音です。そんな私にとって、この『チャート分析2』は完全に“別物”でした。
まず、目次の構成からしてユニークです。DMIやパラボリック、RCIなど、ある程度マニアックな指標も含まれていますが、それをどう組み合わせるかという実践的なアプローチが深く掘り下げられています。この「組み合わせ方」を一冊の中で体系的に扱っている本は、意外と少ないんです。
また、「チャート分析Q&A」という章の存在が秀逸でした。一般的な分析本では、指標を説明するだけで終わってしまいますが、本書は「どう使えばいいか」「どんな悩みが出るか」にまで踏み込んでいます。これにより、読者はただの理論書ではなく“相棒”のように本書を活用できるのです。
投資の現場に即した実用性、そして深掘りのバランス。どちらも備えた、まさに“ありそうでなかった”チャート本だと感じました。
まとめ

本書は単なる知識の詰め込みではなく、「使える分析力」を身につけることを目的としています。テクニカル分析という一見難しそうな領域に、読者が自然に入り込めるように工夫されており、読了後には確かな手応えが残る一冊です。
ここでは、読後に得られる変化と次のステップについて、3つの視点から整理していきます。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
これらの要素を通じて、本書が読者にもたらす学びと、今後の投資活動にどのように活かしていけるかを見ていきましょう。
この本を読んで得られるメリット
投資において「知識がある」ことと「使える」ことには大きな違いがあります。本書『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2』は、読者がただの情報収集に終わるのではなく、実際のトレードで成果を上げられるようになることを強く意識して構成された一冊です。
以下に、本書を通じて得られる代表的なメリットを解説します。
実践的なチャート読解力が身につく
本書は、単なるテクニカル指標の紹介にとどまらず、それらを実際のチャートにどのように当てはめて使うかという「読み解きの技術」にまで踏み込んでいます。たとえば、DMIの各構成要素(+DI、-DI、ADX)がそれぞれ何を意味し、どのような関係性でシグナルを発するのかを図解を交えて具体的に説明。これにより、読者は「なんとなく使っていた指標」の本質を理解し、的確な売買判断につなげられるようになります。
投資スタイルに応じた指標の使い分けが学べる
マーケットは一つでも、投資家のスタイルは人それぞれ異なります。本書では、トレンドフォローに向いている指標、逆張り向けのオシレーター系指標など、相場の局面や投資戦略に応じた使い方を体系的に学ぶことができます。そのため、自分の取引時間軸や性格に合った分析手法を選び、無理のない形でテクニカル分析を取り入れることが可能になります。
チャート分析を組み合わせて応用できるようになる
チャート分析は単体での精度も重要ですが、複数の指標を組み合わせて補完し合うことで信頼度を高めることができます。本書の中でも、「移動平均線+MACD」「パラボリック+RCI」「一目均衡表+DMI」などの具体例を通じて、どう組み合わせれば相場の誤認識やダマシを回避できるのかを学べます。この知識は、分析の精度を一段引き上げてくれる強力な武器になります。
投資家心理と価格の関係を感覚的に理解できる
サイコロジカルラインや酒田五法といった、心理を可視化する指標も紹介されており、価格の裏にある「人間の行動パターン」に対する理解が深まります。特に、チャートが人々の恐怖や欲望をどのように反映しているかを感覚的につかめるようになることで、「なぜ今、相場が動いたのか」が腑に落ちやすくなり、ニュースや噂に振り回されにくくなります。
わかりやすい導入で分析が楽しくなる
本書は各章の冒頭にマンガを採用しており、分析手法が現実の生活や心理とどのように似ているかを直感的に伝えています。これにより、これまで分析を難しいと感じていた人でも楽しく学習を進められ、「もっと知りたい」という意欲を自然に引き出してくれます。

読後の次のステップ
本書を読み終えた後、大切なのは「知識をどう使うか」です。ただ読むだけで満足せず、学んだチャート分析を自分の投資判断に組み込んでいくことが、本当の意味での“成果”につながります。
ここでは、読了後に実践すべき具体的なステップを紹介します。
step
1気になる銘柄のチャートで実地練習する
まずは、あなた自身が普段チェックしている銘柄、または興味のある株や為替のチャートを用いて、実際に学んだ指標を当てはめてみましょう。たとえば、DMIでトレンドの強弱を確認したり、RCIで買われ過ぎ・売られ過ぎを測定したりして、自分の直感と指標の示す内容の違いに気づくことが大切です。知識として学んだテクニカル分析が、実際のチャートとどう一致し、または食い違うのかを観察することで、理解が一気に深まります。
step
2「分析ノート」を作ってトレード記録を始める
自分の分析結果と実際の相場の動きを照らし合わせるために、記録をつける習慣を持つと効果的です。いつ、どのタイミングで、なぜエントリーまたはイグジットを判断したのかを簡潔に書き残しておくだけで、自分の判断傾向やクセが見えてきます。この振り返りこそが、トレードスキル向上への最短ルートです。本書に登場するQ&Aや用語集も活用しながら、自分だけの学びの軌跡を築いていきましょう。
step
3少額でのシミュレーションやデモトレードに挑戦する
いきなり大きな資金を投じるのではなく、少額でのトレードや、デモ口座でのシミュレーションから始めることで、実際の感覚を掴むことができます。こうすることで、損失のリスクを抑えながら、本書で得た知識を実地で“試す”ことができ、分析手法が自分に合っているかを冷静に見極められます。特に、本書で紹介された指標の組み合わせや相場の局面ごとの使い分けは、実践でこそ真価が問われます。
step
4分析に慣れたら“検証”にステップアップする
単に「上がった・下がった」で終わらせず、なぜその判断をしたのか、結果がどうだったのか、他にどの分析が有効だったかを検証することが重要です。過去チャートを使ってバックテストすることで、ある指標の有効性や自分の判断精度が明確になり、より精緻な売買戦略を構築できるようになります。本書の解説は、このような深い検証にも耐えうるだけの具体性と網羅性を備えています。

総括
『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2』は、テクニカル分析の世界において「実践で使える」知識と判断力を磨くための良書です。多くの投資関連書が、指標の定義や使い方を単調に並べて終わってしまう中で、本書は読者が“その先”に進むためのステップを明確に提示してくれます。
特に本書が優れているのは、理論と感覚の両方をバランスよく補ってくれる点にあります。テクニカル指標の裏にある数式や構造を丁寧に説明しながらも、実生活や日常の感覚に例えて理解させてくれる構成が秀逸です。冒頭に描かれるマンガや各パートの導入エピソードがその好例で、読者を置き去りにすることなく、むしろ楽しませながら理解を深める工夫が随所に施されています。
また、DMIやパラボリック、RCI、移動平均乖離率など、やや専門的で中級者向けの指標も扱いながら、それらをどう組み合わせると効果的か、という“応用の指導”までしてくれる点は見逃せません。単なる知識の羅列ではなく、「どう活用するか」を本気で考え抜いて作られている一冊です。これにより、読者は「知識を持っているだけの人」から、「知識を戦略として活用できる投資家」へと進化する手助けを得られます。
さらに、巻末のQ&Aや用語集は、実践中に生じる小さな疑問や混乱をすばやく解消してくれる“セーフティネット”のような存在です。読了後も何度も手に取りたくなる構成になっているため、まさに“使い倒す”タイプの一冊と言えるでしょう。

投資で成果を出すには、経験と知識の両方が必要です。しかし、経験だけでは乗り越えられない局面や、知識だけでは判断がつかない瞬間もあります。
本書が提供してくれるのは、そうした「迷いの場面」を乗り越えるための複眼的な視点であり、それはまさに不確実な相場に向き合うための“コンパス”と言えるでしょう。
テクニカル分析の勉強におすすめ書籍

テクニカル分析の勉強におすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- テクニカル分析の勉強におすすめの本!人気ランキング
- マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド
- 日本テクニカル分析大全
- 手法作りに必要な“考え”がわかる データ検証で「成績」を証明 株式投資のテクニカル分析
- 真・チャート分析大全 ──王道のテクニカル&中間波動編
- 勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2
- テクニカル分析 最強の組み合わせ術
- ずっと使えるFXチャート分析の基本 (シンプルなテクニカル分析による売買ポイントの見つけ方)

