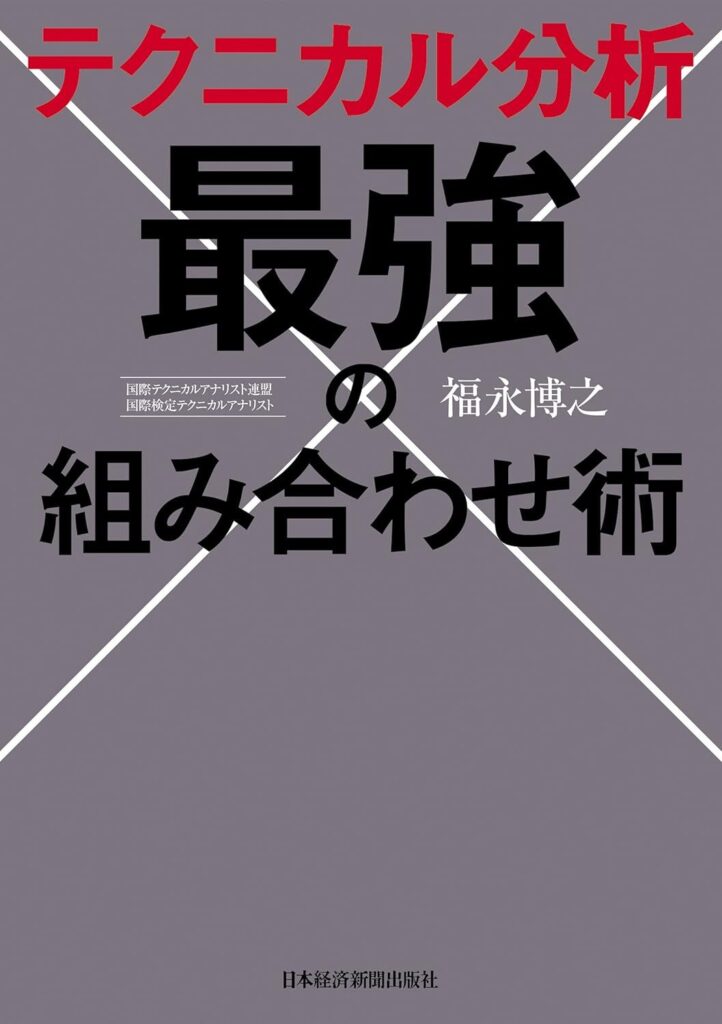
テクニカル分析を勉強しているけれど、「どの指標を使えばいいのか分からない」「売買のタイミングがうまくつかめない」と悩んでいませんか? そんなあなたにぜひ手に取ってほしいのが『テクニカル分析 最強の組み合わせ術』です。

本書は、移動平均線、MACD、RSIなど、株式投資でよく使われるテクニカル指標を単独で使うのではなく、「組み合わせる」ことで弱点を補い合い、売買判断の精度を大幅に高める方法を解説しています。
一つの指標に頼り切った投資判断は「ダマシ(フェイクシグナル)」に引っかかりやすいもの。
だからこそ、複数の指標を連携させて相場の本質を読み解くスキルが、投資家としての成功を左右します。
本書では、初心者でもすぐに実践できるように、具体的なチャート事例やわかりやすい解説が満載。
デイトレード、スイングトレード、中長期投資まで、あなたのトレードスタイルに合わせた最適な指標の組み合わせ方を丁寧に教えてくれます。
さらに、大型株・中型株・小型株といった銘柄規模別の使い分けまでカバーしており、どんな投資家でも「なるほど!」と膝を打つ内容が詰まっています。

合わせて読みたい記事
-

-
テクニカル分析の勉強におすすめの本 7選!人気ランキング【2026年】
株式投資やFX、仮想通貨など、あらゆる金融商品のトレードにおいて重要なスキルのひとつが「テクニカル分析」です。チャートの動きから相場のトレンドや売買のタイミングを見極める力は、初心者から上級者まで、す ...
続きを見る
書籍『テクニカル分析 最強の組み合わせ術』の書評

テクニカル分析に興味を持ち始めた方から、すでに経験のある投資家まで幅広い層におすすめの一冊です。この本を手に取ることで、「ダマシ」を回避し、精度の高い売買判断ができるようになるヒントが詰まっています。
このセクションでは、以下の4つの観点からこの本を解説していきます。
- 著者:福永博之のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれの切り口から、この本の魅力や読みどころをお伝えします。
著者:福永博之のプロフィール
福永博之氏は、株式会社インベストラストの代表取締役であり、日本テクニカルアナリスト協会副理事長を務めるテクニカル分析の第一人者です。国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)が認定するMFTA(Master of Financial Technical Analysis)という国際資格を持ち、テクニカル分析の実践と教育において国内外で高い評価を得ています。
彼は、勧角証券(現みずほ証券)やDLJdirectSFG証券(現楽天証券)での実務経験を経て独立し、個人投資家向けの投資教育や分析ツールの開発に力を注いできました。具体的には、投資教育サイト「itrust(アイトラスト)」の運営、特許取得済みの「注意喚起シグナル」やオリジナルツール「i-tool(アイツール)」の提供など、投資家の意思決定をサポートする幅広い活動を展開しています。
また、テレビ東京「モーニングサテライト」、日経CNBC「朝エクスプレス」、ラジオNIKKEI「スマートトレーダーPLUS」など、メディア出演も多数。わかりやすい解説で、投資初心者からプロまで幅広い層の投資家に信頼されています。

本書の要約
『テクニカル分析 最強の組み合わせ術』は、テクニカル指標の特性を正しく理解し、それらを組み合わせて実践的に使いこなすための手法を解説した一冊です。特に、トレンド系指標とオシレーター系指標の両方を取り入れることで、売買判断の精度を高め、「ダマシ(偽のシグナル)」に惑わされにくい分析を実現します。
例えば、株価の大きな動きが見られる主力株には「移動平均線×MACD」、中期投資には「移動平均線×ストキャスティクス」、新興市場銘柄には「ボリンジャーバンド×MACD」といった具体的な指標の組み合わせが紹介されており、状況に応じて実践しやすい内容になっています。
また、テクニカル分析の基本的な考え方や、トレードスタイルや銘柄規模に合わせた戦略の立て方も豊富なチャート事例とともに掲載されており、初心者から経験者まで幅広く活用できる内容です。

本書の目的
本書の目的は、一つのテクニカル指標だけに頼るのではなく、複数の指標を組み合わせて活用することで「ダマシ」に惑わされず、投資判断の精度を高めることです。テクニカル指標にはそれぞれ強みと弱みがあり、単独で使用すると弱点が露呈しやすくなります。
そこで、本書ではトレンド系指標で相場の方向性をつかみ、オシレーター系指標で売買のタイミングを見極め、さらに勢いを示す指標(モメンタムなど)も補助的に活用することで、複合的に分析し「ダマシ」を回避する方法を詳しく解説しています。
このアプローチによって、投資家は安心して売買判断ができ、損失リスクを最小限に抑えることが可能となります。初心者にもわかりやすくステップを踏んで学べるので、実践的にテクニカル分析を取り入れたい人には特におすすめです。

人気の理由と魅力
この本が多くの投資家から支持されているのは、理論だけでなく「すぐに実践できる」実用性の高さにあります。単にテクニカル指標を解説するだけでなく、実際のチャートを豊富に掲載しているため、読者は学んだその日にチャートを開いて試してみたくなる構成になっています。さらに、図表やチャートの見やすさにも配慮されており、数字や線が苦手な初心者でも視覚的に理解しやすいのが嬉しいポイントです。
また、初心者向けに専門用語やテクニカル指標の仕組みを一から丁寧に解説しているので、知識ゼロの状態からでもステップアップできるようになっています。逆に、中級者や実践経験者にとっても、「なるほど、こうやって組み合わせるのか」と新たな気づきを得られる一冊になっているため、幅広い層の投資家に響く内容です。
特に注目すべきは、単なるテクニカル分析の本ではなく、「相場局面」「投資スタイル」「銘柄規模」など、実際の投資家が直面するリアルな状況を想定して、それぞれのシナリオに合わせた分析手法が紹介されている点です。これにより、読者は単なる理論を学ぶだけでなく、自分の投資スタイルや好みに合わせて柔軟に応用できるようになります。

一冊でテクニカル分析の基礎から応用まで学べる上に、すぐに実践したくなるノウハウが満載!
これは投資家必携のバイブルです。
本の内容(目次)

本書は、テクニカル分析の基本から応用、そして指標の組み合わせによる実践的な活用方法まで、投資家がステップアップできるように全5章構成で解説しています。特に、初心者がつまずきやすいポイントや、実際のチャートを使った検証が随所に盛り込まれており、実戦で役立つ内容になっています。
各章のテーマは以下の通りです。
- 第1章 なぜテクニカル分析で成功確率が上がるのか
- 第2章 成功確率が上がる! トレンド系指標の使い方
- 第3章 成功確率が上がる! オシレーター系指標の使い方
- 第4章 トレンド系とオシレーター系。2つの指標を組み合わせて使う効用
- 第5章 トレンド系指標とオシレーター系指標を実際に組み合わせて検証
各章では、実践的なテクニカル分析のテクニックや売買判断を支える考え方が具体的に解説されています。
第1章 なぜテクニカル分析で成功確率が上がるのか
最初の章では、テクニカル分析の基礎的な考え方から入り、なぜこの分析手法が投資において重要なのかを解説しています。テクニカル分析は、株価の値動きや出来高など、チャート上に現れるデータをもとに市場の動向を予測する手法です。この章では特に、「客観的で再現性がある」というメリットが紹介されています。つまり、感情に左右されることなく、同じ条件下であれば誰がやっても同じ分析結果が得られるということです。
しかし、テクニカル分析を実際の売買で活用する際には、「ダマシ」と呼ばれる偽のシグナルに注意する必要があります。「トレンドが続くと思って買ったのに下落した」など、経験のある投資家も多いはずです。この章では、なぜダマシが発生するのかというメカニズムを明らかにし、売買判断を行う上で大切なポイントを詳しく説明しています。
また、トレンド系指標を使って大きな相場の流れを把握し、オシレーター系指標を用いて売買のタイミングを計るという「二段構え」の分析が有効であることもこの章で述べられています。さらに、売買タイミングだけでなく、日足・週足・月足という時間軸を考慮することの重要性も解説。どの時間軸でシグナルが発生するかで、売買判断が大きく変わることを実例で示しています。

第2章 成功確率が上がる! トレンド系指標の使い方
この章では、テクニカル分析の柱ともいえる「トレンド系指標」について、具体的な使い方と注意点が解説されています。トレンド系指標は、株価の方向性を把握するための指標で、特に移動平均線(MA)やMACD(移動平均収束拡散手法)が代表的です。
移動平均線は、一定期間の株価の平均値を結んだ線で、短期(5日線)、中期(25日線)、長期(75日線・200日線)と複数の期間で使い分けるのがポイント。ここでは、短期と中期の移動平均線を組み合わせて表示することで、ゴールデンクロス(買いサイン)やデッドクロス(売りサイン)を視覚的に把握する方法が紹介されています。ただし、移動平均線は「トレンドの転換を後追いで示す」という弱点があり、反応が遅れることも少なくありません。
その弱点を補うために、MACDという指標も活用します。MACDは短期・長期の移動平均線の差をもとに算出され、トレンドの方向性と勢いを同時に判断できます。特に「0ライン」を中心に、トレンド転換を見極める方法が実践的に解説されています。さらに、MACDとシグナル線のクロスを確認して、売買タイミングを把握する方法も紹介されています。

第3章 成功確率が上がる! オシレーター系指標の使い方
ここでは、テクニカル分析の中でも「売買タイミング」を見極めるために重要な「オシレーター系指標」について詳しく解説されています。オシレーター系指標は、相場が買われ過ぎているのか売られ過ぎているのかを判断する目安になり、特にレンジ相場(横ばいの相場)での売買タイミングを計るのに役立ちます。
RSI(Relative Strength Index)は、一定期間の値上がり幅と値下がり幅から相場の「強さ」を示す指標で、一般的に70%を超えると買われ過ぎ、30%を下回ると売られ過ぎと判断されます。ただし、ここでは「50%ライン」にも注目することで、トレンドが転換するタイミングを捉える方法が紹介されています。
モメンタム指標は、相場の勢いを測るための指標で、株価がどのくらいの勢いで上がっているのか下がっているのかを数値化できます。ローソク足と組み合わせて表示することで、相場の強さを視覚的に判断する方法も解説されています。
MACDもこの章で再登場し、売買サインのクロスや「逆行現象」(ダイバージェンス)など、上級者向けのテクニックも学べます。MACDはトレンド系指標としても使われますが、ここではオシレーター的に活用し、売買タイミングを見極める方法にフォーカスされています。

第4章 トレンド系とオシレーター系。2つの指標を組み合わせて使う効用
この章では、テクニカル分析をさらに実践的に使うための「指標の組み合わせ」について詳しく説明されています。テクニカル分析の大きな落とし穴は、一つの指標に頼りすぎると「ダマシ」にあってしまうリスクが高くなることです。ここでは、異なる種類の指標を組み合わせることで、その弱点を補い、より精度の高い分析を実現する方法が紹介されています。
具体的には、トレンド系指標で相場の方向性を確認し、その上でオシレーター系指標で売買タイミングを計るというアプローチです。例えば、移動平均線で大きなトレンドを判断し、RSIやストキャスティクスでエントリーやイグジットのポイントを見つけるといった使い方が解説されています。
また、「異なるシグナルが出たらどう対応するか」や「相場局面によっては機能しにくい指標もある」といったリアルな注意点も掲載されているので、理論だけでなく実践的な判断力が養われます。特に強い下降トレンドではオシレーター系指標が効かないケースや、方向感が定まらないときの短期RSIの活用法など、相場の実態に即したテクニックが豊富に紹介されています。

第5章 トレンド系指標とオシレーター系指標を実際に組み合わせて検証
この章では、実際のチャートで検証しながら、複数の指標をどのように組み合わせて分析すれば良いのかを具体的に学びます。移動平均線とRSI、ストキャスティクス、MACDなど、さまざまな組み合わせ例が取り上げられ、売買タイミングがどのように変わるかを比較検証していきます。
また、上昇相場・下降相場・横ばい相場といった市場の状況ごとに、どの組み合わせが有効なのかも検証されており、実際のトレードにすぐ活かせる内容が満載です。さらに、同じ株価の動きでも、組み合わせる指標によって売買タイミングが違って見えることを実例で示しているので、自分に合った分析手法を選ぶ参考になります。
最後に、「移動平均線×オシレーター系指標」の有効性についても総括されており、これまでの学びを総復習できます。この章を読むことで、初心者から中上級者まで、より実践的なテクニカル分析をマスターできるようになるでしょう。

第6章 トレードスタイルごとの最適な組み合わせ術
第6章では、デイトレード、スイングトレード、中長期投資など、投資家それぞれのスタイルに合わせたテクニカル指標の組み合わせ方を具体的に紹介しています。「自分の投資スタイルに合った分析方法が知りたい!」という声に応える、非常に実践的な内容です。
たとえば、デイトレードのように短期売買では、5日移動平均線とストキャスティクス、あるいはMACDの短期設定を組み合わせることで、細かい値動きをタイムリーに捉える方法が解説されています。一方、スイングトレードや中期投資では、25日線や75日線とRSI、MACDの組み合わせで、数日のトレンドをしっかりフォローしながらタイミングを計る手法がわかります。
また、長期投資家向けには、200日移動平均線や週足・月足チャートを使った分析方法も紹介されており、幅広い層の投資家が参考にできます。著者自身の経験談や注意点も盛り込まれているため、実践で役立つヒントが満載です。

第7章 大型株、中型株、小型株に最適な組み合わせ術
最後の章では、株の規模別にテクニカル指標の使い方が詳しく解説されています。大型株、中型株、小型株は、それぞれ値動きの特徴が異なるため、同じ指標を同じように使うだけではうまくいかないことも少なくありません。
例えば、大型株は流動性が高くトレンドが比較的安定しやすいため、移動平均線でしっかりトレンドを捉えた後、MACDで売買タイミングを確認する方法が有効とされています。一方、中型株はトレンドの持続性はあるものの、急騰・急落も比較的多いため、移動平均線×ストキャスティクスで短期的な過熱感を見極める方法が紹介されています。
小型株は、値動きが荒くトレンドの転換が急なので、ボリンジャーバンドやRSIを組み合わせて、過熱感や反転ポイントを素早く捉えるテクニックが推奨されています。さらに、指標を使い分ける際の注意点や、資金管理のポイントも紹介されており、初心者から中上級者まで参考になる内容です。

対象読者

『テクニカル分析 最強の組み合わせ術』は、これから投資を始める人から、すでにある程度テクニカル分析を実践している人まで、幅広い層の投資家に役立つ一冊です。
特に次のような方々におすすめしたい内容が充実しています。
- 投資初心者の方
- テクニカル分析に興味がある中級者の方
- 売買タイミングに悩むトレーダー
- 損失のリスク管理に課題を感じる方
- 複数のテクニカル指標を駆使したい方
それぞれの読者層に合わせて、具体的な活用方法や学び方を詳しくご紹介していきます。
投資初心者の方
これから株式投資を始めようという方にとって、テクニカル分析は「難しそう」「数字が多くてとっつきにくい」と感じるかもしれません。しかし、本書では投資の基本から丁寧に解説し、チャートの見方、移動平均線やRSIなどの代表的な指標の使い方を、図解を交えながらやさしく紹介しています。
「テクニカル分析って何?」という疑問が、「なるほど、こういうふうにチャートを読むのか!」と楽しく変わるはずです。さらに、複数の指標を組み合わせることで、株価の動きを多角的に捉えられることを、実例とともに学べるので、投資初心者でも安心してステップアップできます。

テクニカル分析に興味がある中級者の方
すでにテクニカル分析を一度は学んだことがある方でも、「移動平均線は分かるけど、MACDやRSIとの組み合わせがうまくできない」という悩みを抱えることがあります。本書では、単独の指標だけでなく、トレンド系とオシレーター系の指標を組み合わせて分析する方法を詳しく解説しており、中級者がさらにステップアップできる内容になっています。
たとえば、トレンド系指標で相場の大きな流れをつかみ、オシレーター系指標で売買タイミングを計る、といった実践的な使い分け方が豊富なチャート例で紹介されています。単一の指標だけに頼らず、複数指標を補い合うことで投資判断の精度を高めたい方に特に役立つ内容です。

売買タイミングに悩むトレーダー
「エントリーやエグジットのタイミングがなかなかうまくいかない…」という方にとって、本書は強力な味方になります。MACDやRSIなどの売買タイミングを示す指標について、単独で使うだけではなく、トレンド系指標と組み合わせることで「だましシグナル」を減らし、的確なタイミングを導き出す方法が丁寧に解説されています。
実際のチャート事例を交えて、どのタイミングで売買シグナルが出るのか、どのように判断すれば成功率を高められるのかが分かりやすく示されているので、実践力がしっかり身につきます。

損失のリスク管理に課題を感じる方
株式投資で利益を出すには、まず「負けないこと」が大切です。しかし、テクニカル指標のシグナルだけに頼ると、相場の急変やフェイクシグナルに振り回されて損失を抱えるケースが後を絶ちません。本書では、指標を組み合わせて相場の動きを多面的に分析することで、だましを回避し、損失リスクを減らす方法を詳しく解説しています。
特に、移動平均線でトレンドを確認し、オシレーター系指標でタイミングを計るという組み合わせ術を使えば、売買判断に余裕が生まれ、慌てて売買することがなくなります。リスク管理を徹底して投資を続けたい方には必携の一冊です。

複数のテクニカル指標を駆使したい方
「MACDだけだと心もとない」「RSIのサインだけじゃタイミングが不安」そんな経験をしたことがある方には、本書の「組み合わせ術」がまさに救世主です。移動平均線とMACD、RSIとストキャスティクス、ボリンジャーバンドとMACDなど、実戦でよく使われる組み合わせ例が多数紹介されています。
さらに、これらの指標を場面に応じて使い分けるコツや、指標同士のシグナルが矛盾した場合の判断方法まで、著者の経験をもとにした具体的なアドバイスが満載です。単独の指標に頼るのではなく、複数の指標を連携させてシグナルの精度を高め、ダマシを減らす――そんなテクニカル分析の醍醐味を存分に味わえます。

本の感想・レビュー

テクニカル分析初心者でも理解できる
投資を始めてまだ日が浅い私にとって、「テクニカル分析」という言葉はとてもハードルが高く感じていました。特に移動平均線とかMACDとか、聞いたことはあっても実際にはどう使えばいいのか全然分からなかったんです。これまでも投資本はいくつか読んできたけれど、専門用語ばかりで途中で挫折してしまった経験ばかり。でも、この本を読んで、その印象がガラリと変わりました。
最初に示されているのが「テクニカル指標の組み合わせでダマシを回避する」というテーマで、これがとても分かりやすかったです。最初に目的がはっきりしていると、初心者としては「これなら頑張って読めそう!」と前向きな気持ちになれるんですよね。そして、どの指標がどんな特徴を持っているのかを、具体的なチャート例とともに解説してくれていて、「あ、こうやってチャートを見るのか」とスッと頭に入ってきました。
文章も難しい専門用語が出てきたらすぐに補足説明があるので、読みながら迷子になることがなかったです。読んでいるうちに、「よし、自分でもやってみよう」と自然に思えてきて、テクニカル分析がぐっと身近に感じられる一冊でした。
豊富な事例と図解で実践的
普段からチャートを見るのは好きなんですが、実際に指標を使って売買するとなると、どうもピンとこなくて苦手意識がありました。だから、この本の魅力は、理論をただ解説するだけじゃなく、実際のチャートをこれでもかというくらいふんだんに使って説明してくれているところです。
特に感心したのは、各指標の使い方を、実際の相場状況に当てはめながら段階的に教えてくれるところでした。文章だけだとどうしても理解しにくい部分ってあるんですが、実際のチャートが添えられていると、一目で「あ、ここで買いサインが出てる」とか「なるほど、こうやってトレンドが見えるんだな」とイメージが湧くんですよね。
また、トレンド系とオシレーター系の組み合わせを実際のチャートで検証しているので、机上の空論じゃないんだなと実感しました。読みながら「これなら自分のトレードでも活かせる」と思えるのが、この本のすごいところだと思います。
トレンド系とオシレーター系の違いが明確
今までなんとなく「トレンド系」とか「オシレーター系」って言葉は知っていたけど、正直どこがどう違うのか分からなかったんです。だからMACDもRSIも、一緒くたに「なんかチャートに線がいっぱいあるなぁ」程度にしか見てなかったんですよね。でも、この本を読んで、本当に目からウロコが落ちました。
一つひとつの指標について、どんな特徴があって、どんな場面で有効か、そして弱点は何かというところまでしっかり解説してくれているので、自分がどの場面でどの指標を参考にすればいいのかが、すごく分かりやすかったです。
これまで漠然としていた知識が一気につながって、頭の中が整理された感覚がありました。これからはトレードの場面で、しっかりと自分で判断して行動できそうな気がします。
ダマシを回避する組み合わせ術が秀逸
これまで投資をしていて、一番嫌だったのがこの「ダマシ」に引っかかってしまうこと。シグナルが出た!と思って飛び乗ったら、あっという間に逆方向に動いて損失が増えていく…。そんな悔しい経験を何度繰り返したことか分かりません。
だから、この本の一番の魅力は「ダマシ」を回避するための指標の組み合わせ術が、ものすごく分かりやすく解説されていたことです。特に移動平均線とMACDのように、トレンド系とオシレーター系を組み合わせて弱点を補い合うという考え方は、読んでいて「なるほど、こうすればダマシにやられにくくなるのか」と納得しました。
このアプローチを知ってからは、トレードの時に「このシグナルだけで動いていいのかな」と立ち止まれるようになって、無駄な損失が減るんじゃないかという期待が持てました。これからは怖がらずにトレードできそうです。
短期・中期の戦略に役立つ
私は普段から短期売買と中期投資の両方を実践しているのですが、そのたびに「どのテクニカル指標を重視すればいいのか?」と悩むことが多かったんです。この本を読み進めるうちに、そんな悩みを解決してくれるヒントがたくさん詰まっていることに気づきました。
特に印象的だったのは、チャートの動きや市場の状況に応じて、どの時間軸でどの指標を使えば効果的かという点が非常に丁寧に解説されていたところです。日足や週足の使い分け、移動平均線やMACDなどの指標を短期トレードと中期投資でどう生かすのか。そうした実践的なテクニックが、実際のトレードを強力にサポートしてくれると感じました。
この本に書かれていた指標の特性や組み合わせ方をしっかり頭に入れておけば、自分のトレード戦略がよりロジカルに、そして再現性を持って取り組めるんじゃないかと思えたのが大きな収穫です。
株価急騰・急落局面でも安心
私はこれまで、株価が急騰したときや急落したときにパニックになりがちで、結局チャンスを逃したり大きな損失を被ったりしていました。そんな時にこの本を手に取ったのですが、読んでみると「これなら急変動局面でも落ち着いて対応できそうだ」と思える内容が満載で、とても安心感を覚えました。
特に、移動平均線やMACDのようなトレンド系指標と、RSIやストキャスティクスのようなオシレーター系指標を組み合わせて、急変動の中でどう判断すればいいのかという具体例が豊富に掲載されていたのが心強かったです。読んでいて、「もし今この場面だったら、どの指標を見て判断すればいいんだろう」と考えながら読み進めることで、シミュレーション力がついた気がします。
この本のおかげで、相場の急変に一喜一憂するだけじゃなく、落ち着いて分析して行動できるようになりたいと強く感じました。
指標の特性を深く学べる
普段からテクニカル分析には興味があったものの、指標を「なんとなく」使っている感覚が抜けなかった私にとって、この本は一段階上の学びを与えてくれる存在でした。
各指標について、その強みや弱み、どのような相場状況で有効に機能するのか、そしてどこで「ダマシ」に遭いやすいのかといった細かい部分まで踏み込んで解説してくれていて、本当にためになりました。特に、移動平均線やMACDのような代表的なトレンド系指標と、RSI、モメンタムのようなオシレーター系指標それぞれについての詳細な説明があり、チャートを見ているだけでは分からなかった「指標の癖」を知ることができました。
この本のおかげで、指標の名前や数値だけでなく、その背景や成り立ちまで理解が深まり、これからのトレードで指標を使いこなす自信がついた気がします。
初心者から中上級者まで幅広く対応
私は投資歴がそこそこある中級者ですが、初心者の友人にもテクニカル分析の話をよく聞かれることがあります。だから、本書のように初心者にも分かりやすい内容でありながら、中上級者にも気づきの多い一冊というのは本当に貴重だなと感じました。
冒頭でテクニカル分析の基本から丁寧に解説しているので、初心者でも安心して読み進められるし、その後の章では組み合わせ術や実践的なケーススタディが豊富なので、中級者以上の投資家も「なるほど」と思わせられる内容です。
読んでいて感じたのは、「テクニカル指標の組み合わせを使いこなす」という視点は、投資を続けていくうえで絶対に必要だということでした。初心者はもちろん、今の手法に行き詰まりを感じている中級者の方にも、ぜひ手に取ってほしい一冊です。
まとめ

本書『テクニカル分析 最強の組み合わせ術』は、投資初心者から経験者まで幅広い層の投資家に役立つ内容が詰まった一冊です。
ここでは、この本を読むことでどのような力が身につくのか、読後にどのように活用していけばいいのか、そして最後に総括として本書の価値を改めて振り返ります。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
この本を読んで得られるメリット
本書『テクニカル分析 最強の組み合わせ術』は、単なる理論書ではなく、投資家が実践で役立つスキルを確実に習得できるように構成されています。
ここでは、本書を読むことで得られる具体的なメリットを、順を追って紹介していきます。
テクニカル分析の本質を理解できる
単に「移動平均線のゴールデンクロスで買い」「MACDのクロスで売り」というような単独の指標頼みの売買では、ダマシシグナルに振り回されてしまいがちです。本書では、なぜ指標を組み合わせて使うことが重要なのかという「テクニカル分析の本質」を、豊富なチャート事例を交えながら解説しています。テクニカル分析を「単なる売買サイン」ではなく、「相場の背景を読み解くツール」として活用する考え方が身につきます。
ダマシを回避して売買の成功確率が上がる
株式投資で最も怖いのは、「シグナル通りに動いたのに逆行して損失を出す」というパターンです。これは、オシレーター系指標が相場の勢いに振り回されて誤ったサインを出すことがあるからです。本書では、移動平均線などのトレンド系指標とオシレーター系指標を組み合わせることで、このダマシを回避しやすくする手法を紹介しています。結果として、売買の精度が格段に向上し、勝率アップが期待できます。
トレードスタイルに合わせた指標選びができる
デイトレード、スイングトレード、中長期投資といった自分の投資スタイルによって、最適なテクニカル指標の選び方は異なります。本書では、具体的にどの指標をどのように組み合わせると自分のスタイルに合うのかを丁寧に解説しています。そのため、自分に合った指標の組み合わせを見つけやすくなり、ムダな試行錯誤を減らすことができます。
大型株・中型株・小型株の特性に合わせた戦略がわかる
相場にはさまざまな銘柄がありますが、それぞれ値動きのクセや出来高の違いがあります。本書では、大型株・中型株・小型株の特徴を踏まえて、どの指標を組み合わせるのが最適かを丁寧に解説しています。これにより、今まで「銘柄ごとの値動きの違いがよくわからない」と感じていた方も、投資判断の精度を高められるようになります。

読後の次のステップ
『テクニカル分析 最強の組み合わせ術』を読み終えたあと、その知識をどのように実践に活かせばよいのか気になる方も多いでしょう。
ここでは、本書の内容を自分の投資に活かすためのステップを具体的に紹介します。
step
1学んだ組み合わせ術を実際のチャートで試す
まずは、本書で紹介された移動平均線とMACD、RSIとストキャスティクスなどの組み合わせを、自分が普段見ている銘柄やチャート上で試してみましょう。ただ眺めるのではなく、どの場面でどのシグナルが点灯したのか、その時のトレンド状況はどうだったのかなど、書籍で学んだポイントを意識しながら分析することで、実戦的な感覚が養われます。
step
2自分のトレードスタイルに合った指標設定を見つける
次に、書籍で学んだ移動平均線の期間設定やオシレーター系指標のパラメータを、自分の投資スタイル(短期・中期・長期)に合わせて調整してみましょう。例えば、デイトレードなら短期の移動平均線やオシレーターを使い、スイングトレードなら25日線や75日線を活用するといった具合です。本書では設定例も豊富なので、ヒントを得ながら自分だけの最適解を探していきましょう。
step
3ダマシを減らす検証ルールを作る
さらに、学んだ組み合わせ術を机上の理論だけで終わらせないために、自分なりの検証ルールを設けてください。本書で紹介されている「複数の指標が同時にシグナルを示す場面」や、「逆行現象」に着目した売買ルールなど、チェックリスト形式でまとめておくと便利です。これにより、リアルタイムの相場で実際にシグナルが出たときに即断せず、一呼吸置いてリスクを管理しやすくなります。
step
4実践と検証を繰り返し、自分だけの組み合わせ術を確立する
最後に、実際のトレードで学んだことを検証し、改善を重ねることで、本書の内容を自分の武器として完成させていきましょう。特に、トレードノートに自分が使った指標の組み合わせや結果、振り返りのポイントを記録しておくと、どのパターンが自分に合っているのかが見えてきます。こうしたプロセスを積み重ねることで、本書の「最強の組み合わせ術」を自分のものとして使いこなせるようになります。

総括
本書『テクニカル分析 最強の組み合わせ術』は、テクニカル指標を単独で使うだけでは見えにくかった相場の真実を、複数の指標を組み合わせることで立体的に捉えられるようになる一冊です。投資初心者から中級者、そして経験者まで幅広い読者を対象にしており、基礎知識から応用テクニックまで網羅されているため、誰でも段階的に学びを深められる点が大きな魅力です。
特に、移動平均線、MACD、RSI、ストキャスティクスなど、よく使われる指標については強みと弱みを丁寧に解説し、さらに実際のチャート事例を交えながら、どの場面でどの指標を組み合わせればよいのかが分かりやすく示されています。そのため、理論だけでなく実践的な知識として自分のものにできるでしょう。
また、単なる指標の説明にとどまらず、急騰局面や急落局面、横ばい相場など具体的な相場状況に応じた活用方法や、投資スタイル(短期・中期・長期)に合わせたアプローチも充実しているため、自分のトレードスタイルを確立したい方にとっても役立ちます。

本書を読み終えたとき、きっと多くの投資家が「単独の指標に頼らない多角的な相場分析こそが勝率を上げる鍵だ」と実感するはずです。
あなたの投資戦略をワンランク上に引き上げるパートナーとして、この本は心強い味方となるでしょう。
テクニカル分析の勉強におすすめ書籍

テクニカル分析の勉強におすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- テクニカル分析の勉強におすすめの本!人気ランキング
- マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド
- 日本テクニカル分析大全
- 手法作りに必要な“考え”がわかる データ検証で「成績」を証明 株式投資のテクニカル分析
- 真・チャート分析大全 ──王道のテクニカル&中間波動編
- 勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2
- テクニカル分析 最強の組み合わせ術
- ずっと使えるFXチャート分析の基本 (シンプルなテクニカル分析による売買ポイントの見つけ方)

