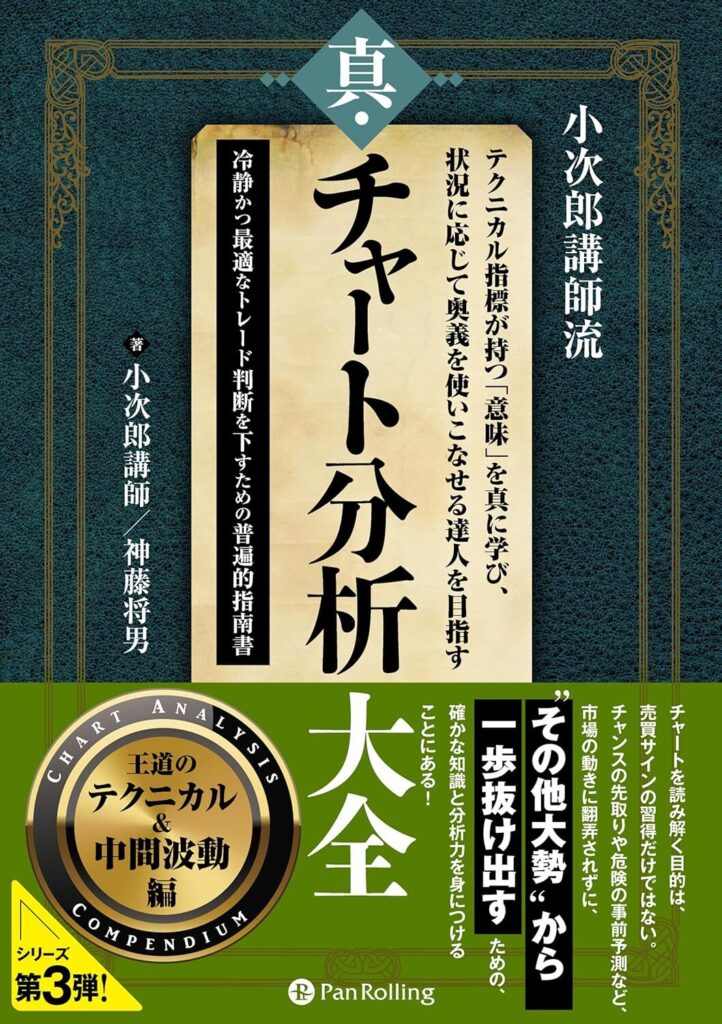
売買サインをただ追いかけるだけでは、相場の波に飲み込まれてしまいます。真に必要なのは「なぜ、ここでそのサインが出るのか?」という本質を見抜く目——。本書『真・チャート分析大全 ──王道のテクニカル&中間波動編』は、テクニカル指標の奥に潜む“理論の芯”を解き明かし、市場を客観的に捉える力を養うための一冊です。

投資歴45年を誇る小次郎講師と、「中間波動論」の第一人者・神藤将男氏のタッグによって構築された本書は、王道かつ実践的なチャート理論に加え、トレンドの初動を捉える最新理論までを網羅。
初心者にもわかりやすく、かつベテランにも学びがある、奥行きのある内容に仕上がっています。
売買の判断だけに頼らず、「今の相場はどんな流れなのか」を読み解きたいあなたに。テクニカルの“使い方”ではなく“考え方”を学びたいあなたに。
本書は、相場の世界で長く戦うための武器となるはずです。

合わせて読みたい記事
-

-
テクニカル分析の勉強におすすめの本 7選!人気ランキング【2026年】
株式投資やFX、仮想通貨など、あらゆる金融商品のトレードにおいて重要なスキルのひとつが「テクニカル分析」です。チャートの動きから相場のトレンドや売買のタイミングを見極める力は、初心者から上級者まで、す ...
続きを見る
書籍『真・チャート分析大全 ──王道のテクニカル&中間波動編』の書評

この本は、相場の流れを「自分の頭で考えて」読めるようになりたいすべての投資家に向けた、知的で実践的な一冊です。ただの売買サイン本とは一線を画し、「なぜそのサインが出るのか?」「それは市場の何を意味しているのか?」といった根本の理解を重視しています。
書評として本書の価値を多角的に分析するため、以下の4つの観点から紹介します。
- 著者:小次郎講師・神藤将男のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれの項目を順に見ていくことで、本書の全体像と特長がより明確になるでしょう。
著者:小次郎講師のプロフィール
小次郎講師(本名:手塚宏二)は、投資歴40年以上を誇る日本屈指のテクニカル分析指導者です。元証券マンという実務経験を持ち、長年にわたり相場と向き合いながら、独自の理論と実践的な手法を確立してきました。
特筆すべきは「移動平均線大循環分析」や「大循環MACD」といった、初心者にも理解しやすく、かつ応用力に富んだ独自インジケーターを開発したことです。また、証券会社勤務時代の経験を基に「投資教育の重要性」に目覚め、退職後はプロ講師として活動を開始。書籍やセミナー、YouTubeなどを通じ、幅広い層に向けて“トレーダーとして生き抜く力”を伝え続けています。

著者:神藤将男のプロフィール
神藤将男(しんどうまさお)は、元金融マンであり、現在はプロのトレーダー・分析者として活躍する人物です。自身も個人投資家として豊富な実戦経験を持ち、分析力と戦略構築力に定評があります。
彼が注目される大きな理由は、「中間波動」という独自の視点を確立したことにあります。中間波動とは、トレンドの転換点や継続パターンを高精度で読み解くための概念であり、これまで多くの分析本では曖昧に扱われていた領域を深く掘り下げています。
小次郎講師からもその研究姿勢と分析力に厚い信頼を寄せられており、本書では共同執筆者として、「より実践的かつ本質的なチャート分析」の構築に貢献しています。

本書の要約
『真・チャート分析大全 ──王道のテクニカル&中間波動編』は、単なるインジケーターの使い方を紹介するハウツー本ではありません。本書の特徴は、「なぜそのテクニカルが有効なのか」「なぜそこで売買サインが出るのか」といった“本質”の理解に重きを置いている点にあります。
テクニカル指標は相場の未来を予測するツールではなく、現在の市場がどのような状態にあるのかを“読み解く言語”です。本書では、ダウ理論やエリオット波動、フィボナッチなどの王道テクニカルに加えて、一目均衡表やDMI・ADX、パラボリックSARなど、幅広い指標を取り上げています。さらに、著者独自の「コジピボ」や「3×3分割投資法」、神藤将男氏の「中間波動論」など、日本の個人投資家に適した応用的内容が数多く盛り込まれているのも特筆すべきポイントです。
重要なのは、これらのテクニカルをただ機械的に使うのではなく、チャートを“読む”力を養い、自分の頭で判断する能力を高めること。本書はそのための理論と実践の両面を兼ね備えた指南書となっています。

本書の目的
本書の最大の目的は、「本質的なチャート分析力を持った投資家」を育てることです。表面的なインジケーターの知識や、売買サインの単純な追従ではなく、その背景にある相場の動きや市場の心理を読み解く力を身につけることに主眼を置いています。
著者は、テクニカル分析を「相場の状況判断の手段」と捉えており、売買サインはその一部に過ぎないと説いています。だからこそ、買いサインが出ている状況でも「なぜ買いなのか」「どこにリスクが潜んでいるのか」「逃げ道はあるか」といった視点を常に持つことが重要であると強調します。
本書では、こうした思考力を育てるために、指標の構造的な理解や、パターンの出現する確率、過去との比較、トレンドの継続・転換の兆しといった観点から多角的な視点を提供しています。特に中間波動に関する解説は、既存のチャート本では見られない新たな角度を加えるものであり、従来の分析では見落とされがちだった「相場の変化点」に光を当てる試みでもあります。

人気の理由と魅力
本書が多くの投資家から支持されているのは、その内容が「実際のトレードにすぐ役立つ」だけでなく、「理論の裏付けがしっかりしている」からです。特に他のテクニカル本と大きく違うのは、計算式や数値の意味まで掘り下げて解説している点にあります。たとえば、なぜDMIでは±DIを見るのか、なぜパラボリックSARがドテンの判断に使われるのか、といった根本的な問いに答えてくれるのです。
また、「中間波動」や「コジピボ」などの独自理論は、従来の教科書的アプローチでは得られなかった新しい視点を提供してくれます。これにより、読者は“ただの売買シグナルの利用者”から“相場の地図を描ける投資家”へとステップアップできるのです。
さらに、内容が高度でありながらも、文章は語り口調でやさしく、チャート図も豊富に掲載されているため、投資初心者でも挫折することなく読み進められます。理論と実例がセットになっているため、「読んだだけで終わる」ことなく、「すぐに使える」実践力が身につくのも大きな魅力です。

本の内容(目次)

この書籍では、チャート分析の基本から応用に至るまで、幅広い知識と技術を順を追って学べるよう章立てされています。それぞれの章は独立しつつも相互に関連しており、初心者が段階的にスキルアップできる構成になっています。
以下のようなテーマが取り上げられています。
- 第1章 ダウ理論
- 第2章 エリオット波動
- 第3章 フィボナッチ
- 第4章 ピボット(PIVOT)
- 第5章 ピボットを改良した小次郎講師流「コジピボ」
- 第6章 トレンドライン&チャネルライン
- 第7章 トレンドの初動を見つける「中間波動」
- 第8章 出来高と価格帯別出来高
- 第9章 DMI&ADX
- 第10章 パラボリックSAR
- 第11章 移動平均線大循環分析から派生した「3×3分割投資法」
- 第12章 一目均衡表 上級編
これらのテーマを一つひとつ深掘りすることで、単なるテクニカル指標の使い方にとどまらず、背景にある理論や市場心理まで理解できるようになります。
第1章 ダウ理論
すべてのテクニカル分析の原点とも言えるのがこの理論です。19世紀末、米ウォール街で「ウォール・ストリート・ジャーナル」を創刊したチャールズ・ダウが生み出したもので、相場の動きには“パターン”があるという考えに基づいています。ダウ理論では、市場には「上昇トレンド」「下降トレンド」「横ばい(もみ合い)」の3つの流れがあり、それぞれは「始まり」「中盤」「終わり」の段階に分かれるとされます。
具体的には、価格が「高値と安値を切り上げていく」状態を上昇トレンドとし、その逆が下降トレンドと定義されます。また、トレンドの確認には複数の市場(例:日経平均とTOPIXなど)が同調しているかを確認する「相関性」や、出来高による裏付けが重要とされています。

第2章 エリオット波動
エリオット波動論は、アメリカの会計士ラルフ・ネルソン・エリオットが提唱した理論で、価格の動きは「波」のように上下を繰り返すと考えます。具体的には、上昇相場では「5つの上昇波(推進波)」と「3つの調整波(修正波)」で構成される8つの波が基本形です。
この波は、どの時間軸でも出現しやすく、小さな波の中にもさらに小さな波が存在する「フラクタル構造」になっています。さらに、波の比率や到達点には「フィボナッチ比率(黄金比)」が頻繁に現れ、数理的な裏付けがあるとされています。

第3章 フィボナッチ
「1、1、2、3、5、8、13…」と続く有名な数列をご存知でしょうか? これがフィボナッチ数列です。この数列を用いた比率、たとえば「61.8%」や「38.2%」は、相場の押し目や戻りの目安として多くの投資家に使われています。
例えば、急騰後に価格がどれくらいまで下落するか、あるいは下落からどれほど反発するかといったシーンで、「どの辺りまで下がったら買いか?」を判断する基準になります。これは心理的な節目としても意識されやすいため、多くの場面で“効いて”くるわけです。

第4章 ピボット(PIVOT)
ピボットは、主にデイトレーダーが用いるテクニカル指標で、前日の「高値」「安値」「終値」から算出される値をもとに、当日の売買の目安を立てるためのラインです。ピボットポイントを中心に、上下に抵抗線(R)や支持線(S)が計算され、「価格がこのラインを超えたらトレンドが強まる」「跳ね返ったら反転」といった判断に役立てられます。
さらに本書では、単にラインを引いて終わりではなく、計算式の意味や終値の重要性、そして「中心価格」の考え方まで深掘りしています。これにより、単なる目印ではなく、市場心理の可視化としてピボットを活用できるようになります。

第5章 小次郎講師流「コジピボ」
本書最大の特徴のひとつが、著者独自の「コジピボ」という手法です。これは、ピボットをさらに即応性の高いトレードに最適化したもので、デイトレードの瞬発力が要求される場面で特に効果を発揮します。
コジピボでは、前日の終値と独自に設定された6本のラインを組み合わせて、値動きの方向性や反転ポイントを判別します。また、時間帯ごとのエントリーポイントの違いや、手仕舞い戦略、FX・先物での活用法、さらには“144通りの値動きパターン”といった応用まで解説されており、非常に実戦的です。

第6章 トレンドライン&チャネルライン
視覚的な判断を助けてくれる「線」の技術がこの章のテーマです。トレンドラインは、安値または高値を結ぶことで、現在の相場の流れ(トレンド)を確認できます。チャネルラインは、トレンドラインに平行な線を追加し、その範囲内での値動きの幅を捉えるものです。
この線は、トレンドが継続するのか、反転の兆しがあるのかを判断するうえで極めて有効です。また、意外と多くの人が間違うのが「どの点を結べばいいのか」という基本操作。本書では、その引き方の基本から、実際の相場でどう活用するかまでを丁寧に解説しています。

第7章 トレンドの初動を見つける「中間波動」
相場には「上昇」「下降」「もみ合い」といった大きな流れがありますが、その中間にはしばしば“揺り戻し”のような動きが現れます。この動きを「中間波動」と呼び、トレンドが継続するのか、転換するのかの分岐点として極めて重要です。
本章ではまず中間波動の基本を学び、その理由や役割を理解します。さらに、トレンド継続時に出現する代表的なパターン(トライアングル、ペナント、フラッグなど)と、トレンド転換時に現れる兆候(V字、W字、三尊・逆三尊など)を実例とともに紹介しています。また、チャート構造の“フラクタル性”を意識した分析方法にも踏み込み、あらゆる時間軸で波動を応用できる視点が養えます。

第8章 出来高と価格帯別出来高
チャート上で注目されがちなのは価格ですが、もうひとつの重要な情報が「出来高(できだか)」です。これは、どれだけの取引があったかを示し、価格の動きがどれほど“本気”かを測る指標です。たとえば、上昇しているのに出来高が伴っていなければ、上昇は長続きしないかもしれません。
さらに価格帯別出来高に目を向けると、特定の価格帯でどれほど取引が集中していたかが分かります。これは「その価格に注目している投資家が多い=心理的節目」だということを意味し、反発やブレイクの判断に活かせます。本章では、そうした“厚みのある価格”を見極める技術も解説され、精度の高いエントリー・エグジットの判断に繋がります。

第9章 DMI&ADX
一見難しそうなこのテクニカル指標は、実は「今の相場に力があるのか」「トレンドが生まれそうか」を判断するための有効なツールです。DMI(Directional Movement Index)は、買い勢力と売り勢力のどちらが強いかを±DIという2本のラインで表し、ADX(Average Directional Index)はトレンドの強弱を数値化します。
たとえば、+DIが-DIを上回れば買い優勢と判断でき、ADXが上昇していればトレンドが強まっていることを示します。本章では、この3本の線の役割や読み方だけでなく、どのタイミングで仕掛け・手仕舞いをすべきかも具体的に解説。計算式の意味にも踏み込んでおり、DMI&ADXを根本から理解できます。

第10章 パラボリックSAR
パラボリックSARは、売買の転換点(ドテン)を視覚的に知らせてくれるインジケーターです。チャート上に点(SAR)が表示され、価格が点を上回れば買い、下回れば売りと判断します。その特徴は、トレーリングストップの進化形として、利益確定や損切りのタイミングを自動的に導いてくれる点です。
この章では、まずルールと活用法を学び、ドテンのタイミングの見極め方を具体例で習得します。また、SARの点がどのような計算で動いているのかを理解することで、“なぜそこに出現するのか”を納得しながら使えるようになります。加速係数という要素も加わるため、設定を変えることで自分好みにカスタマイズすることも可能です。

第11章 「3×3分割投資法」
投資初心者でも実践できる戦略的な資金管理術として注目されるのが、3×3分割投資法です。これは移動平均線をベースにした大循環分析を発展させたもので、資金を3分割し、さらに仕掛けと手仕舞いを3段階で分けることによって、リスクを抑えながら効率良く利益を追求する方法です。
本章では、まず初心者向けにその基本構造を解説し、次に中級者向けの応用として相場の段階ごとの仕掛け方を示し、最終的には上級者向けの工夫や応用テクニックまで網羅されています。複雑なテクニカル分析が苦手でも、資金管理の面から堅実な投資を目指したい人には最適な内容です。

第12章 一目均衡表 上級編
日本生まれのテクニカル指標である一目均衡表は、5本の線から成り立ち、「時間」「価格」「形状」の3つの要素で相場を分析します。本章はその上級編として、単なる買いサイン・売りサインの使い方ではなく、“なぜそのようなサインが出るのか”を根本から理解する内容になっています。
特に「基準線」「転換線」「先行スパン」など5本の線の意味と、相場水準における「半値」の重要性が詳細に解説されています。また、変化日や時間論など独特の考え方も紹介され、相場の未来を“予想”ではなく“予測”するための視点が養われます。

対象読者

『真・チャート分析大全 ──王道のテクニカル&中間波動編』は、投資歴やスキルレベルにかかわらず、多様な層の読者に向けて設計された一冊です。
以下のような方々にとって、本書は特に有益な内容となっています。
- テクニカル分析を体系的に学びたい初心者
- チャートの本質を理解して取引精度を上げたい中級者
- これまでのテクニカル手法に限界を感じている上級者
- 独自理論に触れたいトレーディングマニア
- 実践的なトレードスキルを身につけたい個人投資家
それぞれの読者層に対して、本書がどのような価値を提供するのかを詳しく見ていきましょう。
テクニカル分析を体系的に学びたい初心者
これから投資を始めようとする人にとって、チャートやテクニカル分析は専門用語ばかりでとっつきにくい世界に見えるかもしれません。しかし、本書では「ダウ理論」や「エリオット波動」などの古典的な理論から丁寧に解説されており、基礎を一から学べる構成になっています。単なる知識の羅列ではなく、図解や実例が豊富に盛り込まれているため、視覚的に理解しやすいのも特徴です。
例えば、「トレンドとは何か」「なぜ移動平均線が重視されるのか」といった初歩の疑問に対しても、背景にあるロジックや実践へのつなげ方を解説。こうした体系的なアプローチにより、初心者でも無理なくステップアップしていけます。

テクニカル分析は、最初の入口こそ難しく見えますが、論理的に学べば必ず習得できます。
まずは“なぜ”を大切にする姿勢が、将来の武器になります。
チャートの本質を理解して取引精度を上げたい中級者
一通りの指標やパターンは知っているけれど、取引の精度に伸び悩んでいる――そんな中級者にとって、本書の大きな価値は「テクニカル指標の本質」に踏み込んでいる点です。ただの「サイン」に頼るのではなく、「なぜそのサインが現れたのか」「どんな相場環境なら有効なのか」といった背景まで理解することで、曖昧だった判断に確信が生まれます。
さらに、指標ごとに計算式の意味や構造を明示しているため、盲目的なトレードから卒業できます。例えば、ADXが示すのは「トレンドの強さ」であり、「方向」ではないという点など、表面的には見えにくい情報が解き明かされていく過程は、まさに“目からウロコ”でしょう。

売買サインを“使う”のではなく、“読み解く”力が中級者の壁を越える鍵です。
理屈を知れば、感覚の精度は確実に高まります。
これまでのテクニカル手法に限界を感じている上級者
長年トレードを続けてきた人の中には、これまでの手法に対して「なんとなく限界を感じる」「環境の変化に適応できていない」と思うことがあるはずです。そんな上級者にとって、本書は新たな視点と発見をもたらす一冊になります。
特に注目したいのは、小次郎講師が提唱する「コジピボ」や、神藤将男氏が体系化した「中間波動論」といった独自理論の存在です。これらは従来の教科書的アプローチを超えた、実戦志向の新しい手法であり、従来の“知識”を“知恵”へと昇華させてくれます。
また、144通りに分類された値動きパターンの整理など、分析の幅を広げる理論的な工夫も充実。マンネリ化していた分析に、刺激と深みを与えてくれるでしょう。

手法に“飽き”を感じたときこそ、理論のアップデートの好機です。
次のステージは、枠を超える発想から生まれます。
独自理論に触れたいトレーディングマニア
一般的な教科書では触れられない領域や、他の書籍ではお目にかかれない切り口に出会いたいという“トレードマニア”にも、本書は強くおすすめできます。中でも「中間波動論」や「コジピボ」は、既存の理論の再解釈とも言えるもので、まさにマニア心をくすぐる内容です。
たとえば、中間波動論では、トレンドの「初動」にこそ大きなチャンスがあることを強調しています。これは一般的な「トレンドフォロー型」の考え方とは一線を画すものであり、仕掛けのタイミングに対する新たな視点を提供してくれます。
また、ピボットの線の読み方を拡張した「コジピボ」は、相場の構造を読み解くツールとして実戦で大きな威力を発揮します。

実践的なトレードスキルを身につけたい個人投資家
理論だけでなく、実際の売買に役立つ具体的なノウハウを求める個人投資家にとっても、本書の実用性は極めて高いです。各章には、売買の事例やシナリオ、トレード戦略の解説が豊富に盛り込まれており、「知って終わり」ではなく、「使って成果を出す」ことに重点が置かれています。
たとえば、もみ合い相場での立ち回り、加速相場での仕掛け、トレンドの見極めといったテーマが、チャートとともに丁寧に展開されます。また、デイトレード向けの時間帯ごとの戦略や、FX・先物市場での注意点にも触れられており、実戦で即役立つ情報が満載です。

本の感想・レビュー

本質を学ぶ重要性
私はこれまで、移動平均線やRSIなど、いわゆる「テクニカル指標」の使い方ばかりに目を向けてきました。どのラインを抜けたら買いか、どこで売るか、そんな“表面的なサイン”だけを追い続けていたのです。しかしこの本に出会って、私の考えは大きく変わりました。
著者の小次郎講師は、テクニカル指標の「意味」に重きを置いています。つまり、指標が示しているのは単なる売買のタイミングではなく、市場の“状態そのもの”だということを強調しています。なぜその位置でサインが出るのか、なぜ今は「買い目線」といえるのか。その背後にあるロジックを知ることで、私は初めて相場の動きに納得感を持てるようになったのです。
分析の手法を鵜呑みにするのではなく、その原理を理解して初めて「使える」知識になる。まさに“本質を学ぶこと”の大切さを、この本は教えてくれました。これを読む前と読んだ後では、チャートを見る目がまるで別人のように変わったと実感しています。
中間波動が分かりやすく整理されている
私のようにチャートパターンに苦手意識を持っていた人には、この本の「中間波動」の章が特に刺さると思います。中間波動という言葉自体、あまり一般の投資書では深く解説されないのですが、本書ではしっかり一章を割いて丁寧に説明されています。
何よりありがたかったのは、各パターンが「どのようなトレンド局面で現れやすいか」が明確に分類されている点です。トライアングル、ペナント、フラッグ、ウェッジといったパターンが、なぜそういう形になるのか、どんな状況で出やすいのかが理論的に整理されていて、理解が一気に深まりました。
私はこれまで、チャートパターンを形の「見た目」だけで覚えようとして失敗してきました。しかし本書では、その背景にある市場の心理や値動きの力学がわかるようになっており、「なるほど、だからこの形になるのか」と腑に落ちる瞬間が何度もありました。
独学では得られない体系的な学びがある
テクニカル分析を独学で学ぶには限界があると感じていた私にとって、本書はまさに「道標」でした。インターネットや一般的な入門書では、個々の指標が断片的に紹介されるだけで、全体の構造やつながりが見えないまま混乱してしまうのが常でした。
この本の良いところは、古典的なダウ理論やエリオット波動といった基礎理論から始まり、現代的な分析技術や独自理論「コジピボ」までを順序立てて解説してくれている点です。まるで講座を受けているような感覚で、理解がすんなりと頭に入ってきます。
また、各理論が単独で紹介されるのではなく、どう相互に関連し、どのような場面で活用すべきかという「応用」の部分にまで踏み込んでいるのが印象的でした。私のように「何から手をつけていいかわからない」と感じていた人には、最初の一冊として強くおすすめしたい一冊です。
「コジピボ」は使いやすく即実践できた
私は普段、短期トレード中心に活動している個人投資家です。そんな私にとって「コジピボ」の存在は衝撃でした。これまでいくつものインジケーターを試してきましたが、ここまで明確に仕掛けと手仕舞いのポイントを示してくれる手法にはなかなか出会えません。
コジピボは、前日の終値を基に算出された6本の線で構成され、トレンドの方向性をビジュアル的に把握できます。ラインの意味がしっかりと理論的に説明されているので、安心して使えるのも大きな魅力です。しかも、計算式の意味まで丁寧に解説されているので、単なる“トレードの道具”ではなく“考え方”としても使えます。
導入してからというもの、私はトレード時の迷いがかなり減りました。勝率が上がったことよりも、まず精神的なブレが減ったのが一番の収穫です。即実践できるというだけでなく、継続的に使って成長できるツールだと感じています。
一目均衡表の理解が格段に深まった
私はこれまで一目均衡表に対して苦手意識を持っていました。線が多すぎて複雑に見え、どこをどう見ればいいのか分からないというのが正直なところでした。ところがこの本では、各線の役割やその意味合い、構成の背景、さらには波動論・時間論・価格変動論といった一目均衡表独自の世界観まで丁寧に整理されており、少しずつ霧が晴れるように理解できていきました。
特に印象的だったのは、相場水準を「半値」と捉える考え方や、1日のチャートには膨大な情報が含まれているという哲学的とも言えるアプローチです。こうした説明を通じて、一目均衡表は単なるインジケーターではなく、相場そのものの“見取り図”なのだと感じるようになりました。以前は無理やり使おうとしても感覚で捉えきれなかったこの指標が、今では私の分析の軸になりつつあります。
ダウ理論がここまで丁寧なのは珍しい
長年、個人でトレードをしてきましたが、ダウ理論というと「価格はすべてを織り込む」「トレンドは明確なシグナルが出るまで継続する」といった抽象的な原則だけが紹介されがちで、実戦にどう活かすかが曖昧に感じていました。ですが本書では、その抽象的な理論を現実のチャートにどう当てはめ、どのようにトレンドを判断すべきかという視点で、非常に具体的に解説されています。
「3段上げ」「複数市場での確認」「出来高による裏付け」など、ダウ理論の各要素が細かく取り上げられ、理論と実践が地続きでつながっていることがよく分かりました。単に知識として覚えるのではなく、「だからこの場面で買いを仕掛ける」といった実際の行動にまで落とし込めるようになるのは、実に価値の高い経験でした。
初心者にも配慮された実例豊富な解説
私は投資初心者で、正直なところチャートの見方さえ曖昧な状態からのスタートでした。それでも、この本は安心して読み進めることができました。なぜなら、専門用語には必ず丁寧な説明が添えられていて、初学者がつまずきやすいポイントに対しても、補足や図解がしっかり入っていたからです。
特にありがたかったのは、各テクニカルの説明に実例が豊富に盛り込まれていた点です。「このようなチャートでこう動いたとき、なぜこのサインが出るのか」といった因果関係が明確なので、ただ暗記するのではなく、しっかり理解できる形で知識を定着させることができました。
読み終えた今、私は自分の判断でトレードの戦略を立てられるようになりつつあります。初心者でも自信を持って学べるように配慮された構成に、心から感謝しています。
図解と解説が豊富で理解しやすい
チャート分析の本って、文章だけが続くと正直読むのがしんどい。そんな経験が何度もありました。でもこの本は違っていました。図と文章が連動していて、とにかくわかりやすい。どこを見て、どう判断するのかというプロセスが、視覚的に整理されていてスッと頭に入ってくるんです。
さらにありがたかったのが、解説のトーンです。専門用語は当然出てくるんですが、それが一方的に書かれるのではなく、背景や意味が丁寧に解かれていくから、自然に知識として自分の中に入ってくる感じ。私はあまり数学が得意ではないのですが、計算式すら読み物として楽しめました。それはひとえに、説明が実に“噛み砕かれている”からだと思います。
まとめ

書籍『真・チャート分析大全 ──王道のテクニカル&中間波動編』は、投資初心者から熟練のトレーダーまで、すべてのチャート分析家に向けて、真の意味で「使える」テクニカルを学ぶための実践書です。理論と実務の架け橋となるような内容が、広範な読者層にとって深い学びを提供しています。
このセクションでは、読了後に得られるメリットや次の学習へのつなげ方を整理し、最後に本書の総括を行います。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれの視点から、締めくくりとして大切なポイントを紹介していきます。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、この書籍を通じて得られる主なメリットを丁寧に解説していきます。
テクニカル指標の「本質」がわかるようになる
多くの投資本は、「このサインが出たら買い」という結論だけを教えます。しかし、それだけでは再現性の高いトレードは不可能です。本書では、テクニカル指標がなぜその場所でサインを出すのかという“背景”を、数式や相場の力学に基づいて解説しています。たとえば、DMIの±DIが何を測っているのか、パラボリックSARが加速係数によって何を表現しようとしているのか、といった情報まで掘り下げています。
このように「どう使うか」ではなく、「なぜそうなるか」を理解することに主眼を置いている点が、本書の大きな特長です。結果として、相場の動きがなぜそうなったのか、自分の頭で読み解く力が自然と育ちます。
チャート分析に「立体感」が出る
本書を通じて学べる概念の一つに「中間波動論」があります。これは、上昇・下降というトレンドの“切れ目”や“継続の中継地点”に注目する分析手法です。従来のチャート分析が「始点と終点」だけを見ていたとすれば、中間波動は「その途中の流れ」にも意味を見出します。
これにより、たとえば「トライアングル」や「ペナント」といった形状が、なぜその場面で現れるのか、どういったトレンドの予兆なのかを理解できるようになります。チャートが平面的な図ではなく、相場参加者の心理が映し出された“ダイナミックな物語”として見えてくるのです。
「判断の軸」が手に入る
チャート分析における最大の悩みの一つは、「どこを見ればいいのかがわからない」という迷子状態に陥ることです。本書では、その迷いを解消するための“軸”を複数提示しています。たとえば、「ダウ理論」や「一目均衡表」のような古典的理論に加えて、小次郎講師オリジナルの「コジピボ」や「3×3分割投資法」といった独自ロジックも展開されています。
こうした分析軸を持ってチャートを見ることで、どんな相場環境においても「自分は今、何を根拠に動くべきか」が明確になります。これは、投資家にとって最も大切な「自信」と「一貫性」を支える基盤です。
トレードに「戦略性」が生まれる
本書では単にインジケーターを紹介するのではなく、それをどのように“実際の売買判断”に活かしていくかというプロセスまで踏み込んでいます。たとえば、「反動相場におけるピボットの活用法」や、「加速相場での仕掛けと撤退ポイント」など、具体的なケーススタディが豊富です。
このアプローチは、トレーダーに「戦術」ではなく「戦略」を教えるものです。場当たり的なエントリーではなく、「この状況ではこの指標が優位性を持つから、こう行動する」という一貫した判断のロジックを構築できるようになります。
経験がなくても実践しやすい“再現性”の高さ
本書は難解な理論書ではありません。用語には丁寧な解説が添えられており、初心者にも配慮された構成です。さらに、巻末にかけては実際のチャートを活用した事例分析が豊富に掲載されており、理論と実践のギャップを埋めてくれます。
これにより、「本を読んだはいいけど、どう使えばいいか分からない」という読者の不安を払拭してくれます。再現性が高く、自分のトレードルールに応用しやすい点も、大きな魅力です。

相場で継続的に勝つために必要なのは、“知っていること”ではなく、“理解し、使えること”。
この本は、その両方を手に入れるための実践的なガイドです。
読後の次のステップ
本書を読了した後は、「学びっぱなし」にするのではなく、身につけた知識と理解を土台にして、一歩一歩実践に移していくことが重要です。ただ知識を得ただけでは投資の成果にはつながりません。
ここでは、本書で得た学びをより深く定着させ、トレーダーとして実力を磨くためのステップをご紹介します。
step
1自分専用の「相場ノート」を作成する
読んで得た知識を整理し、振り返りながら実践するために、自分だけのトレードノートやチャート日記をつけることをおすすめします。たとえば、特定のテクニカル指標を使ったときのエントリー・エグジットの判断理由や、実際の結果、反省点などを記録しておくと、知識が経験として積み上がっていきます。また、時間が経ってから見直したときに、自分の成長や改善点が明確になります。
step
2実際のチャートに「引いてみる・測ってみる」
学んだ指標やトレンドライン、中間波動などを、過去チャートやリアルタイムのチャートに実際に描き込んでみることで、理論が現実の相場にどう当てはまるかを確認できます。頭で理解した内容が、視覚的な分析力に変わる瞬間です。特に、三尊やフラッグのようなパターン分析は、何度も自分の手で描いてみることで自然に見つけられるようになります。
step
3小さなトレードで「検証」する
最初から大きな資金で実践するのではなく、まずは少額で小さなトレードを繰り返し、本書で得た分析法や売買判断がどれだけ有効かを検証してみましょう。成功・失敗を問わず、その結果から何を学べたかが重要です。検証の中で、自分の相性が良いテクニカルやタイミングの取り方が明確になっていきます。
step
4他の書籍や教材と「接続」して理解を深める
本書で学んだ基礎と応用は、他のテクニカル書やマーケット解説とも非常に相性が良く、さらなる知識拡張のための土台となります。特に、本書の内容を活かす形で、ファンダメンタル分析や資金管理に関する情報を取り入れることで、総合的なトレード力の強化が期待できます。「学びの軸」があるからこそ、次に学ぶべきものが見えてきます。
step
5自分の「ルールブック」をつくる
最終的なゴールは、自分自身の売買ルールを持つことです。本書の中で紹介されたトレード手法や、状況別の対応例を参考にしながら、あなただけの“売買判断のマニュアル”を作ってみてください。「どんな相場環境で、どの指標を使い、どこで入ってどこで出るか」を明文化することで、ブレないトレードが可能になります。

テクニカル分析を“知っている”だけでは不十分。
“使えるようになる”ためには、自分の手で試し、自分の言葉で整理し、自分の判断軸を育てる。そこに進んでこそ、本当のトレーダーへの道が開けます。
総括
『真・チャート分析大全 ──王道のテクニカル&中間波動編』は、単なるチャートの読み方を教える入門書ではありません。本書は、テクニカル指標の裏にある「意味」や「背景」まで掘り下げ、相場の本質を見抜くための思考力を養うことを目的とした、非常に密度の濃い一冊です。
一般的なテクニカル分析書では、売買サインの出し方やインジケーターの使い方が解説されて終わるケースが多いですが、本書は「なぜそのサインが出るのか」「そのシグナルはどのような相場環境で効果を発揮するのか」といった根本的な理解を重視しています。これは、実際の相場で起こり得る“想定外”に対処する力を鍛えるためでもあります。
また、著者の小次郎講師と神藤将男氏が導入した独自理論である「コジピボ」や「中間波動論」は、実践的かつ革新的なアプローチとして、既存のテクニカル手法に物足りなさを感じていたトレーダーにとって新たな発見を与えてくれるでしょう。特に中間波動に関しては、相場の「転換点」や「継続の見極め」に重要なヒントが詰まっており、読み解く力を身につければ、トレードの精度が一段階引き上がります。

本書は、知識の習得だけでなく、投資家としての“自立”を目指す人にこそふさわしい一冊です。
教えられたことをただ真似するのではなく、考え、検証し、自分なりのスタイルを確立する。
この本は、そのプロセスにおける強力な羅針盤となってくれます。
テクニカル分析の勉強におすすめ書籍

テクニカル分析の勉強におすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- テクニカル分析の勉強におすすめの本!人気ランキング
- マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド
- 日本テクニカル分析大全
- 手法作りに必要な“考え”がわかる データ検証で「成績」を証明 株式投資のテクニカル分析
- 真・チャート分析大全 ──王道のテクニカル&中間波動編
- 勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析2
- テクニカル分析 最強の組み合わせ術
- ずっと使えるFXチャート分析の基本 (シンプルなテクニカル分析による売買ポイントの見つけ方)

