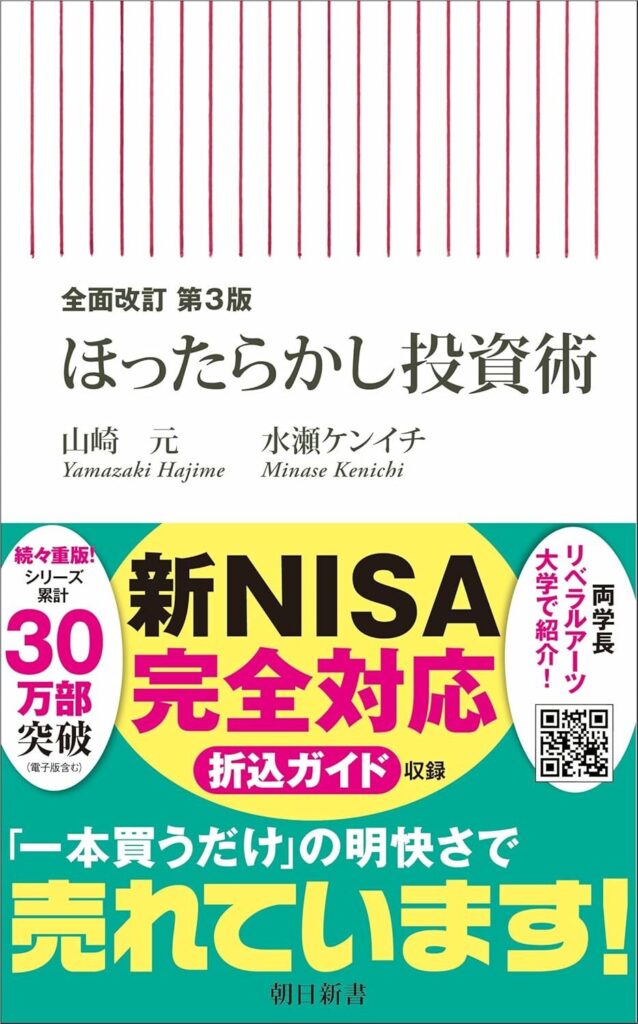
投資は難しい、時間がかかる、リスクが高い——そう思っていませんか?
『【全面改訂 第3版】ほったらかし投資術』は、そんな不安や迷いを抱える人にこそ手に取ってほしい一冊です。著者の山崎元氏と水瀬ケンイチ氏が、複雑な投資の世界から「本当に必要な方法」だけを抽出し、誰でもすぐに実践できる形にまとめました。

7年ぶりの全面改訂となる今作では、よりシンプルで実行しやすい戦略へと進化。
全世界株式インデックス・ファンドを中心に据え、iDeCoや新NISAなど最新制度をフル活用する方法をわかりやすく解説しています。
投資経験ゼロでも、「仕組みを作ってあとは放っておく」だけで、着実に資産を育てられる設計です。
時間も知識も限られている現代人にとって、資産形成は「日常生活の邪魔をしない仕組み化」がカギ。
本書は、その公式を提示し、お金の不安から解放されるための最短ルートを教えてくれます。

合わせて読みたい記事
-

-
インデックス投資について学べるおすすめの本 10選!人気ランキング【2025年】
投資の世界で「着実に資産を増やす方法」として注目を集めるインデックス投資。初心者でも始めやすく、長期的な資産形成に向いていると言われますが、実際に取り組もうとすると「何から学べばいいの?」と迷ってしま ...
続きを見る
書籍『【全面改訂 第3版】ほったらかし投資術』の書評

このセクションでは、執筆陣の経歴や信頼性、書籍全体の骨子、著者が込めた狙い、そして多くの投資家に支持される理由を、多角的に整理していきます。
情報を体系的に理解できるよう、以下の視点から深掘りしていきます。
- 著者:山崎 元のプロフィール
- 著者:水瀬 ケンイチのプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
これらのポイントを押さえることで、本書が「初心者にとっての最初の一冊」として強く推奨される背景が見えてきます。
著者:山崎 元のプロフィール
山崎 元(やまざき はじめ)氏は北海道生まれ。東京大学経済学部を卒業後、三菱商事に入社。その後、住友信託銀行、野村投信、メリルリンチ投信、UFJ総合研究所など、合計12回の転職を経験しています。この異色の経歴は、資産運用や証券ビジネス、経済分析など幅広い領域を“現場感覚”で把握する力を培いました。
楽天証券経済研究所客員研究員として数多くのレポートを発表し、テレビ・新聞・雑誌などでも活発に発言。特徴は、アカデミックな理論をベースにしつつも、それを生活者目線で解きほぐす点です。たとえば、複雑な金融商品の説明も「それは、スーパーで値札を比べるのと同じ」といった身近なたとえで語るため、専門知識がなくてもスッと理解できます。
2024年1月に惜しまれつつ逝去しましたが、遺した著書やコラムは今なお引用され、多くの投資家に影響を与え続けています。

著者:水瀬 ケンイチのプロフィール
水瀬 ケンイチ氏は、現役の会社員でありながら20年以上の投資経験を持つ個人投資家です。2005年から運営するブログ「梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー」は、日本のインデックス投資ブログの草分け的存在として広く知られています。
彼の文章は、専門用語を避けつつ、実際の運用体験をベースにしているため、初心者でも投資の全体像をイメージしやすいのが特徴です。メディア出演や他書籍への寄稿も多く、投資に関する講演や座談会でも発信を続けています。
ユニークなのは、会社員としての生活と投資を両立している点。つまり「投資が本業ではない一般人」目線からのアドバイスができることです。これは、同じ立場の読者にとって強い安心感につながります。

本書の要約
本書は、できるだけ少ない手間で、かつ堅実に資産を増やすための投資法を体系化した一冊です。軸となるのは、低コストで世界中の株式に分散できる全世界株式インデックスファンドを一本だけ選び、長期的に積み立てていくという方法です。これにより、個別銘柄の選定や頻繁な売買といった煩雑な作業を避けながら、世界経済全体の成長に乗ることができます。
本書は単なる理論書ではなく、読者が実際に投資を始められるように、証券口座の開設方法や商品選びの基準、積立設定の手順までを具体的に解説しています。さらに、税制優遇制度であるiDeCoやNISAの活用法にも触れ、どの制度から優先的に使うべきか、なぜそれが有利なのかを明快に説明しています。
また、投資を継続するうえでつまずきやすいポイントにも配慮しています。例えば「相場の下落にどう対処するか」「許容できる損失額の設定方法」など、心理面や生活設計の観点からもアドバイスが盛り込まれています。これにより、読者は“始める前”から“続けるための仕組み”まで一通り学べる構成になっています。

本書の目的
本書が目指すのは、情報過多で複雑化した投資環境の中で、誰でも再現可能な運用法を確立し、資産形成に費やす時間と労力を削減することです。著者たちは、資産運用はあくまで人生を豊かにするための手段であり、それ自体を目的化してはいけないと考えています。過度に相場の動きに一喜一憂したり、情報収集に膨大な時間をかけるのは本末転倒であり、人生の質を下げる要因にもなりかねません。
そのため、本書では「ほったらかし」にできる仕組みを作り、生活の中で投資を意識する時間を最小限に抑えることを推奨しています。市場や制度が変わっても揺らぎにくい投資哲学を持ち、淡々と続けることこそが、最終的に大きな資産を築く近道であるという考えが全編を通じて貫かれています。

人気の理由と魅力
この本が幅広い層から支持されるのは、平易な文章と実践的な内容のバランスが優れているからです。専門用語は必要最低限にとどめ、初めて投資に触れる人でも読み進められるよう配慮されています。さらに、抽象的な理論にとどまらず、実際の証券会社名や商品名が登場し、今すぐ行動に移せる具体性があります。
また、2024年から始まった新NISAをはじめ、最新の制度や市場環境の変化にも対応している点も大きな魅力です。金融制度は数年ごとに改正されるため、古い知識だけで投資を続けることはリスクになります。本書はそのリスクを避けるために、最新情報を踏まえたアプローチを提示しています。
さらに、提案している投資法は年齢や資産規模を問わず応用できる普遍性があります。若い世代が資産形成のスタートとして使うことも、高齢者が資産の維持や運用に使うことも可能です。全世界株式への分散投資は、特定の地域や業種に依存しないため、長期的な安定性が期待できます。こうした汎用性と持続可能性が、長く読み継がれる理由の一つです。

本の内容(目次)

この書籍は、投資経験の有無を問わず、最小限の手間で資産を着実に育てるための実践書です。章ごとに役割が明確に分かれており、初めての人でも迷わずステップを踏めるよう構成されています。
以下の章立てを順に解説していきます。
- 第1章 ほったらかし投資と人生のお金
- 第2章 ほったらかし投資の簡単!「実行マニュアル」
- 第3章 実際に始めてみよう!
- 第4章 インデックス運用の基礎知識―納得して投資するために
- 第5章 「ほったらかし投資」 実践の勘所
- 第6章 よくある質問にお答えします
これらを押さえることで、本書の全体像と狙いがつかめ、投資を実際に始めるための「地図」と「道案内」を同時に得られます。
第1章 ほったらかし投資と人生のお金
この章では、資産運用を単なるお金儲けの手段ではなく、「人生の質を高めるための道具」として捉える姿勢が示されています。株式市場は短期的には上がったり下がったりしますが、長期で見れば経済成長と企業活動の拡大に伴い右肩上がりになる傾向があります。この性質を利用し、日々の値動きに振り回されずに資産を育てるのが「ほったらかし投資」です。
著者たちは、資産運用の複雑さや個別銘柄の選定に時間を費やす必要はないと断言します。理由は、プロの投資家であっても市場平均を長期的に上回るのは極めて難しいからです。むしろ、低コストのインデックスファンドを使って市場全体に投資する方が、コスト削減効果と分散効果により、安定した成果を得られます。
さらに、この投資法は年齢や資産規模を問わず適用可能です。若者も高齢者も、投資経験が浅い人もベテランも、同じアプローチで成果を狙えるのは大きな特徴です。「お金のストレス」から解放されることで、趣味や家族、健康など本当に大切なことに時間とエネルギーを使えるようになると説かれています。

第2章 ほったらかし投資の簡単!「実行マニュアル」
この章は、初心者が迷わず投資を始められるように、6つのステップで具体的な実行方法を示しています。最初に強調されるのは「できるだけ早く始める」ことです。時間を味方につけることで、複利の力が資産を大きく育てます。たとえば、同じ利回りでも20歳から始める場合と40歳から始める場合では、最終的な資産額に大きな差が生まれます。
次に、自分が耐えられる損失額を決め、それ以上はリスクを取らないというルールを設定します。残りは「無リスク資産」として安全な商品(例:変動金利型10年満期の個人向け国債)に置きます。そして、リスクを取る部分は全額「全世界株式インデックスファンド」に一本化します。これは、世界中の株式市場に分散投資することで、特定の国や業種のリスクを抑える狙いがあります。
さらに、iDeCoやNISAなどの税制優遇制度を積極的に活用することで、運用益にかかる税金を最小限に抑えられます。制度は複雑に見えますが、本書ではどの制度から使うべきかを明確に示しており、迷いなく行動できます。最後に、積立投資を正しく理解し、相場の上下にかかわらず一定額を継続投資する「ドルコスト平均法」の効果が解説されています。

第3章 実際に始めてみよう!
ここでは、実際の投資商品の選び方と証券口座の開設方法が詳細に説明されています。著者が示す「ファイナルアンサー」としての銘柄は、低コストかつ信頼性の高い全世界株式インデックスファンドです。選定の際には、信託報酬(運用管理費用)、純資産総額、インデックスとの乖離の小ささが重要な判断基準になります。
証券会社の選び方についても比較表が掲載され、楽天証券、SBI証券、マネックス証券の特徴が整理されています。例えば、楽天証券では楽天ポイントを投資に回せる、SBI証券はTポイントやVポイントが貯まるなど、日常生活と連動したメリットも紹介されています。
実務面では、ネット証券での口座開設から入金、ファンドの購入、積立設定までの流れを写真や画面キャプチャを使って解説。投資初心者でも、指示通りに操作すれば数日で投資がスタートできるようになっています。また、iDeCo口座開設時の注意点やおすすめファンドも明記されており、年金制度との組み合わせ方も学べます。

第4章 インデックス運用の基礎知識―納得して投資するために
この章では、インデックス運用の仕組みとその強みを体系的に学びます。インデックスとは、市場全体の動きを数値化した「ものさし」のようなもので、例えばアメリカのS&P500や日本のTOPIXが有名です。これに連動する投資信託を購入することで、個別銘柄を選ばなくても市場全体に投資できます。
重要なのは、どのインデックスを選ぶかです。「世界株」「S&P500」「先進国株」などには、それぞれ構成国や銘柄数、為替の影響などの違いがあります。著者は、投資対象が広く、分散効果の高いものほど長期運用に向いていると解説します。
また、インデックス運用が優れている理由として、低コストで市場平均を得られること、頻繁な売買による課税や手数料を避けられること、そして運用の予測性が高いことが挙げられます。一方で、短期的には市場全体の下落から逃れられないなどの欠点も説明されます。こうした「良い面」と「注意点」の両方を知ることで、納得して長期投資を続けられるようになります。

第5章 「ほったらかし投資」 実践の勘所
ここでは、長期投資を継続するために必要な心構えや注意点が語られます。
特に重要なのは、投資の三原則である「長期・分散・低コスト」を理屈として理解し、それを自分の中で納得する(腹落ちさせる)ことです。市場が急落したときに慌てて売ってしまうのは、原則の理解が不十分だからです。この章では、リーマンショックやコロナショックといった過去の急落事例を振り返り、原則を守った場合の結果を具体的に示しています。
また、投資を複雑化しすぎないことの重要性も指摘されています。商品を増やしすぎると管理が難しくなり、パフォーマンスの低下や不要な売買につながります。必要最小限の構成を保ち、余計な動きを避けることが、長期的な成功への近道です。

第6章 よくある質問にお答えします
最後の章では、読者が実践中に抱く疑問をQ&A形式で解消します。例えば、「ほったらかし投資でFIREは可能か?」という質問には、リターンの期待値や生活費の見積もりを踏まえた現実的な答えが示されます。「まとまったお金は一括投資と分割投資どちらがよいか?」では、統計的には一括投資の方が期待リターンは高いが、心理的な負担を減らすために分割投資も有効といったバランスの取れた説明がなされています。
また、「バランスファンドは向いているか?」「証券会社が破綻したらどうなるか?」といった実務的な不安にも触れています。さらに、「外国債券のインデックスファンドを勧めない理由」や、「全世界株式は日本を含むか除くか」という細かい選択肢の比較も解説されています。
為替ヘッジの有無や、インデックス投資と環境問題(ESG投資)との関係など、より専門性の高いテーマにも踏み込み、初心者だけでなく中級者にも役立つ内容になっています。読者はここで、自分に必要な判断基準を確立できます。

対象読者

本書は、投資に関してまったくの初心者から、ある程度経験はあるが「もっと効率的に資産形成を進めたい」と考えている人まで、幅広い層に向けて書かれています。
特に、次のようなタイプの方にとって有益な内容です。
- 初心者で投資を始める一歩を探している人
- 資産運用に手間や難しさを感じている人
- iDeCo・NISAなど制度を活用したい人
- 長期的な資産形成を目指す人
- 投資にかける時間や手間を省きたい人
これらの読者像ごとに、本書がどのように役立つのかを具体的に見ていきましょう。
初心者で投資を始める一歩を探している人
投資を始めたいと思っても、「何から手を付ければいいのか分からない」「ニュースやネット情報が多すぎて混乱する」という壁にぶつかる人は少なくありません。
特に初めての投資では、株や債券、投資信託などさまざまな選択肢があり、それぞれメリット・デメリットがあるため、選択の段階でつまずくケースが多いのです。本書はそうした迷いを減らすために、数ある方法の中から「インデックスファンド」という1つの手段に焦点を絞り込み、最もシンプルで再現性の高いアプローチを提案しています。
著者は、複雑なテクニカル分析や銘柄選定を避け、投資の入口で必要な知識を最小限に抑えることで、「まず始めてみる」という行動に移りやすくしています。また、机上の理論にとどまらず、著者の実際の投資経験や数字を用いた事例も多く掲載されており、現実的で実践的な学びが得られる構成になっています。

資産運用に手間や難しさを感じている人
多くの人が資産運用を難しいと感じる理由の一つは、選択肢の多さです。株式や投資信託、ETF、不動産投資など、手法は数え切れないほどあり、それぞれに異なる知識と判断が求められます。さらに、「どの銘柄を選べばいいのか」「いつ売ればいいのか」といった意思決定は、経験の浅い個人投資家にとって大きなストレスです。
本書が提案する「ほったらかし投資」は、このストレスを最小限に抑える方法です。あらかじめ運用方針を決め、定期的に積み立てるだけなので、銘柄の選別や頻繁な売買は不要。忙しい会社員や育児中の方でも、日々の生活に負担をかけずに資産運用を続けられます。
また、この方法は「やるべきこと」と「やらなくていいこと」が明確なので、投資の世界にありがちな情報過多の状況に振り回されることもありません。複雑な戦略を練る必要はなく、シンプルなルールを守るだけで長期的な成果が期待できるのです。

iDeCo・NISAなど制度を活用したい人
投資で成果を出すには、単に運用するだけでは不十分です。利益にかかる税金をどれだけ減らせるかという「制度活用」も、結果に大きな差を生みます。
本書では、iDeCoや新NISA、つみたてNISAといった税制優遇制度の仕組みを、初心者でも理解できるように図解と具体例で丁寧に解説しています。また、「どの制度から優先的に利用すべきか」「制度の中でどの商品を選ぶと効果的か」といった実践的な優先順位や組み合わせの方法も紹介されています。
この知識を活用すれば、同じ運用成績でも手元に残る金額を大きく増やすことができ、長期的な資産形成における複利効果を最大化できます。まさに「税制を味方につけた投資」が可能になるのです。

長期的な資産形成を目指す人
短期間で利益を狙う投機的な手法は、偶然の要素が大きく、再現性が低いものです。たとえ一度うまくいっても、同じ成功を繰り返すのは困難です。対して、本書が提案する長期投資は、何十年にもわたってコツコツと資産を積み上げるアプローチです。
この方法の最大の武器は「複利効果」です。例えば、100万円を年利5%で運用すると、1年後には105万円になりますが、その翌年は元本100万円だけでなく、増えた5万円にも利息がつきます。これが雪だるま式に膨らみ、長期間続けるほど成長スピードが加速します。
また、長期投資は一時的な景気後退や株価の下落にも耐えられるよう設計されており、短期の値動きに振り回されない精神的な安定も得られます。本書では、景気循環の中で投資を継続する重要性や、感情に左右されないための思考法も紹介しています。

投資にかける時間や手間を省きたい人
現代は仕事、家庭、趣味と、毎日が忙しく過ぎていきます。そんな中で、日々の株価チェックや経済ニュースの分析に時間を割くのは現実的ではありません。特に初心者は、情報を集めれば集めるほど混乱し、かえって行動できなくなることもあります。
本書の投資法は、一度仕組みを作れば、その後の管理は最小限で済むように設計されています。例えば、投資銘柄や積立額を決めたら、自動積立設定を行い、あとは年に数回のリバランス(資産配分の調整)をするだけです。これにより、他の時間を自分のやりたいことに充てながら、着実に資産を増やせます。
さらに、「動かない」こと自体が、余計な売買によるコストや失敗のリスクを避ける最大のポイントになります。本書では、この「放置のメリット」も具体的な事例とともに解説しており、忙しい人ほど実践すべき投資法であることが分かります。

本の感想・レビュー

明快な「ほったらかし投資」の定義で迷いが消える
読み始めて最初に感じたのは、この本がしっかりとした“軸”を持っているという安心感でした。著者たちは、ほったらかし投資の定義を冒頭から明快に示し、その背景や経緯まで丁寧に説明してくれます。「最善の運用に限りなく近づけつつ、個人が無理なく継続できる方法」という定義は、単なる耳障りの良い言葉ではなく、実際の投資経験や金融理論に基づいたものであることが伝わってきます。
さらに印象的だったのは、この定義の中で「誰でも同じ方法でよい」という潔い結論に至っている点です。年齢や投資経験、運用額の大小に関係なく、同じ手法が通用する理由が理路整然と語られており、読むうちに「これなら迷わず進められる」と確信できました。インデックスファンドを使う理由や、そのメリットがシンプルな言葉で解説されているので、初心者でも納得感を持って受け入れられます。
この章を読んでから後のページを進めると、すべての情報が一本の道筋につながっているように感じられます。投資の知識が断片的に積み上がるのではなく、しっかりと定義に基づいて体系的に整理されるので、読み進めるほど理解が深まっていく感覚が得られました。
改訂版ならではの“実行マニュアル”で実践しやすい
改訂版を手に取ってまず驚いたのは、ただの知識本ではなく、「そのまま真似すれば投資を始められる」実用性が詰まっていることです。特に“実行マニュアル”の章は秀逸で、資金をどう振り分けるか、リスク資産と無リスク資産の割合をどう決めるかといったポイントが、迷いなく決断できる形で示されています。
また、各ステップが論理的な順番で並び、なぜその手順を踏むのかが明確に説明されています。たとえば、投資を始める前に「許容できる損失」を決める重要性や、その具体的な算出方法が書かれていることで、精神的な準備まで整えられる構成になっています。
過去の版では複数の選択肢を提示していた部分も、今回は結論を一本化しており、情報がよりシンプルで再現性の高い形になっているのが特徴です。読みながら自然と「自分はこの順番で行動すればいい」とイメージできるので、知識だけでなく行動に直結する本になっていると感じました。
コスト・純資産・乖離で銘柄選びが具体的に
銘柄選びのパートは、この本の中でも特に実務的な価値が高いと感じました。多くの投資本では「低コストのファンドを選ぶ」といった大まかな指針しか示されないことが多いのですが、この本ではさらに踏み込み、コスト、純資産総額、インデックスとの乖離という3つの基準を具体的に提示しています。
それぞれの基準について、数値の見方や評価の仕方が丁寧に解説されているので、「なぜこれが大事なのか」を腹落ちさせた上で判断できます。単に「安いから良い」という表面的な理解ではなく、運用の安定性や信頼性まで考慮した基準が提示されているため、初心者が自己流で迷走するリスクを避けられるのも大きな魅力です。
特に、インデックスとの乖離の説明では、「どの程度の差なら許容範囲か」という具体的な目安が示されており、判断に迷う余地を最小限にしてくれます。これにより、投資対象を選ぶ際の不安が大きく減り、自分の選択に自信を持てるようになりました。
具体的な証券会社別の口座開設手順が親切
投資を始めるとき、多くの人が最初につまずくのが口座開設のステップだと思います。この本では、楽天証券、SBI証券、マネックス証券といった主要ネット証券ごとに、特徴や強み、注意点を整理した上で、開設の手順をわかりやすく解説してくれています。
特にありがたかったのは、説明が単なる手順書ではなく、途中で押さえておくべきポイントや便利なサービスにも触れている点です。これにより、ただ口座を作るだけでなく、その後の運用にもスムーズにつなげられる準備が整います。
画面操作や必要書類の説明も整理されているため、ネット証券の口座開設が初めてでも迷わず進められます。読んでいるうちに「この通りにやれば間違いない」という安心感が得られ、手を動かすハードルが一気に下がる構成でした。
初心者が抱きがちな疑問に丁寧に答えるQ&A
Q&Aの章を読んでいると、自分が投資を始める前に抱いていた不安や疑問が、そのままリストになって並んでいるように感じました。まとまった資金を一括で入れるべきか、段階的に入れるべきかといった投資のタイミングに関する悩みや、証券会社が破綻したときに自分の資産は安全なのかという心配、外国債券がインデックス投資の選択肢として適していない理由など、投資初心者が必ず通る疑問が網羅されています。
特に印象的だったのは、著者が答えを提示するだけでなく、その根拠や背景を必ず添えてくれている点です。単なるFAQではなく、質問に関連する知識や視点も自然に身につく構成になっています。そのため、読み終えた後には単に「答えを知った」という感覚だけでなく、「自分でも判断できる」自信が生まれます。この章を読むことで、投資に対する漠然とした不安が徐々に小さくなっていきました。
「続ける」ための工夫や心構えが背中を押す
投資の世界では「始めるよりも続けることの方が難しい」と言われますが、この本はその難しさを真正面から扱っている点が好印象でした。特に、「億劫さ」をどう克服するかという視点が新鮮で、精神面と実務面の両方から継続のコツが示されています。
著者は、複雑な仕組みを作らないこと、頻繁に売買を行わないこと、そして一度決めた方針を安易に変えないことを強調します。これらはシンプルでありながらも、感情やニュースに左右されやすい現実の投資環境では、意識しないとすぐに崩れてしまう要素です。
さらに、「続けるためには、自分が納得できる理由と仕組みを持つことが重要」というメッセージが心に残りました。この章を読んだ後は、自分の投資計画に対して「これなら長く続けられる」という確信が持てるようになり、背中を押された感覚があります。
長期・分散・低コストの哲学がシンプルに伝わる
本書の中核を成すのは、やはり「長期」「分散」「低コスト」という三原則です。これらは投資の基本として知られてはいますが、この本では単なる格言としてではなく、実際の投資にどう影響し、どう機能するのかを筋道立てて解説しています。
「長期」は、時間を味方につけることで市場の変動をならし、資産を着実に成長させる考え方として説明されます。「分散」は、地域や資産クラスを広く持つことでリスクを和らげる方法として描かれます。そして「低コスト」は、運用の成果を削らないための必須条件として語られ、その具体的な効果まで数字を交えて理解できる構成です。
読み終えたときには、この三原則が単に守るべきルールではなく、投資を迷わず続けるための羅針盤だと感じられました。難しい理論を噛み砕き、生活の延長線上で捉えられるようにしてくれている点が、この本の大きな強みです。
過去の環境変化にも対応し “今” に強い構成
この本は単に理論や手法を語るだけでなく、過去の経済環境の変化とそれへの対応まで含めて説明しています。老後2000万円問題や新型コロナによる市場の急落・急反発といった出来事が、ほったらかし投資にどのような影響を与えたのかを具体的に振り返っています。
これらの事例を通じて、相場の急変や社会的な不安に直面したときでも、ほったらかし投資の原則が有効であったことが確認できます。この実績は、これから先の未知の変化に対しても揺らぎにくい安心感を与えてくれます。
理論的な正しさだけでなく、実際の市場で試され、結果を残してきた方法であることがわかるため、「今この瞬間から使える方法」として信頼できる構成になっています。
まとめ

ここまでで紹介してきたように、本書は、投資初心者から経験者まで、幅広い層にとって役立つ一冊です。単に投資手法を解説するだけではなく、合理性の裏付けや最新の制度対応、実践に必要なステップまで網羅しており、読後すぐに行動へ移せるのが特徴です。
このセクションでは、最後に内容を整理しながら、読者が得られる効果や次に取るべき行動を明確にしていきます。ここで扱うテーマは以下の3つです。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、本書を通じて得られる代表的なメリットを詳しく見ていきます。
投資方針が明確になる
多くの人が資産運用で失敗するのは、最初に「どの方向へ進むべきか」を定めないまま動き出してしまうことにあります。本書では、インデックス投資を中心に据えた明快な方針が提示されており、複数の選択肢で迷う時間を排除できます。さらに、著者が過去の経験や検証をもとに結論を一本化しているため、読者は「何を信じて、どう動くか」を迷うことなく決められます。
インデックス運用の合理性を理解できる
インデックス投資は、株式市場全体の動きを反映する指数に連動する運用方法です。本書では、その優位性を単なる理論ではなく、歴史的な実績やデータ分析を交えて解説しています。これにより、「なぜこの方法が有効なのか」を腹落ちさせた上で実践でき、相場の変動時にも動揺しにくくなります。
制度を最大限に活用できる
新NISAやiDeCoといった制度は、うまく使えば税制面で大きなメリットを得られますが、仕組みや条件は複雑です。本書では、初心者でも理解しやすいよう制度の特徴を整理し、どう組み合わせれば効果的かを具体的に示しています。結果として、節税効果を最大限に活かしながら資産形成を進められるようになります。
相場変動に振り回されずに続けられる
投資を途中でやめてしまう大きな原因は、価格の上下による心理的なストレスです。本書は、あらかじめ相場変動を前提にした「ほったらかし」の仕組みを作ることで、この問題を根本から解消します。年に数回の確認だけで済むため、日常生活にほとんど影響を与えずに長期投資を続けられます。

読後の次のステップ
本書を読み終えた時点で、あなたは「ほったらかし投資」を始めるための理論と方法を手に入れています。しかし、資産形成は知識を得ただけでは進みません。大切なのは、学んだ内容を自分の生活や環境に落とし込み、継続できる仕組みを作ることです。
ここからは、読後に実践すべき具体的なステップを紹介します。
step
1投資口座を開設する
知識があっても、行動に移さなければ資産は動きません。本書のガイドに従って、まずは証券会社の口座を開設します。楽天証券、SBI証券、マネックス証券など、それぞれの特徴を理解し、自分の生活スタイルに合った金融機関を選びましょう。開設手続きはオンラインで完結し、想像以上に短時間で完了します。
step
2積立設定を開始する
投資の肝は「続けること」です。口座開設後は、毎月自動で積立が行われるように設定します。初めから大きな金額で始める必要はなく、少額からでも十分です。自動化することで、日々の相場やニュースに影響されず、長期的な資産形成のリズムを作れます。
step
3定期的なモニタリングの習慣をつける
ほったらかし投資といっても、完全放置ではなく年に1〜2回は運用状況をチェックします。ここでは利益や損失を気にするのではなく、計画通りに進んでいるかを確認します。この確認作業は、方向性のズレを早期に修正するための安全弁として機能します。

総括
『【全面改訂 第3版】ほったらかし投資術』は、投資の世界における複雑さや心理的ハードルを取り払い、誰もが実践できる「再現性の高い資産運用法」を示した一冊です。著者の山崎元氏と水瀬ケンイチ氏は、過去の版からさらに内容を精緻化し、あらゆる世代・立場の投資家が同じ方法で成果を得られるよう、方針を一本化しました。その結果、この本は投資の初心者だけでなく、経験者にとっても有用な「公式マニュアル」としての完成度を高めています。
本書の強みは、理論と実践が密接に結びついている点にあります。単にインデックスファンドの優位性を説くだけでなく、商品選びから積立設定、iDeCoや新NISAといった制度活用まで、具体的な手順を示しているため、知識を得たその日から実行に移せる設計です。さらに、過去の市場変動や制度改正に対応した最新情報を盛り込み、「いま始めるべき投資法」としての信頼性を確保しています。
また、本書は単なる投資解説書にとどまらず、「お金を増やすことは手段であり、目的はより良い人生を送ること」という哲学を一貫して伝えています。資産形成の効率を高めることで、時間や心の余裕を生み出し、それを人生の豊かさにつなげる。この価値観が全編に通底しており、読み終えたときには、単にお金の知識だけでなく、自分の生き方やライフプランを考えるきっかけも得られるはずです。

最終的に、本書は「知っているかどうか」が将来の資産額を大きく左右する現実を示し、その知識を誰もが理解しやすい形で提供しています。
投資における最も大きなリスクは「始めないこと」だと気づかせてくれる一冊であり、その意味で、手元に置いて繰り返し参照したくなる実用書です。
インデックス投資について学べるおすすめ書籍

インデックス投資について学べるおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- インデックス投資について学べるおすすめの本!人気ランキング
- 【全面改訂 第3版】ほったらかし投資術
- JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則
- 経済評論家の父から息子への手紙
- ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第13版> 株式投資の不滅の真理
- 敗者のゲーム[原著第8版]
- インデックス投資は勝者のゲーム──株式市場から確実な利益を得る常識的方法
- サイコロジー・オブ・マネー 一生お金に困らない「富」のマインドセット
- ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質
- 投資と金融がわかりたい人のための ファイナンス理論入門
- 図解でわかる ランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて

