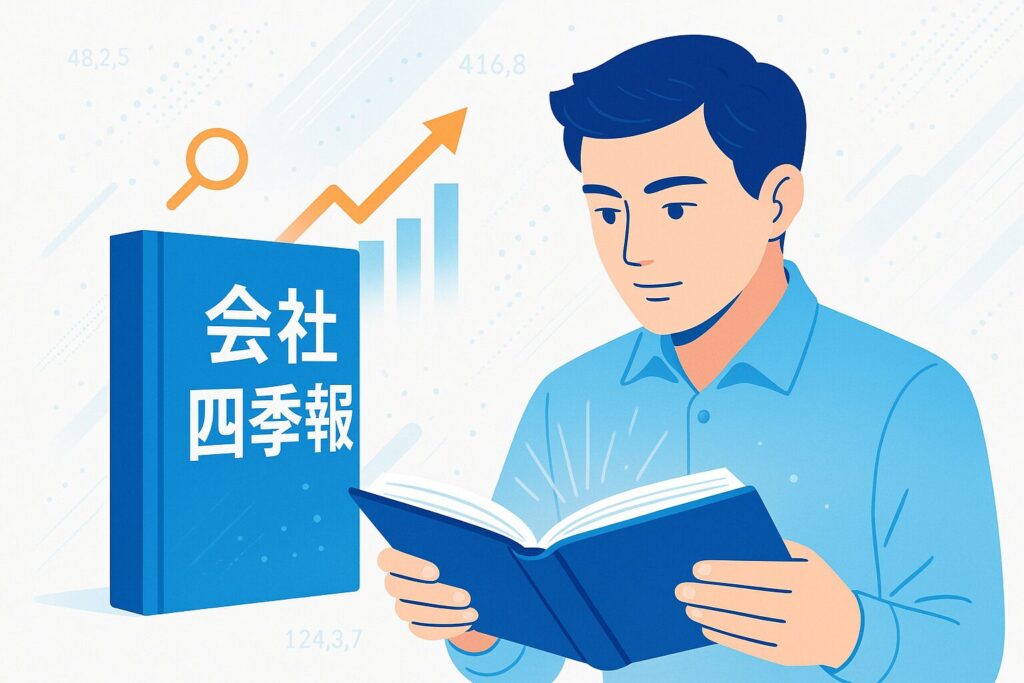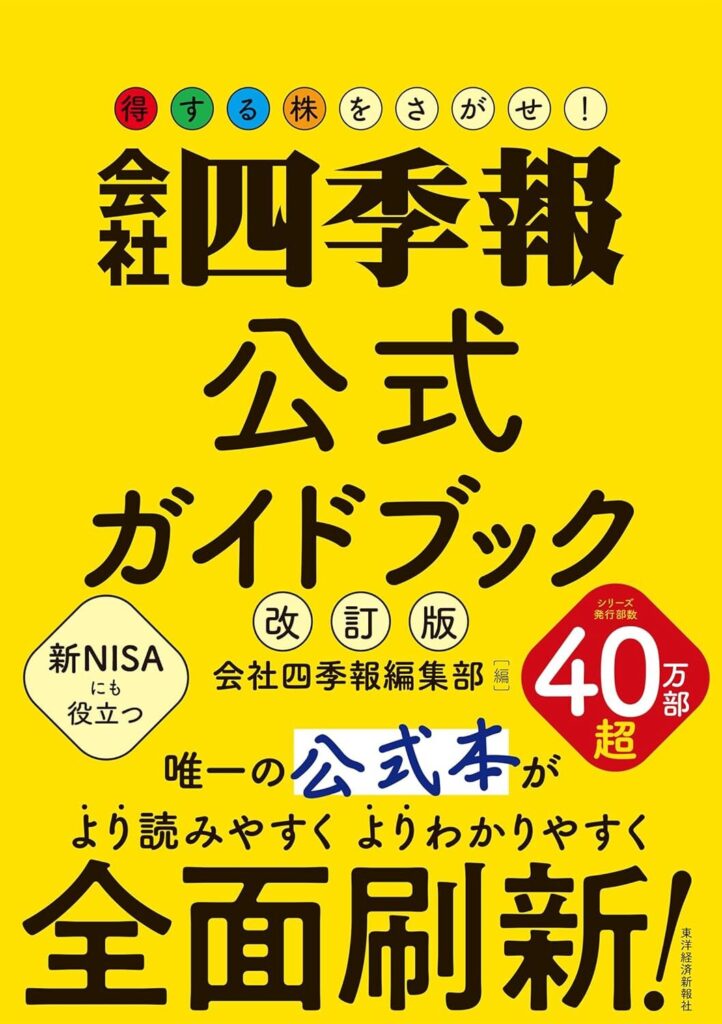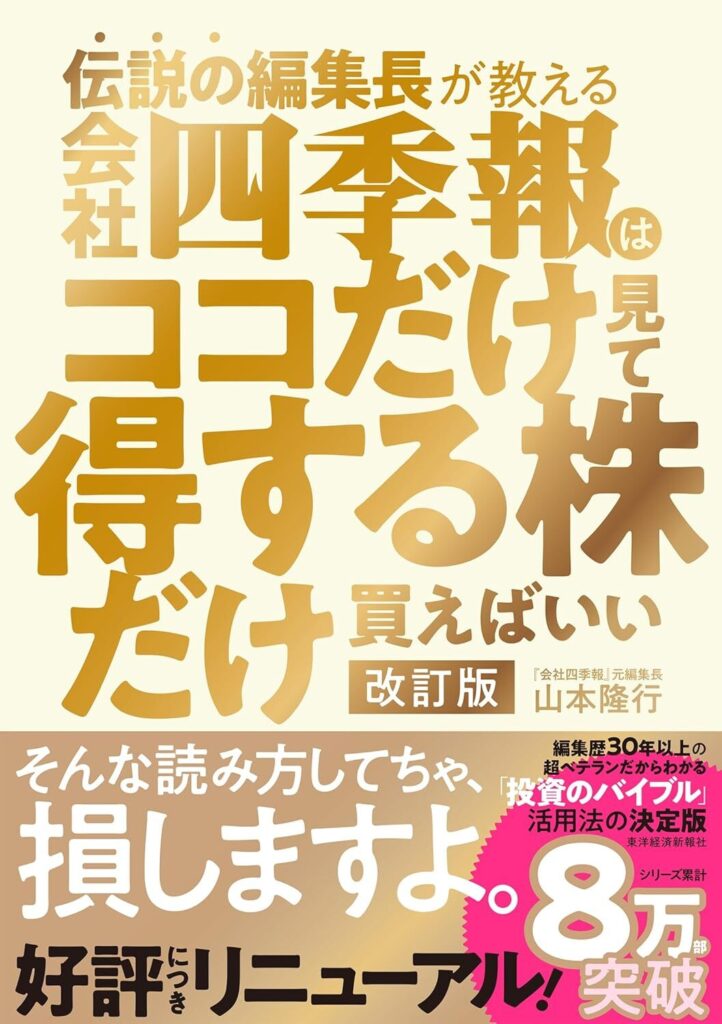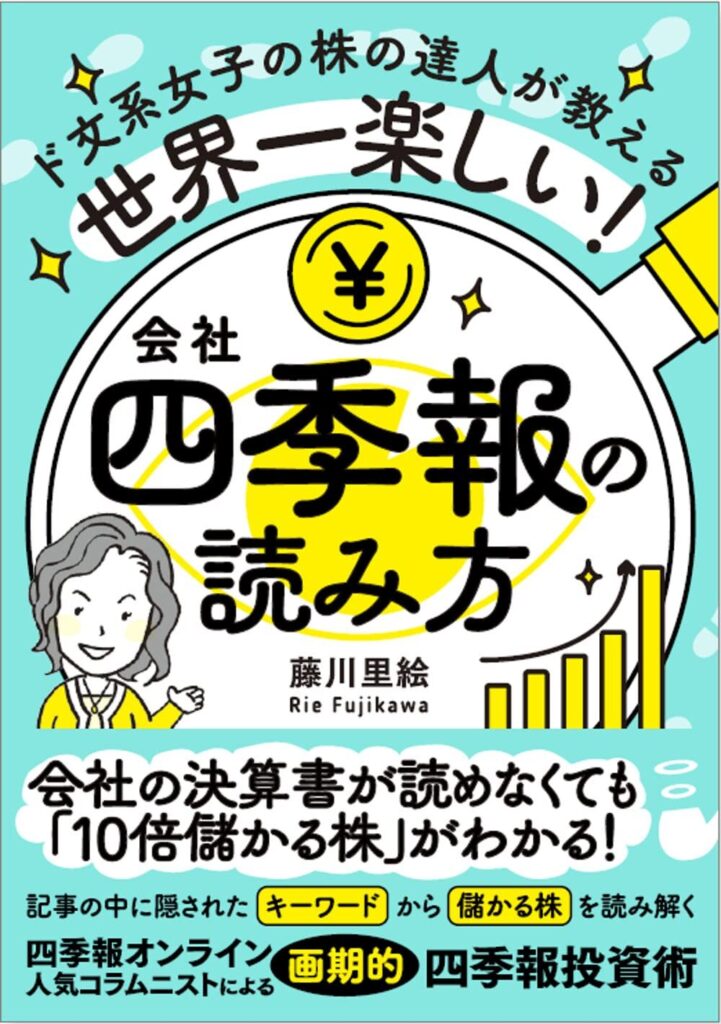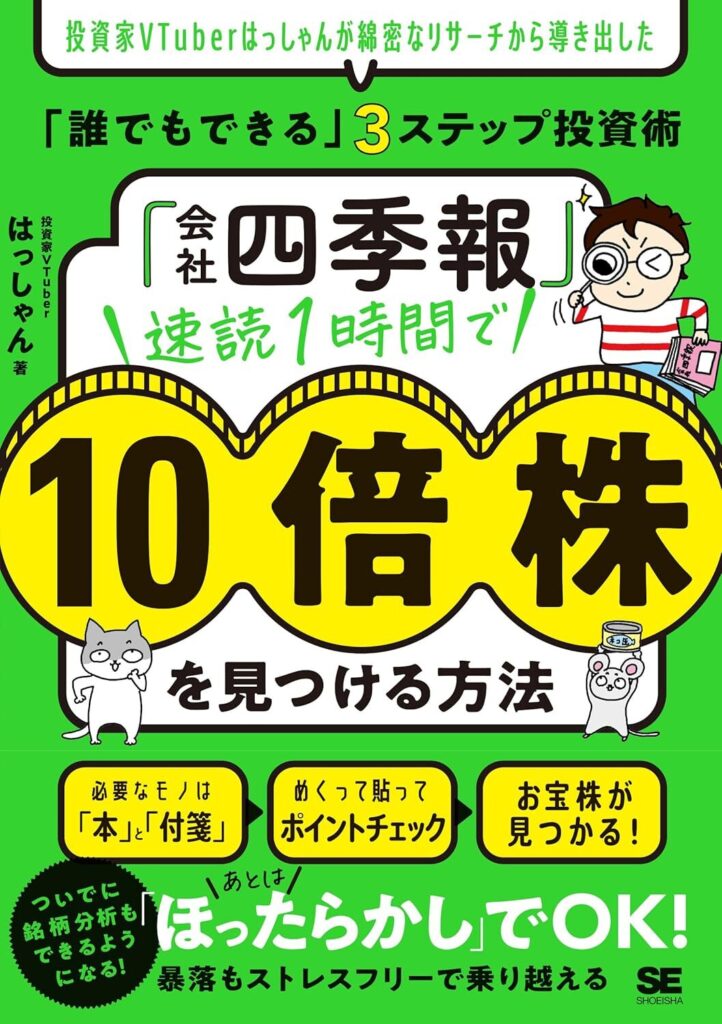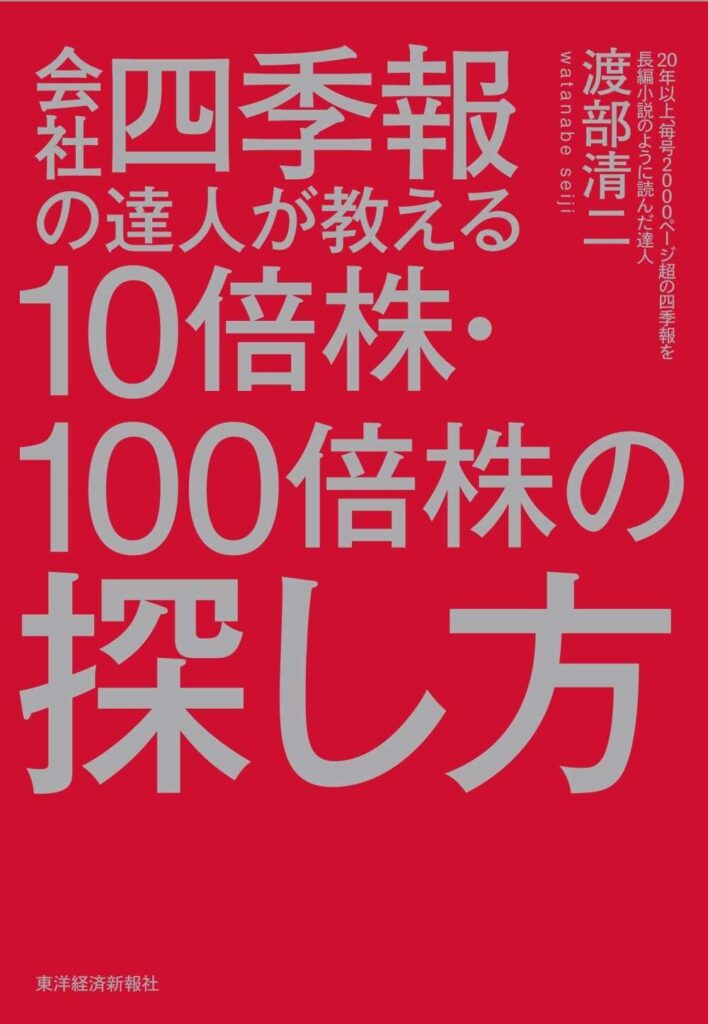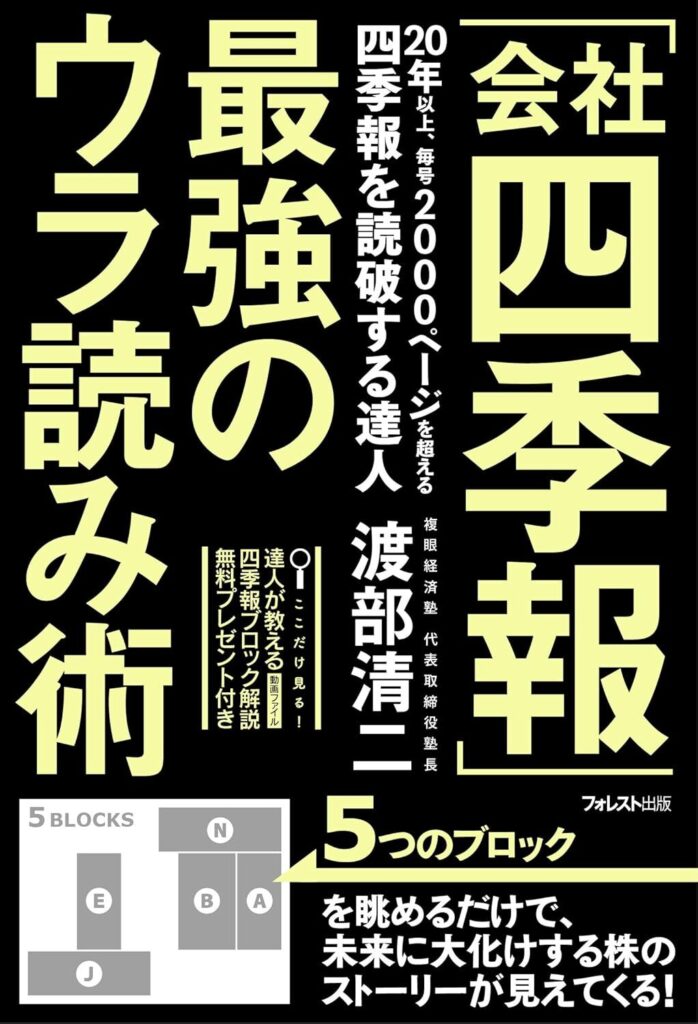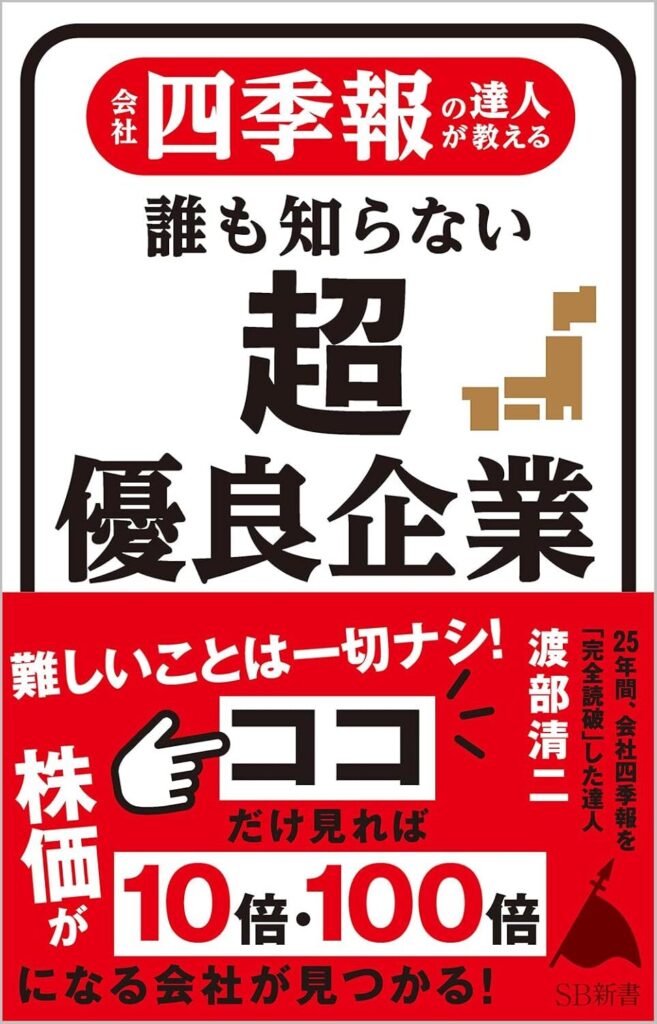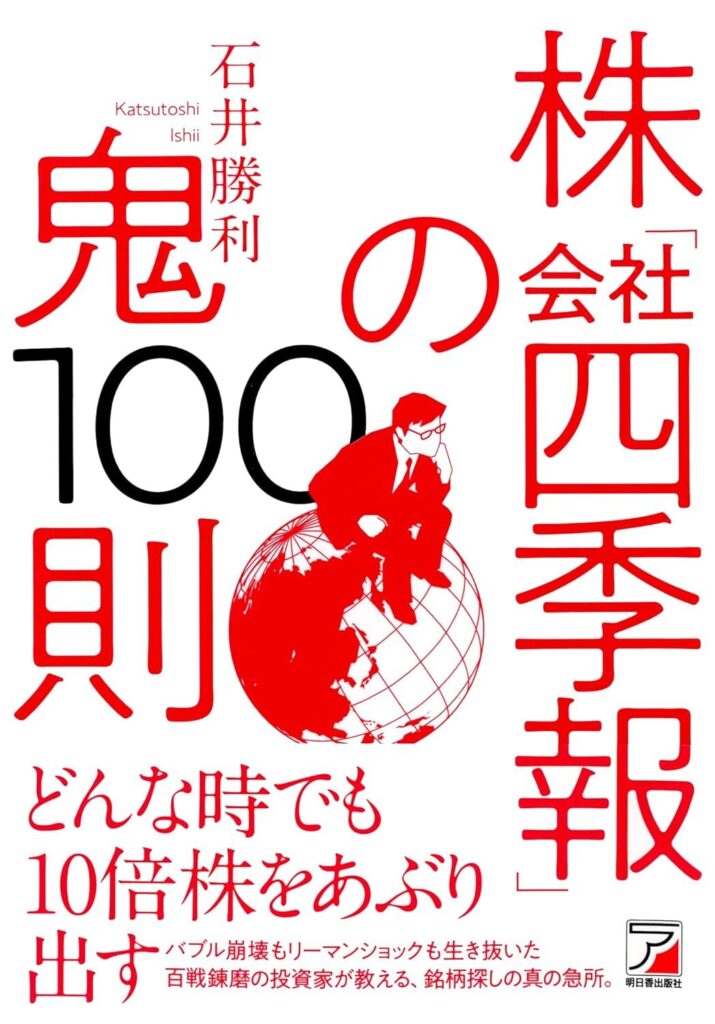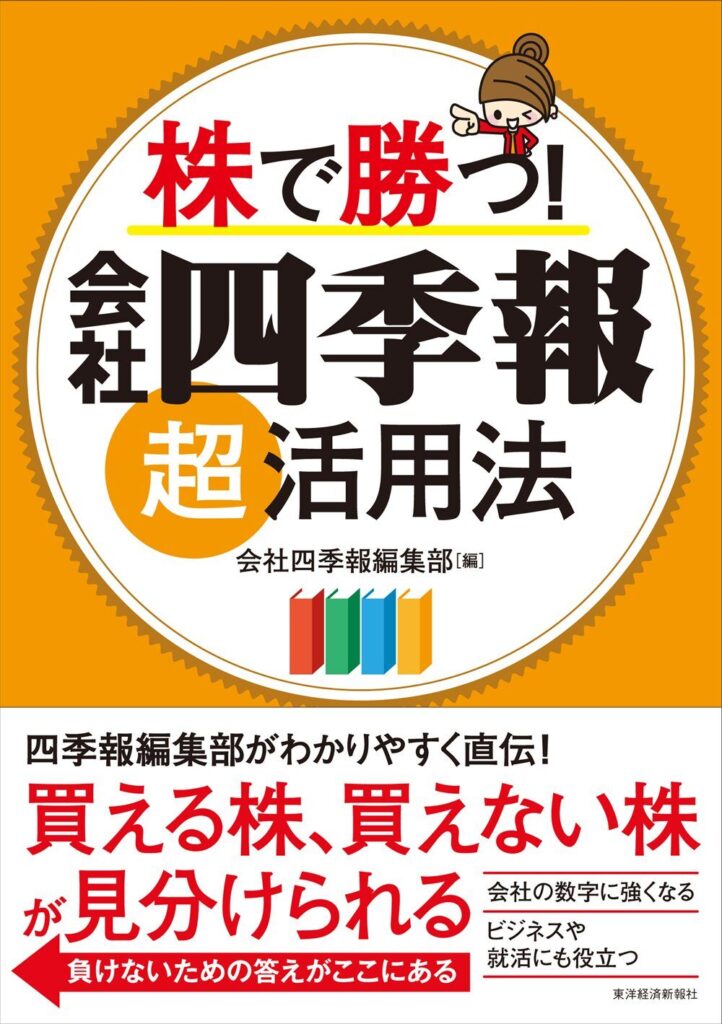「会社四季報を買ってみたものの、ページを開いても何が書いてあるのかさっぱり分からない…」
そんな悩みを抱えている投資初心者は少なくありません。四季報は上場企業の情報がぎっしり詰まった、まさに“投資家のバイブル”ともいえる存在ですが、その情報量の多さや独特の表記に圧倒されてしまう方も多いはずです。
しかし、会社四季報の読み方を正しく理解すれば、将来性のある企業を見つけたり、投資判断の材料を得たりと、株式投資において大きなアドバンテージになります。特に、決算書やIR資料だけでは見えてこない「現場のリアルな情報」や「成長ストーリー」も読み取れるようになるのが、四季報ならではの魅力です。

ガイドさん
そこで本記事では、「四季報の見方がわからない」という方でも安心して読み進められるよう、四季報の読み方を分かりやすく解説してくれるおすすめの本をランキング形式でご紹介します。
初心者向けに丁寧に書かれた入門書から、ベテラン投資家も愛用する実践的な参考書まで幅広くピックアップしました。
「とりあえず四季報を読むのではなく、使いこなしたい」「銘柄選びの目を養いたい」という方は必見です。
ぜひこの記事を参考に、四季報を“読む”から“活用する”へとステップアップしていきましょう!

読者さん
1位 会社四季報公式ガイドブック 改訂版
株式投資に興味を持ったとき、まず最初に直面するのが「どの企業の株を買えばいいのか?」という疑問ではないでしょうか。インターネットやSNSで情報があふれる中、何を信じ、どの指標を頼りに判断すればよいのか分からず、結局「なんとなく人気の銘柄」に手を出してしまう……。そんな経験がある方は決して少なくありません。
そこで登場するのが、長年にわたって“投資家の羅針盤”として親しまれてきた『会社四季報』です。1936年の創刊以来、四半期ごとに刊行され、すべての上場企業の最新情報と独自予想を掲載してきたこの一冊は、プロの機関投資家から個人投資家まで、幅広い読者層に支持されてきました。しかし一方で、「情報量が多すぎて読み方が分からない」「初心者には敷居が高い」と感じる声も根強くあります。
そんな悩みを解決するために生まれたのが、今回ご紹介する『会社四季報公式ガイドブック 改訂版』です。本書は、四季報を発行している東洋経済新報社の編集部が自ら全面的に改訂し、誰でも四季報を“読みこなせる”ようになるための知識とノウハウを凝縮した、まさに「使い方の教科書」です。
続きを読む + クリックして下さい
掲載されているのは、単なる読み方のマニュアルではありません。たとえば、会社の特色や大株主、社長の名前がどのような意味を持つのか、連結事業欄の数字から何が分かるのかといった、ページの隅々に隠れた「読み解きのヒント」を具体的な例とともに解説。さらに、独自の業績予想がどのように作られているのか、記事の見出しに込められた意味、配当や株主優待のチェックポイントまで、四季報に詰め込まれた情報を120%活かすための視点が余すところなく紹介されています。
加えて、近年話題の「新NISA」にも対応。非課税枠を活かしてどんな銘柄に投資するべきか、その見極め方にも踏み込んでいます。投資信託やインデックスでは物足りなくなった方、自分の目で銘柄を選んでポートフォリオを組みたい方には、最適な指南書となるでしょう。
また、財務指標やキャッシュフローといった、いわゆる“会計の専門用語”も丁寧にかみ砕いて解説。「自己資本比率が高いってなぜ安心なの?」「利益が出ているのに現金が足りないってどういうこと?」といった素朴な疑問にもしっかり答えてくれます。単に投資テクニックを身につけるだけでなく、企業そのものを見る目が育つ――これはまさに、投資の“地力”をつける一冊と言えるでしょう。
さらに巻末には、上級者向けの“お宝銘柄発掘法”や“米国会社四季報の活用術”といった、次のステップにつながる実践的な内容も収録。日本株だけでなく、世界の市場へ目を向けたいと考えている方にとっても、大いに役立つ内容です。

ガイドさん
『会社四季報』を“なんとなく”使っていた人こそ、本書を読めば驚くはずです。
「こんなにも情報が詰まっていたのか」「今まで宝の持ち腐れだった」と。四季報を「情報の山」から「利益の源泉」へと変える力が、本書にはあります。
本の感想・レビュー
私は普段から中長期で株式投資をしている40代の会社員です。これまでにも色々な投資本を読んできましたが、正直「四季報の使い方」についてここまで具体的かつ実践的に書かれた本には出会ったことがありませんでした。
このガイドブックを読み込んで、実際に投資スタイルが変わりました。特に強く印象に残っているのは、業績予想の読み方です。会社の公式発表では見えてこない部分が、四季報の「独自予想」には反映されていること、その精度が高いという裏側まで丁寧に解説されていて、納得感を持って銘柄選びができるようになりました。
実際、ガイドブックの内容を参考にして選んだ銘柄が、四半期決算で市場予想を上回る結果を出し、しっかり株価も上昇しました。もちろん一喜一憂しすぎないように心がけていますが、自信を持って判断できる材料が手に入るという意味で、この一冊の効果は計り知れません。
他5件の感想を読む + クリック
私は金融業界とはまったく縁のない仕事をしている人間です。株式投資に興味はあったのですが、どうしても数字や指標になると壁を感じてしまっていました。でも、『会社四季報公式ガイドブック 改訂版』は、そんな私のような“数字アレルギー”の人間にも優しいつくりで、本当に助けられました。
とくに良かったのは、図解の多さと視覚的なわかりやすさです。ただ説明を並べるだけでなく、紙面の一部を拡大して「ここがポイントです」と明示してくれているので、「なるほど、こういう風に見ればよかったのか」と腑に落ちる場面が何度もありました。また、専門用語に対する解説もただ辞書的な説明ではなく、「なぜその概念が重要なのか」まで言及されていて、読み物としても面白かったです。
今では、ニュースで企業名が出てきたときにも「この会社、どんな特色があったっけ?」と自分で調べたくなるようになりました。読んで終わりではなく、理解が行動につながる本だと思います。
私は日頃からWebサービスをよく使うタイプで、四季報も「会社四季報オンライン」の存在は知っていました。ただ、どちらを使うべきか迷っていたのが正直なところです。でも、このガイドブックでは「紙とオンライン、両方の長所を活かしてこそ最大の効果がある」と明快に書かれていて、その活用方法に大きなヒントをもらいました。
紙版は視野が広く、全体を俯瞰しながら企業を眺められる一方で、オンラインは検索や条件指定がスムーズ。特にタイムリーな情報更新に関してはWeb版の強みが際立っていて、それをきちんと区別して使いこなす姿勢こそが現代の投資家には必要なんだと実感しました。おかげで、今では情報収集のストレスが大幅に減り、より効率よく銘柄分析ができるようになっています。
「四季報って、なんであんなに小さな文字でびっしり書いてあるの?」――これが、私が四季報に最初に抱いた率直な印象です。書店で手に取ったものの、すぐ閉じて棚に戻してしまったこともあります。正直、投資の参考書だとは聞いていても、あまりにも難しそうで、自分には縁がないものだと感じていました。
でも、このガイドブックに出会ってから、すべてが変わりました。まず驚いたのは、読み方に「順番」があるということ。何となく眺めていたページが、意味のある構造を持っていたことに気づけた瞬間、まるで霧が晴れたようでした。そして、難しい言葉や数字が、なぜそこにあるのか、どう読み取るかをきちんと教えてくれるので、初心者の自分でもすんなり理解できました。実際に手元に四季報を置いて、ガイドブックと照らし合わせながら読み進めるうちに、次第に「この会社、面白いな」と思えるようになってきたのは大きな収穫です。
自分は経理職に就いていて、数字にある程度の慣れはあったのですが、投資の世界となると話は別でした。特に企業のキャッシュフローの分析には前から苦手意識がありました。営業活動、投資活動、財務活動――それぞれ何を意味しているのかは理解していても、それを「投資判断」にどう落とし込めばいいのかがピンとこなかったんです。
この本では、キャッシュフローの各要素を単体で見るのではなく、企業の成長段階や財務構造と照らし合わせながら判断する視点を紹介してくれています。たとえば、営業キャッシュフローが安定していても、投資に積極的すぎる会社には注意が必要な理由など、言葉だけではなく背景の考え方から教えてくれるのが非常にありがたかったです。
数字をただ読むのではなく、「意味づけ」しながら企業を見られるようになったのは、自分にとって大きな進歩でした。これまで漠然と避けていた企業分析が、いまはむしろ楽しいと思えるようになっています。
私は2024年から新NISAを使って投資を始めたばかりの30代主婦です。最初は「なんだか得らしいからやってみよう」くらいの感覚だったんですが、実際に始めてみると、何を買ったらいいか分からず困ってしまっていました。そんな時にこのガイドブックに出会いました。
嬉しかったのは、「どんな企業が長期保有に適しているか」という視点で情報の見方を教えてくれるところです。NISAは非課税で保有する期間が長くなるぶん、短期の上下よりも“成長する企業かどうか”が大事になると思っていたので、そういう目線で四季報を読む方法を知ることができたのはとても心強かったです。
情報はたくさんあるけれど、どう選んで、どう読むかまで具体的に教えてくれるガイドブックだからこそ、「制度の仕組み」と「投資の実践」を結びつけることができた気がします。NISAを活用する人には、ぜひ一読してほしい内容だと思います。
2位 エミン流「会社四季報」最強の読み方
「株を始めてみたいけど、情報が多すぎて何を信じればいいのか分からない」「銘柄選びに自信がなく、いつも感覚で買ってしまう」「『会社四季報』を買ってはみたものの、どこを読めばいいか分からずに閉じたまま」——そんな投資初心者の悩みに真正面から応えてくれるのが、本書『エミン流「会社四季報」最強の読み方』です。
著者は、トルコ出身で東大卒、元野村證券という異色の経歴を持ち、日本株を15年以上にわたり分析し続けてきた投資家・エミン・ユルマズ氏。彼は『会社四季報』を「日本経済の縮図」と位置づけ、その1ページ1ページの裏に“企業の物語”が存在すると語ります。本書は、そんな彼の“毎号全ページ読み込み続けてきた”経験から生まれた、最強の四季報活用術です。
続きを読む + クリックして下さい
本書が他の投資本と決定的に違うのは、単なる読み方のハウツー本ではないという点です。四季報のどのページをどう読むのかという実用的な解説にとどまらず、「どのように企業の本質を見抜くか」「割安かつクオリティの高い銘柄をどう発見するか」といった、“本質的な判断力”を養うための思考法まで、具体的かつ体系的に学べる構成になっています。
特に注目すべきは、エミン氏が重視する投資基準です。一般的な投資本ではあまり触れられない「PSR(株価売上高倍率)」という指標を軸に、利益に表れにくい成長企業の価値を見出す方法を紹介しています。また、自己資本比率が70%以上ある企業を高く評価するなど、財務の健全性にも強くこだわった“堅実な投資眼”が光ります。
そして本書の後半では、エミン氏自身が注目してきたお宝銘柄が具体的に紹介されます。過去の成功事例としての9銘柄と、今後2~3年で株価が2倍、3倍になる可能性を秘めた11銘柄。それらの選定理由も詳細に解説されており、読者は「なるほど、こういう企業を探せばいいのか」という感覚を実際に掴むことができます。
時代は今、投資家にとって大きな転換点を迎えています。新NISA制度が始まり、「長期・積立・分散」という基本が再び注目を集める中、個人投資家に求められているのは“自分の頭で考える力”です。本書はまさにその力を鍛えるための実践書であり、「情報に流されず、信念を持って銘柄を選び、長期で保有する」ための武器となります。

ガイドさん
単に“儲けるため”ではなく、“企業の価値を見極め、未来に投資する”という本質的な姿勢を学びたい人にとって、本書は間違いなく「読むべき一冊」です。
これから株式投資を本気で学びたいと考えている方、NISAを本格的に活用したい方、四季報を有効活用したいすべての人に、自信を持っておすすめできる内容です。
本の感想・レビュー
私は20年以上株式投資に取り組んできましたが、それでもこの本から学ぶことは非常に多かったです。特に著者が15年間にわたって毎号欠かさず四季報を読み込んできたという話には、驚きと敬意を感じました。
ページの端々から伝わってくるのは、机上の理論ではなく「現場の肌感覚」。四季報のデータをどう解釈し、実際にどう行動に移すか。そのリアルな知見が、読者に向けて真正面から語られているのです。
特定の数値だけに頼らず、状況判断やタイミング、相場観といった“生きた投資の勘どころ”が随所に盛り込まれている点は、まさに熟練者の経験の賜物だと感じました。こういう投資本に出会える機会はそう多くありません。
他5件の感想を読む + クリック
これまでの私は「割安株」と「成長株」は別物だと思い込んでいました。高成長な企業は高PERでも仕方ない、逆に安い株はどこか問題を抱えている…そんな単純な見方しかできていなかったのです。
ですが、この本で提案されている「割安+クオリティ」という考え方は、それを見事に覆してくれました。企業の成長性と財務の健全性、ビジネスモデルの強さを併せ持ちながら、それでいて株価が過小評価されている銘柄がある――その可能性を知って、目から鱗が落ちました。
そうした企業をどう探し、どう判断していくかも実例を挙げながら丁寧に説明されていて、投資戦略の幅がぐっと広がったように感じます。
投資本の中には「理屈はわかるけど、結局どんな銘柄を選べばいいの?」という疑問が残るものが少なくありません。その点、本書では具体的な銘柄が数多く取り上げられていて、とても参考になりました。
エミンさんが選んだ銘柄は、単なる人気株や高成長株ではなく、過去の業績推移や現在の市場環境、将来の展望までしっかり分析されたうえで紹介されているのがわかります。何より、選定の背景にある考え方が一貫しているので、読みながら納得できるのです。
また、紹介されている銘柄がどれも今すぐ買えと言っているのではなく、あくまで「こういう着眼点で銘柄を見てみよう」というスタンスなのも信頼感が持てました。自分の目で判断する力を養うための優れた教材だと思います。
私はこれまでファンダメンタル分析を中心に株式投資をしてきました。PERやPBRといった指標は当然のように使っていましたし、それが“投資の基本”だと信じてもいました。しかし、この本を読んで感じたのは、それらの数値に過度に依存しないことの重要性です。
エミン氏は、PERやPBRといったバリュエーション指標を「目安」として扱う一方で、それだけでは見えてこない企業の質や市場の評価ギャップにこそ投資機会があると述べています。印象的だったのは、そうした指標が割安でも「バリュートラップ」に陥るリスクについての言及でした。
数字はあくまで過去の反映でしかなく、将来に向けたビジョンや構造変化をどう読むかが肝心なのだという視点は、私の分析手法に新たな視座を加えてくれました。特に、PSR(株価売上高倍率)や時価総額に注目する考え方は、視野を広げるきっかけになりました。
投資の勉強はここ数年、定年を見据えて少しずつ進めてきました。初心者向けの本も何冊か読みましたが、「で、結局どうすればいいの?」という疑問がいつも残っていました。でも『エミン流「会社四季報」最強の読み方』は、私のような普通の生活者にも、すぐに実践できることが書かれていたのがとてもありがたかったです。
たとえば、四季報を読むときの順番や、どのページから見れば情報が整理しやすいか、あるいはどんなキーワードに注目するべきかが具体的に紹介されています。それに、「損切りのルールを設けない」「下がっているときに買い足さない」といった独自の考え方も、自分なりの軸を作る上で非常に参考になりました。
知識だけで終わらず、読後すぐに手を動かしたくなるような構成が、この本の大きな魅力だと思います。読みながら何度も付箋を貼ってしまいました。
『会社四季報』はもう何十冊と読んできましたが、それでも「この本でこんなに発見があるのか」と驚かされました。特に、巻頭ページや業績予想の部分に注目する読み方は、目から鱗が落ちる内容でした。
私はこれまで四季報を、個別企業の情報を調べるための辞書のように使ってきました。しかしエミン氏は、それだけでなく「マーケットの温度」を測るための指標としても活用できると示してくれています。業種別の業績動向や、予想数字の微妙な変化など、細かな情報の積み重ねこそが、未来のトレンドを読む手がかりになるというのです。
投資というのは数字の正確さだけでなく、空気を読む感性も問われる世界。その感覚をどう磨けばよいのかを、具体的な読み方を通じて教えてくれる一冊だと思います。
3位 伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版
「株式投資を始めたものの、会社四季報をどう活用すればいいのか全然わからない」
「数字ばかりで何を見れば“買い”か判断できない」
そんな迷いや不安を抱える個人投資家の心にズバリと刺さるのが、書籍『伝説の編集長が教える会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい 改訂版』です。
著者の山本隆行氏は、長年『会社四季報』編集部で記者・編集長を務めてきた実力派。現在も投資セミナーや講演活動で「四季報の読み解き方」を伝えるスペシャリストとして、多くのファンを集めています。本書はその山本氏が「現場記者しか知らない読み方」「投資家として結果を出すための視点」「手間をかけずに割安株・成長株を発掘する技術」を、初心者にもわかりやすい文章で丁寧に解説した一冊です。
続きを読む + クリックして下さい
この本の最大の魅力は、会社四季報を「読み物」としてでなく、「投資の武器」として使いこなすための知識と実践ノウハウが惜しみなく公開されている点にあります。たとえば、「増益」と「増額」の違いが株価に与える影響、営業利益進捗率の重要性、上方修正が“続く企業”の特徴、さらに「PERが低い=割安」は間違いという衝撃的な指摘まで、すべてが実例とともに語られます。
読み進めるうちに、なぜ春号・夏号・秋号・新春号の四季報で“見るべきポイント”が異なるのか、どの時期にどんな情報が盛り込まれているのか、四季報の裏側まで理解できるようになります。特に「独自増額」や「黒字転換」といったキーワードに敏感になることで、相場が動き出す“前兆”を読み取る目を養うことができるでしょう。
また、株価チャートの基本的な読み方や、キャッシュフロー計算書から企業の“見えないリスク”を見抜く方法、さらには四季報に載る【連結事業】欄から稼ぎ頭を見極めるテクニックまで、これ1冊で投資判断の視点が根本から変わる構成になっています。

ガイドさん
「株で資産を増やしたいけど、情報が多すぎて何から手をつければいいのか分からない」「自分で銘柄を見極める“軸”がほしい」「初心者でも納得しながら勉強できる本を探している」――そんな方にとって、本書はまさに最初に読むべきバイブルです。
本の感想・レビュー
僕はこれまで、会社四季報って「投資家が使うプロ向けツール」だと思って敬遠していました。でも、本書を読んで考えが180度変わりました。
情報の量や精度がすごいというのは聞いていたけれど、どうやってその情報を“読む”のかというノウハウがまったくなかったんですよね。本書では、ページのどこをどんな視点で見ればいいか、四季報がどのように構成されていて、それぞれの項目にどんな意味があるのかを、著者の経験を交えながら丁寧に解説してくれます。
特に面白かったのは、各号の違いと、それぞれの使いどころ。四季報って4回出てるけど、全部同じ内容だと思っていたんですよ。それが春号と夏号でこんなに違うなんて。本当に目から鱗が落ちました。
他5件の感想を読む + クリック
私は数字を見るのがもともと得意ではないので、PERとかPBRとか言われても、何となく「低いほうがいいのかな」くらいの理解しかありませんでした。この本を読んで、それが大きな誤解だったことに気づきました。
指標はただの目安ではなくて、その裏には必ず“ストーリー”があるという視点を教えてもらったんです。PERが低い理由にはちゃんと意味があるし、PBRが1倍を割っているからといって飛びつくのは危険。むしろ、その理由や背景を探ることが本当に大事で、その考え方を本書は何度も何度も教えてくれました。
「数字だけを追う投資から、一歩進んだ目線を持とう」というメッセージが、静かだけど力強く伝わってくる本です。読み終えた今は、以前より数字を立体的に見られるようになった気がしています。
正直、大化け株って“運”だと思ってました。だって、予想できないから「化ける」んでしょ?って。でもこの本を読んだあと、その考えが甘かったと気づきました。
著者はただ感覚で語るのではなく、明確なロジックで「こういう銘柄は化ける可能性がある」と示してくれるんです。それが説得力ありすぎて、思わず四季報を手に取りながらページをめくってしまいました。
特に、売上成長率や利益率、さらには主力事業の構成など、具体的なチェックポイントがいくつも紹介されていて、これが大化けの「兆し」なのかと納得感がありました。しかも、実際に過去の成功銘柄をもとに説明されているから、イメージしやすいんです。
運に頼るのではなく、根拠を持って探せるという視点が、私にとっては大きな収穫でした。
今までは株価を見て「割安かどうか」って、PERとPBRだけで判断していたんです。でもそれって、めちゃくちゃ危ういことだったんだなと、この本でようやく理解できました。
著者が言うように、「低PERだから割安」「PBR1倍割れだからお買い得」といった短絡的な見方では、真の価値にはたどり着けません。たとえば、PERが低くても将来性がなければ評価されないし、PBRが1倍を切っていても市場から見捨てられている可能性だってある。
本書では、そうした“使いどころ”と“使い方の間違い”を丁寧に解きほぐしてくれました。私はこれまで、なんとなく“数字の表面”だけで判断していたのだと実感し、今後はもっと深く見ていこうと決意しました。
読み進めるうちに何度も感じたのは、「この人、本当に会社四季報を知り尽くしているな」ということです。筆者は元編集長という立場から、一般読者には見えない“行間”のようなものを教えてくれます。
特に印象的だったのは、業績コメントや材料欄に込められた記者たちの意図や、“微妙な表現の違い”の重要性です。文字通り一語一句に意味があるというのは、実際に作る側にいた人でなければ語れないリアリティだと思いました。
さらに、季節ごとの発行意図や、編集部がどこに注目して取材しているかという話は、これまでの四季報の読み方にまったくなかった視点です。読みながら、まるで“会社四季報の裏側ツアー”を体験しているような感覚でした。
読み終えた瞬間、自然と「何か良い銘柄ないかな」と四季報をめくっていました。まるで自分が“発掘作業”を始めたかのような感覚です。これは、単に知識を得るだけでなく、「すぐに使いたくなる」本だという証拠だと思います。
著者が提示するチェックポイントがとても具体的で、ページを開いて数字を追えば、それが実際に見えてくるんですよね。「こういう視点で読めばいいのか」と実感できるので、自分の行動がすぐに変わります。
読み終えて終わりではなく、読んだ直後から行動が始まる本。こういう“スイッチが入る”本には、なかなか出会えません。会社四季報が、知識を詰め込むための本から、未来を探しにいく道具に変わった気がします。
4位 世界一楽しい! 会社四季報の読み方 小説のようにハマり、10倍儲かる!
株式投資をはじめたとき、多くの人がまず手に取るのが『会社四季報』です。3800社以上の上場企業の情報が凝縮された、まさに“投資家のバイブル”。しかし、その情報量と専門用語の多さに圧倒され、「どこを読めばいいのかわからない」「数字だらけで苦痛」と、途中で挫折してしまった経験がある方も多いのではないでしょうか。
そんな四季報の“高い壁”を、楽しみながら軽々と飛び越える方法があるとしたら――?
それが、藤川里絵氏の著書『世界一楽しい! 会社四季報の読み方 小説のようにハマり、10倍儲かる!』です。
続きを読む+ クリックして下さい
著者は、四季報オンラインの人気コラムニストであり、筋金入りの「数字嫌い」。それでも、四季報の“記事欄”や“数字の行間”に潜むヒントを読み解くことで、なんと自己資金を5年間で10倍に増やすことに成功しました。本書は、その経験と知恵を惜しみなく注いだ、まったく新しい「読み物」としての四季報活用術です。
四季報は、ただのデータ集ではありません。記者が見出しに込めた「意図」、行間に漂う「匂わせ」、そして数字の奥に隠された「変化の兆し」。それらをまるで推理小説の謎解きのように追いかけていくことで、株価上昇のサインを見つけ出す――これが本書の核となるアプローチです。
「増配か」「不気味」「虎視眈々」……そんな言葉に隠された意味を紐解くうちに、あの分厚い四季報がまるで宝の地図のように見えてくるから不思議です。しかも、楽しく読めるだけでなく、「株価が上がる会社を見つける力」も自然と身につくという、まさに一石二鳥の内容。

ガイドさん
四季報を読むのが初めての方も、これまで数字ばかり追って疲れてしまった方も、この一冊を読めば視界がガラリと変わるはず。
投資の世界に必要なのは、知識よりも“見る目”――その“目”を育てる最良の指南書が、ここにあります。
本の感想・レビュー
読み始めてまず驚いたのは、その“読みやすさ”でした。私は普段、金融や投資に関する書籍を読むことが多いのですが、正直この本ほどテンポよく読み進められたものは珍しいです。タイトルに「楽しい!」とあったので、正直言って最初は少し疑っていたんです。でも読み進めるうちに、「これはたしかに楽しいわ」と素直に感じてしまいました。
何よりも印象的だったのが、著者の語り口の軽やかさ。専門的な話をしているはずなのに、文章のトーンが柔らかく、堅苦しさをまったく感じないんです。話がどんどん展開していくのに置いていかれた感じもせず、まるで会話をしているような感覚でスルスル読めてしまいました。
読書というより、誰かとカフェで「四季報ってこう読むと面白いんだよ」って話を聞いているような、そんな空気感が心地よくて、一気に読了してしまいました。
他5件の感想を読む + クリック
私は投資を始めたばかりで、四季報を読もうと思ってはみたものの、ページを開いた瞬間に「無理かも」と感じてしまった口です。数字、業績、専門用語……どれもハードルが高くて、正直、最初は完全に諦めていました。
そんなときに出会ったのがこの本です。読んでみて、まずホッとしました。初心者の立場を理解してくれているという安心感が文章からにじみ出ていたんです。たとえば、著者が「私も数字が苦手だった」と語っていたくだりでは、「えっ、あの著者でもそうだったの?」と驚きつつ、どこか勇気をもらいました。
本書では、数字の分析よりも、四季報の記事欄の言葉や表現に注目するスタイルが紹介されていて、これなら自分にもできるかもと思えました。実際、読み方を真似してみたところ、以前よりもはるかに「情報を読めた」感覚があり、楽しくなってきたんです。
投資はハードルが高いと思っていた私のような初心者でも、この本なら安心して読み進めることができました。四季報の“入り口”として、本当にありがたい一冊でした。
私はつい最近、ようやく証券口座を開いたばかりの完全なる投資初心者です。株式投資に興味はあるものの、「会社四季報」という存在すらほとんど知らず、書店でその分厚さを見て尻込みしていました。そんな私にとって、本書はまさに「導いてくれる先生」のような存在でした。
この本のすごいところは、難解な用語や理屈を並べるのではなく、読者の不安や戸惑いに共感した上で、やさしく、かつ実践的に知識を届けてくれる点にあります。著者自身が数字嫌いだったことを正直に語ってくれていたのも、とても励みになりました。「苦手な人が書いた本だからこそ、苦手な人にもわかる」というのは本当にその通りだと思います。
一読者として、「もっと早くこの本に出会いたかった」と心から思いました。今後も何度も読み返すことになると思いますし、これから四季報を開くたびに、きっと著者の声が脳裏に浮かぶ気がします。それくらい、初心者にとっては頼もしい一冊です。
読書なのに、ゲームをしてるみたいにワクワクした。そんな感覚をくれたのがこの本です。私はもともと活字が苦手で、数字やグラフを見ると眠くなるタイプ。でも、この本で紹介されていた「記事欄の言葉を拾う」という読み方には完全にハマってしまいました。
「虎視眈々」や「積極投資」など、たった一語で企業の動向をにおわせてくる表現を探すのが、まるで“言葉狩り”みたいで、本当に楽しい。そういう言葉の裏には、取材を重ねた記者のリアルな手応えがあると聞いてからは、読み方ががらりと変わりました。
一見、何気なく書かれている言葉の奥に、意図がある。その意図を読み解くこと自体が、もはや知的なゲームなんです。しかも、それが投資成果に直結するとなれば、こんな面白い読み物って他にないなと感じました。正直、人生で初めて「四季報を読むのが楽しい」と思えた瞬間でした。
正直、この本を読んで最初に思ったのは、「大学時代に出会っていれば人生変わってたかも」ってことです。就職活動中、僕は会社四季報を使っていましたが、完全に「見る」だけでした。売上や社員数、業種でフィルターをかけて、ただデータを拾うためだけに開いていた感じです。
でも、この本を読んでから気づいたんです。四季報って、実は“会社の人格”がにじみ出てるんだってこと。記事欄の見出しや言い回しには、記者の想いとか、企業の温度感が詰まっていて、それを読み解くという発想が、僕には全くなかった。
もしあの時、この読み方を知っていれば、もっと深く企業を知ることができただろうし、入社後のミスマッチも避けられたかもしれない。そう思うと悔しい気持ちもあります。でも、今からでも遅くない。この本に出会えたことで、社会人としての視野がまた一つ広がった気がしています。
「同じ会社の四季報を、号ごとに読み比べると面白い」――この発想にやられました。今までそんな読み方、したことなかった。だけど、実際にやってみると、もう止まらない。これって、もはや推理小説の楽しみ方そのものです。
本書で紹介されていた、ある会社の見出しの変遷――「予兆」→「不気味」→「防衛策」――を読み解いていく過程に、心底ゾクゾクしました。たった数文字の表現の中に、企業内部の緊張感が詰まっていて、それが数ヶ月かけて一つのストーリーとして展開していく。ここまで“読む価値のあるデータベース”だったとは、四季報を完全に見くびっていました。
ひとつの会社に注目して過去号をさかのぼる読み方は、今後も続けていきたいです。自分なりの考察をノートにまとめるのも楽しくて、まさか投資を通じてこんな知的好奇心を刺激されるとは思いませんでした。
5位 「会社四季報」速読1時間で10倍株を見つける方法
あなたは、『会社四季報』を最後まで読んだことがありますか?
そして、読んでみたものの「文字が多すぎて挫折した」「どこを見れば良いかわからなかった」そんな経験はありませんか?
『会社四季報』は、日本に上場しているすべての企業の財務情報・業績予想・株価チャートなどが掲載された、まさに“投資家のバイブル”とも呼ばれる情報集です。しかし、それがあまりにも情報量が多く、使いこなせている人はごく一部。投資初心者にとっては、むしろ“難しすぎて使えない本”という印象を持っている方も多いのではないでしょうか。
そんな四季報を、わずか「1時間」で読み解き、「10倍株」を見つける方法がある――そう聞いたら、にわかには信じがたいかもしれません。しかし、それを現実のものとしたのが、本書『「会社四季報」速読1時間で10倍株を見つける方法』です。
続きを読む + クリックして下さい
著者の“はっしゃん”氏は、会社員として働きながら株式投資に取り組み、独自の銘柄発掘法によって総資産3億円を築いた実力派の個人投資家。そんな彼が、自ら編み出し、3年半にわたってTwitterやYouTubeで実践・公開してきた投資法の全貌を、この一冊に詰め込んでいます。
特筆すべきは、「知識ゼロでも再現できるシンプルさ」と「結果を出しているという実績」。本書で紹介されている速読法では、難解な財務指標や高度なチャート分析は一切不要。必要なのは、四季報と付箋だけ。
まずは右肩上がりの株価チャートにだけ注目し、そこに付箋を貼る。その後に、売上・利益の成長を見てふるいにかけ、最後は“理論株価”で絞り込む。たったこれだけの3ステップで、誰もが「成長企業を見つける目」を手に入れることができるのです。
しかも、はっしゃん氏は2019年夏号から2023年新春号まで、15冊分の四季報を実際に速読・検証し、1,224枚もの付箋を貼って得られた統計データを本書で公開しています。それらの銘柄が後にどのような株価推移をたどったか、何が“当たり”で何が“外れ”だったのか、その検証データが満載です。過去の相場の流れや経済イベントとともに「どのような企業が伸びてきたか」を学べる体験型の構成も、大きな魅力のひとつ。
さらに、初心者が迷いがちな「売るタイミング」「リスクの考え方」「長期保有のコツ」まで網羅。単なる銘柄探しの手法だけでなく、投資で勝ち続けるための“思考法”までも教えてくれる内容となっています。

ガイドさん
これまで、「株は難しそう」「四季報は分厚くて読めない」と感じていた方こそ、本書の対象読者です。特別なスキルは不要。必要なのは「やってみよう」という一歩だけ。
四季報が、ただの情報誌ではなく“未来の資産を発掘する道具”に変わる瞬間を、ぜひあなたの目で体験してください。
本の感想・レビュー
タイトルに「付箋だけで10倍株が見つかる」と書かれているのを初めて目にしたとき、正直なところ半信半疑という気持ちが拭えませんでした。「本当にそんなに簡単なことで成果が出るのだろうか?」という疑問が強く、期待よりも警戒心のほうが先に立っていたと思います。
ただ、読み始めてすぐに、これは単なる理論書ではなく、実際に著者が長年試行錯誤を重ねて築き上げた実践的な方法なのだと伝わってきました。特に、四季報の過去15冊に付箋を貼り、その結果を定量的に追って記録してきた過程は、読み物としても説得力がありました。
「右肩上がりのチャートを見つけたらそこに付箋を貼る」という行為自体は本当にシンプルですが、それをきちんと続け、一定のルールで選別していくことで、統計的にも期待値が高まっていくのだという説明には、納得感がありました。
読み終える頃には、当初の疑念はすっかり和らぎ、「こういうやり方なら、自分にも取り入れられるかもしれない」と思えるようになっていたのが印象的です。派手な方法ではないからこそ、地に足のついたアプローチとして受け入れやすかったです。
他7件の感想を読む + クリック
これまで、四季報を読んでみようと手に取ったことは何度かありました。でも、あの細かくてぎっしり詰まった情報量に圧倒され、結局途中で読むのをやめてしまっていたのが実情です。特に「業績」の見方が分からず、何を基準に判断すればいいのかピンとこないまま、投げ出してしまうということが何度もありました。
この本では、業績をチェックする上で注目すべきポイントを「売上」と「利益」、しかもそれらが「連続して伸びているかどうか」という視点に絞って説明してくれます。複雑な財務分析や専門用語の知識がなくても、「グラフの傾き」と「数字の流れ」に着目するだけで良いという発想に、目から鱗が落ちました。
実際に自分でも四季報を開いて、書かれている通りに業績を追ってみたところ、これまで漠然としていた情報がはっきりと意味を持って目に入ってくるようになりました。あの情報の密度に戸惑わずに済んだのは、注目する箇所が決まっていたからだと思います。
これまで「四季報=難しいもの」というイメージを持っていた自分にとって、この本が教えてくれた視点の転換は大きかったです。業績チェックに対する苦手意識がずいぶん和らいだように感じています。
投資というと、特別な知識やスキルが必要なものだという先入観があり、なかなか手を出しづらく感じていました。証券口座は持っているものの、実際に銘柄を選ぶとなると「どこから始めればいいのか分からない」という状態が長く続いていました。
この本が紹介する方法は、そういった“初めの一歩”を踏み出せずにいる人にとって非常にありがたいものだと思います。何より良かったのは、「必要な道具は紙の四季報と付箋だけ」と明記されていることでした。スマホアプリやパソコン、チャート分析ソフトなどが要らないので、投資という行為そのもののハードルが一気に下がったように感じました。
紙面をめくりながらチャートに目を通し、「これは良さそう」と思えるものに付箋を貼る。その行為が自然で直感的だったため、「投資の入口」に立つまでの心理的な壁がすっと消えていったような気がします。机の上に四季報を広げて、付箋を貼るという作業にちょっとした楽しさすら感じました。
投資を本格的に始めたいけどどう動いていいか分からない人にとって、これほどシンプルで親しみやすいアプローチは他にないのではないでしょうか。
今までの私は、ネットで見かけた「おすすめ銘柄」やSNSで話題になっている企業に乗っかって株を買うだけの、いわば“受け身の投資家”でした。正直なところ、自分でゼロから企業を見極める力はなく、判断軸も曖昧。運が良ければ利益、ダメなら損切り、そんなことを繰り返していました。
この本を読み、実際に紹介されている三段階のステップを体験してみたところ、気づけば「自分で判断できる」状態に少しずつ近づいていました。最初のチャートチェックでは「右肩上がり」に注目し、次に業績を見て成長性を確認し、最後に理論株価で割安かどうかを判断する。たったそれだけの手順ですが、「これなら自分でもいける」と思えたのはとても大きな進歩でした。
付箋を貼って四季報を読み込んでいく中で、以前ならスルーしていた小さな成長企業にも目がいくようになりました。何より「自分で銘柄を選んだ」という感覚が、投資そのものの手応えをぐっと高めてくれた気がします。
普段は会社勤めで忙しく、平日は夜遅くまで仕事、休日は家族サービス。そんな生活を送る中で、「銘柄選びに何時間もかけるような投資スタイルは無理だ」と諦めていました。でもこの本を読んで、時間がなくても投資ができる道筋があると知り、本当に救われた気持ちになりました。
特にありがたかったのは、紙の四季報と付箋を使えば、ネットに張りつかなくても十分に銘柄選定ができるという点です。私は通勤時間や週末のちょっとした空き時間を使って作業していますが、それだけでも十分に形になります。特別な道具や環境を用意しなくても、「読む→付箋を貼る→分析する」の3ステップが完結するのは、忙しいサラリーマンにとって非常に実用的です。
また、投資法の一貫性があるため、途中で迷いが生まれにくいのも魅力の一つです。毎回同じ手順を踏むことで、判断のブレも減りました。これまで感覚的にやっていた投資が、「手法」として自分の中に根付いたような実感があります。
本書を読んでまず驚いたのは、その手法が「再現性」に非常に優れているという点でした。投資の本にはありがちな“成功体験の紹介”にとどまらず、実際のデータとともに具体的な方法が提示されており、「誰でも同じように実行できる」という安心感があります。
特に、2019年夏号からの四季報15冊にわたって実践されてきた記録や、実際に付箋を貼った471銘柄のその後の動きが丁寧に分析されていたのは圧巻でした。やり方が抽象的でなく、明確に示されているので、自分がそのまま真似できるという確信が持てました。
この信頼感があったからこそ、私自身だけでなく、同じように投資に興味を持っていた家族にもこの本を勧めました。今では、我が家では週末に四季報を囲んでチャートを眺め、付箋を貼る時間がちょっとした共通の趣味になっています。投資がこんなに身近なものになるとは思っていませんでした。
これまで投資といえば、難解な指標や専門用語の羅列に圧倒されて、なんとなくでしか銘柄を選べていませんでした。そんな中、この本が教えてくれた「右肩上がりのチャートを選ぶ」という考え方には、非常に大きなインパクトがありました。
これが最初のふるいになるというのが驚きでしたが、実際にやってみると、その効果は絶大です。月足チャートを眺めて、過去数年間にわたってなだらかに上昇している企業にだけ注目する。その時点で多くの企業をスピーディーにふるいにかけることができ、無駄な時間や迷いが減りました。
しかも、そのチャートが「期待上げ」ではなく、実際の業績に裏打ちされた継続的な成長を反映しているのかどうかを次のステップで確認していく流れも、理にかなっています。ビジュアルを入り口にすることで、数字に苦手意識がある人でも取り組みやすい構成になっていると感じました。
この本の最終ステップにあたる「理論株価」のパートは、これまでの投資本ではあまり見かけなかった実用的な内容でした。数字が苦手な私にとっては少し身構える部分もありましたが、読んでみると、考え方や手順がとても丁寧に解説されていて安心しました。
「理論株価」と聞くと難しそうな印象を受けますが、ここで紹介されているのは、シンプルな3つの指標を用いた独自の計算式。しかも、その考え方を補完するためのWebツールやチャートルームが紹介されていて、実際の活用まできちんと設計されているのが印象的でした。
この章を読んだことで、「自分が選んだ銘柄の価値を、自分で確かめる」という視点が芽生えました。誰かの推奨銘柄に依存するのではなく、自分の判断に責任を持てるようになる――それが投資における本当の自立だと気づかされた気がします。
6位 会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方
「10倍株(テンバガー)や100倍株を見つけるのは、特別なセンスを持つ一部のプロだけ――」
そんなイメージを持っていませんか? あるいは、四季報に興味はあるけれど、膨大なページ数に圧倒され、手に取ることすら躊躇しているかもしれません。
本書『会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方』は、そんな投資初心者から中級者までに向けて書かれた、極めて実践的かつ体系的な投資入門書です。
著者の渡部清二氏は、20年以上にわたり、年4回発行される「会社四季報」を1冊まるごと読破し続けてきた、いわば“情報収集の職人”。1冊約2000ページもの四季報を、まるで長編小説を読むかのように隅から隅まで読み尽くし、そこから多くのテンバガー銘柄を発掘してきました。その経験と実績が、本書のすべての章に凝縮されています。
続きを読む + クリックして下さい
本書では、著者が実際に発見した「10倍株」「100倍株」の事例をふんだんに紹介しながら、それらを見つけ出すための具体的な着眼点を読者に伝授していきます。単に理屈を並べるのではなく、実際の四季報の誌面を使って「どこを、どう見るか?」を明示しているのが大きな特徴です。
たとえば、「増収率が高い」「営業利益率が高い」「オーナー経営者が筆頭株主」「上場5年以内」など、実際にテンバガーを生み出した企業に共通する指標を、明快に整理しています。こうしたチェックポイントは、初心者でも四季報を通じて再現できる実用性があるため、読み終える頃には「私にも見つけられそうだ」という自信が芽生えるでしょう。
さらに、四季報の読み方や使い方についても、読破するためのコツや効率的な読み進め方、オンライン版(会社四季報ONLINE)を活用したスクリーニング術まで丁寧にフォロー。四季報を「分厚い辞書」ではなく、「未来の成長企業を探し出す宝の地図」として活用できるよう導いてくれます。
この本は、株式投資で成功するための“裏技”を教えるものではありません。むしろ、正攻法で地に足のついた調査を行い、四季報を駆使して情報の本質を見抜き、将来有望な企業をいち早く見つけ出すという、王道の投資スタイルを提唱する一冊です。
情報があふれる時代において、誰でもアクセスできる情報源をどう読み解くか――。その差こそが、投資の明暗を分けるのです。

ガイドさん
「いつかテンバガーに出会ってみたい」
「四季報を読んでみたいけど、どこをどう見ればいいかわからない」
「話題株やSNSの“おすすめ”ではなく、自分の目で価値ある企業を発掘したい」
そんなあなたにこそ、本書は“投資家としての視点”を養い、“自分の頭で考える力”を与えてくれるはずです。
本の感想・レビュー
投資において、感覚だけで判断することほど危険なことはないと、私は常に思っています。だからこそ、この本で紹介されていた「増収率」や「営業利益率」といった具体的な数値をもとに銘柄を分析する手法には、大きな安心感と納得感がありました。定性的な話と定量的な裏付けのバランスが取れているからこそ、「この方法なら自分でも応用できそうだ」と思えたのです。
特に印象的だったのは、著者がどのようにしてその“見るべき数字”に気づいたかを語っている点です。これは単なる数字の並列ではなく、投資家としての試行錯誤の過程で自然と身についた「視点」だということがわかります。そしてそれを、読者でも取り入れられるように、事例とともに体系的に解説してくれているのです。
私はこの本を読んで以来、四季報を見る際に、これまで以上に増収率や営業利益率、さらにはオーナー経営かどうかといった点に注目するようになりました。
他5件の感想を読む + クリック
本を閉じた瞬間、すぐに四季報を手に取っていました。まるで背中を押されるように。「よし、やってみよう」という前向きな気持ちが湧いてきたのです。私はこれまで四季報を「情報の辞書」のように捉えていました。必要なときに索引を引いて、目的の銘柄だけを確認する。言ってしまえば“調べもの”のツールでした。
でも本書を読んでからは、その認識が完全に変わりました。四季報はただの情報の集合体ではなく、企業という“生き物”の今と未来が詰まった、生きた読み物なのだと感じるようになりました。実際にページをめくっていくと、注目ポイントに自然と目が留まるようになり、ひとつひとつのコメントに企業の鼓動を感じることができます。
何よりもありがたかったのは、「全部読まなくても大丈夫」「ポイントを押さえれば、初心者でも十分に銘柄を見つけられる」と著者が繰り返し語ってくれていることです。その言葉が、自分の投資に対するハードルを一気に下げてくれました。今では、週末に四季報をめくる時間がちょっとした趣味のようになっていて、「また1ページ、未来に近づいた気がする」と思えるようになっています。
投資の世界で「10倍株」とか「テンバガー」という言葉をよく聞くものの、実際にそれをどう見つければいいのかは曖昧なままでした。しかし本書では、過去の実例とともに「10倍株に共通する条件」が明確に示されていて、非常に納得感がありました。
成長性、収益性、経営者の姿勢、上場からの年数といった具体的な観点が丁寧に解説されており、しかもそれが単なる理論ではなく、実際の四季報誌面の記述と照らし合わせながら示されているのがありがたい点です。
これまではなんとなく「勢いのありそうな会社」に投資していた自分にとって、銘柄選定の基準が明確になったのは大きな進歩。特に、数字を見る際の“見るべきポイント”がはっきりしたことで、投資がより戦略的になったと実感しています。
私は株式投資を始めたばかりの初心者です。右も左もわからない中で手に取ったこの本は、専門用語だらけの投資の世界に橋を架けてくれたような存在でした。最初は正直、「難しそうだな」と身構えていたのですが、ページを開くとすぐにその不安は消えました。語り口がやさしく、例え話も実体験に基づいていて、すっと頭に入ってきたのです。
特にありがたかったのが、章ごとに目的が明確で、最後にはポイントが整理されている構成です。読みながら線を引いたり、ノートにメモを取りながら進めていけるので、自然と知識が蓄積されていきます。また、紙の四季報だけでなく、四季報オンラインのスクリーニング機能についても実践的に解説されていて、実際に自分でも使ってみたところ、初めてとは思えないほどスムーズに銘柄を見つけられました。
この本を読んでから、「投資は特別な人だけのものではない」と思えるようになりました。実践の敷居を下げてくれる工夫が随所にあり、「これなら私でもできるかもしれない」と前向きな気持ちにしてくれたことが、何より嬉しかったです。
私はこれまで四季報を、「ただの企業データ集」としか見ていませんでした。PERや売上高、業績コメントを機械的に読み流すだけで、そこから企業の“本質”を掘り下げようとしたことはありません。でも本書を読んで、四季報は単なる数字の羅列ではなく、「企業が歩んできた物語」を読み取るための媒体なのだと、目から鱗が落ちる思いがしました。
著者は、数字やコメントの奥にある“変化の兆し”を読み取り、それを未来の成長シナリオとして描き出していきます。その姿勢が印象的で、数字を「読む」のではなく、「感じ取る」ように扱っているのがわかります。これまで私は、数字の表面だけを見て判断していたのだと気づかされました。
読後には、四季報に対する距離感がぐっと縮まりました。今では、紙面の中に「物語の芽」を探すように読んでいます。これまで無味乾燥に感じていた四季報が、こんなにも深く、人間的な“気配”を帯びていたとは……。読み方が変われば、見える世界も変わる。それを強く実感させてくれた一冊です。
私は普段、金融の世界に縁のない仕事をしていますが、それでも本書に出てくる“証券会社時代の裏話”には強く惹きつけられました。特に、機関投資家営業という、一般にはあまり知られていない業務の中で、どのように四季報を使い、プロの投資家相手に日本株を売り込んでいたのか――その記述にはリアリティがあり、読んでいて背筋が伸びるような緊張感がありました。
証券会社で叱咤されたエピソードや、ファンドマネジャーとのやりとりなど、現場での経験が生々しく綴られていて、ただの“成功者の回顧録”では終わっていません。結果よりも過程に重きを置きながら、著者がどのように投資家としての土台を築いてきたのか、その背景が垣間見えるのがとても良かったです。
私にとって、投資というのは“数字”や“理論”の世界というイメージが強かったのですが、この本を読んでからは、むしろ“人”の世界なのだと感じるようになりました。真剣勝負の現場で磨かれた視点だからこそ、著者の言葉には説得力があるのだと思います。学び以上に“熱量”が伝わる、貴重な体験記でした。
7位 「会社四季報」最強のウラ読み術
株式投資を始めてみたいけれど、企業分析が難しくて自信がない――。
「会社四季報」は便利だと聞くけれど、分厚い情報の山に圧倒されて、どこから手を付けていいか分からない――。
そんな不安や疑問を抱える人にとって、本書『「会社四季報」最強のウラ読み術』は、まさに羅針盤となる一冊です。著者は、四季報を20年以上にわたり読み続け、通算84冊を隅々まで読み込んできた企業分析のエキスパート・渡部清二氏。彼が編み出した独自の「ウラ読み術」は、複雑な情報を「本当に見るべき5つのブロック(ABEJN)」に絞ることで、投資の判断力を劇的に高める実践的な手法です。
続きを読む + クリックして下さい
この読み方をマスターすれば、企業の健全性、成長性、そして継続性といった核心的な要素が、短時間で浮かび上がってくるようになります。株価チャートの細かい動きに一喜一憂する必要はありません。数字の裏にある“企業の物語”を読み解くことができるようになるのです。
さらに注目すべきは、本書が単なる「投資指南書」ではないという点です。たとえば、Aブロックの【特色】欄を読み解くことで、就活生は企業の強みや変化の兆しを知ることができますし、営業担当者であれば、取引先の事業モデルを深く理解する材料になります。つまりこの一冊は、投資家だけでなく、「企業を知りたい」と願うすべての人にとっての最強ツールなのです。
PER(株価収益率)ばかりに頼る従来の分析とは一線を画し、本書ではPEG(株価収益成長率)やPSR(株価売上高倍率)など、未来の成長を測る“本質的な指標”を重視します。こうした指標を用いることで、いわゆる「テンバガー銘柄」――10倍に化ける成長株――を見つける視点が手に入るでしょう。
また本書には、世界的な伝説の投資家ピーター・リンチの考え方をベースにした戦略も織り込まれており、長期的な投資スタンスや「仮説→検証→洞察」の思考フレームも身につけられる内容となっています。

ガイドさん
投資に必要なのは、“数字を読む”ことではなく、“企業を読む”こと――。
あなたもこの一冊で、企業分析の視野が広がり、未来を見通す力を手に入れてみませんか?
『「会社四季報」は分厚い情報誌ではなく、企業の未来を読み解く「知の地図帳」なのだということを、本書は教えてくれます。
本の感想・レビュー
私はこれまで「会社四季報」は、真面目に全部読まなければ投資に役立たないと勝手に思い込んでいました。でもこの本に出会って、それがまったくの思い違いだったと気づかされました。というのも、著者が「ABEJNの5ブロックだけを読めば十分だ」と教えてくれたからです。正直、最初は「そんな都合のいい話があるのか」と疑っていましたが、実際にその通りに読み進めてみたところ、驚くほど情報が整理され、企業の全体像がつかめるようになりました。
特にありがたかったのは、読むべきブロックに明確な目的が設定されていた点です。「ここでは企業の今が分かる」「ここでは将来性を読む」といったように、役割ごとにポイントが提示されているので、ページをめくるごとに“何を感じ取るべきか”が明確でした。これまで時間ばかりかけて四季報を読んでいたのが、嘘のようです。今では1冊を一通り把握するのにかかる時間が、格段に短縮されました。それでいて、理解はむしろ深くなっているのだから、この“ウラ読み術”には本当に感謝しています。
他5件の感想を読む + クリック
正直に言うと、私はこれまで投資にまったく縁がなく、「数字」と聞いただけでアレルギー反応が出そうなタイプでした。四季報の中身を少し見たこともあるのですが、専門用語や略語がぎっしり並んでいて、これは自分には一生関係ない世界だと思っていました。でも、この本はそんな私のような“数字ぎらい”の人間にこそ読んでほしいです。
まず、どこをどう見ればいいのかを丁寧に示してくれるので、ページを開くときの不安感がまったくありません。それに、自己資本比率やPBRといった難しそうな指標も、「なぜ大切なのか」「どう見れば安心なのか」をかみくだいて教えてくれます。決して数式を使った小難しい説明ではなく、視覚的にイメージしやすい比喩や構造的な見方を教えてくれるので、「数字を読む=感覚で判断できるようになる」感覚が芽生えてきました。
今では、会社を見る目がちょっと変わったように思います。決算書を恐れずに見られるようになったのは、この本のおかげです。
私は仕事柄、四季報には毎号目を通しているのですが、この本を読んで「まだまだ甘かったな」と思い知らされました。なぜなら、普段見過ごしていた“記者のコメント欄”の読み方に、これほどまでに深い意味があるとは気づいていなかったからです。
特に印象に残ったのは、著者がそのコメントのなかにある「言葉のトーン」に注目していた点です。ネガティブな単語が使われているか、それともポジティブな変化を匂わせるような語彙か。そこから、その企業がどんなフェーズにあるのかを読み解くという視点は、まさに“記者の目を通して見る”という感覚で、実務に活かせる内容でした。
コメント欄というのは、どうしても数字の裏付けがないせいか、軽く見てしまいがちですが、本書を読んでからはむしろ“最も人間らしい情報”として重視するようになりました。今では、数字とコメントの両輪で企業を見るクセがつき、分析の精度が格段に上がったと感じています。
PERではなくPEG・PSRを使う視点が勉強になる
「PERが低いから買い」——そんな感覚で投資していた時期が、私にもありました。でもこの本を読んで、その考え方がいかに表面的で危ういものかを痛感しました。著者が強調していたように、PERは過去の数字に基づいた評価にすぎません。本当に大事なのは、これからの伸びしろをどう測るか。そのために使うべき指標がPEGやPSRだという主張には、大いに納得しました。
特に印象に残ったのは、PSRを使って“企業の未来に市場がどれだけ期待しているか”を見るという点です。この視点を持つことで、これまで“割高だと思って敬遠していた企業”の中にも、実は大きな可能性を秘めた銘柄があることに気づきました。指標の本当の使い方を知ることで、見る世界がガラリと変わった感覚です。
本書は、数字の見方を“測る道具”から“未来を映すレンズ”に変えてくれました。投資を一歩深めたい人には、ぜひ読んでほしい内容です。
四季報の本で「人格」という言葉が出てくるとは、正直思っていませんでした。しかし読み進めていくうちに、企業を見るという行為が、単なる数字の集合体を見ることではなく、その背後にある価値観、哲学、文化を感じ取る行為であると気づかされました。第5章で述べられているように、企業の歴史や風土、さらには株主総会の空気感までを“読む”というのは、非常に新鮮で、しかも説得力がありました。
私自身、長年経営の現場にいたこともあり、企業には“顔”があると常々感じてきました。著者はそれを「企業の人格」と表現していますが、まさに腑に落ちる言葉でした。財務諸表では見えない、その企業がもつ空気感やこだわりは、案外四季報のなかの短いコメントや数字の変化に、うっすらと表れるものです。
この本を読んで以降、私は「この会社は、どんな人間だったら友達になれるだろうか?」という視点で企業を眺めるようになりました。投資において、それほど重要な変化だと感じています。
これまで私が四季報を使うときは、主に個別企業の数字を比較する目的で使っていました。しかし本書では、それだけではなく、「経済全体の流れをつかむためのツール」としての活用法が紹介されていて、目から鱗が落ちました。
特に印象深かったのは、著者が「業種別 業績展望」や「市場別決算業績集計表」に注目して、マクロな経済動向を読み解く姿勢です。個別企業が浮かび上がるだけでなく、それが属する産業全体の傾向まで見えてくる。それによって、今どの業界が波に乗り、どの業界が沈みがちなのかが、非常に直感的に把握できるようになります。
また、未来を仮説として捉えるというアプローチも面白いと感じました。四季報という“今”の情報のなかに、未来のヒントを見いだしていく視点は、診断士としての分析力をさらに深めるうえで、大きな学びとなりました。四季報は単なる企業辞典ではなく、現代経済を立体的に把握する地図であると再認識させられました。
8位 会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業
株式投資で成果を出すには、情報の“質”と“見る目”が何より重要です。しかし、世の中にあふれる情報のなかで、本当に価値ある企業、つまり将来性のある「超優良企業」を自力で見抜くのは決して簡単ではありません。そんな悩みを抱える個人投資家や投資初心者にとって、まさに道標となるのが本書『会社四季報の達人が教える 誰も知らない超優良企業』です。
著者は、会社四季報を20年以上にわたり“完全読破”し続け、累計80冊以上を精読してきた四季報のプロフェッショナル・渡部清二氏。証券会社出身であり、現在は個人投資家向けの教育機関「複眼経済塾」を運営しながら、多くの塾生に向けて企業分析と銘柄選定のノウハウを伝授しています。本書は、そんな著者の知見と実績を詰め込んだ“実戦型の企業分析指南書”です。
続きを読む + クリックして下さい
特徴的なのは、四季報という専門的な情報誌を、初心者でも使いこなせるよう“6つの情報ブロック”に分解し、誰でも再現可能な読み方を提示している点です。「会社四季報は難しそう」「どこから読めばいいのかわからない」といった不安を解消し、明確な視点を持って企業分析に取り組めるよう導いてくれます。
さらに本書では、企業を次の5タイプに分類し、それぞれに合った見つけ方を詳細に解説しています。
- 成長性が高く株価10倍も狙える〈中小型成長株〉
- 業績が反転して株価急伸が期待できる〈業績回復株〉
- 独自の強みで安定的に稼ぐ〈優良株〉
- 株価が割安に放置されている〈バリュー株〉
- 長寿と堅実性を兼ね備えた〈老舗株〉
いずれの章も、具体的な銘柄例、数字の見方、着目すべき四季報の欄などが具体的に記されており、「単なる理論書」ではなく、すぐに実践に移せる“投資の教科書”として仕上がっています。
また、テンバガー(株価10倍株)を夢見る成長株志向の投資家だけでなく、これから株式投資を始めたい初心者、就職・転職活動中の学生・社会人、さらには企業分析力を高めたいビジネスパーソンにとっても、本書は価値ある羅針盤となるはずです。

ガイドさん
単に「儲かる株を教える」本ではありません。本書が目指すのは、情報に振り回されず、自分自身の目で“未来の主役”となる企業を見抜ける力を育てること。読み終えたとき、あなたは「会社四季報」が単なるデータ集ではなく、“宝の地図”であることを確信するでしょう。
四季報を武器に、まだ誰も気づいていない原石を発掘したいあなたへ。この一冊が、真の優良企業との出会いを導いてくれます。
本の感想・レビュー
これまで株に触れたことがなかった自分にとって、『会社四季報』はまさに「プロ向けの難解な資料」という印象でした。ところが、この本を読み始めてすぐに、その印象が大きく変わったんです。ページをめくるたびに感じたのは、まるで隣で語りかけてくれるような丁寧な説明。読み方の手順がしっかりしているから、どこからどう読み始めればよいか迷うことがありませんでした。
特に、「四季報の6つのブロックに注目する」というアプローチが非常に明快で、数字の意味が少しずつ理解できるようになっていきました。難しい指標も、実際の企業を引き合いに出しながら説明されていたので、初心者の私でもすっと頭に入ってきます。「これは何を意味しているのか」という疑問が、本の中で自然に解消されていく感覚は、読書そのものが楽しい体験でした。
理解の積み重ねによって、読後には「私にも分析できるかもしれない」と感じられたのが嬉しかったです。まったくの初心者でも、確実に読み終えられる構成になっていることに感動しました。
他7件の感想を読む + クリック
これまでなんとなく四季報を開いたことはありましたが、正直なところ「どこを見たら何が分かるのか」が分からず、途中で挫折していました。でもこの本では、四季報を読むうえで必要な情報の「見極めポイント」が、具体的に示されています。特定の項目にフォーカスしながら、どのような変化や兆しを読み取るべきかが書かれていて、「なるほど」と思う連続でした。
印象的だったのは、四季報を“全部読まなくていい”という提案です。実際に注目すべきポイントが6つに整理されていて、それぞれに意味があることが丁寧に解説されていました。情報が膨大だからこそ、取捨選択の視点が大切なんだと気づかされます。
読後は、これまで何となくしか使えなかった四季報が、いわば「投資の道具」へと変わりました。ただ読むだけでなく、読むことで戦略が立てられるようになった実感があります。
最初は単に「儲かりそうな株を知りたい」と思って読み始めたのですが、途中から考えが変わりました。この本は、単に儲け話を紹介しているのではなく、“どうやって会社の価値を見抜くか”という思考法を育ててくれます。四季報の読み方から始まり、企業の収益性や財務の健全性などを見る目が、自然と身につくように構成されているのが印象的でした。
特に、各章の「実践編」では、実際にどの情報をもとに企業の成長性や割安性を判断するかが示されていて、非常に実用的でした。ここで得た知識は、四季報だけでなくニュースやIR情報を見る際にも応用できそうです。
「株を買う・売る」という行為の前に必要な視点を、しっかりと教えてくれる本です。読み終えたときには、明らかに投資に対する自分の態度が変わっていました。
テンバガーという言葉を知ってはいたものの、それが自分にとって現実になるとは思っていませんでした。でも、この本を読んでからは、そうした考えが変わっていったんです。具体的な条件に基づいて、どのような企業が将来的に株価10倍の可能性を持つのかが示されていて、説得力がありました。
注目したのは、中小型でオーナー企業、かつ高い成長率を持つ企業に焦点を当てていた点です。こうした企業にどういう兆候が現れるのか、その兆候をどう四季報で読み解くのかが明快に解説されていて、「これなら自分にも見つけられるかもしれない」と思えました。
この本は、夢物語ではなく、具体的な行動につなげられるテンバガーの手法を提示してくれます。投資の可能性に胸が高鳴るような体験でした。
読み終えた瞬間、まるで背中を押されるように書店へ足を運び、最新の会社四季報を手に取っていました。今まで何度か四季報を見かけたことはあったのですが、正直「自分には難しそう」と敬遠していたのです。でも、本書を通じて“どこを、どんな視点で見ればいいか”が明確になり、「自分にもできそうだ」と感じた瞬間、自然と行動に移っていました。
特に印象に残ったのは、四季報を読む際にチェックするべきポイントを6つに絞り込んで紹介している点です。この6つの視点を知ったことで、「全部読まなきゃ」と思っていた重圧がすっと消えて、具体的に“どこを見るか”がわかるようになったのは非常にありがたかったです。
書籍を読み終えただけで満足せず、実際に四季報を購入して実践したくなる。そんな知的好奇心を刺激してくれる力が、この本にはありました。
初めての株式投資に踏み出そうと決めたとき、偶然手にしたのがこの本でした。今思えば、最初にこれを読んでおいて本当に正解だったと思います。どの銘柄を買うべきかと焦る前に、“企業を見る目”を養うことの大切さを教えてくれたからです。
特に心に残ったのは、「良い企業と儲かる株は違う」という考え方です。人気企業や大企業に飛びつきたくなる気持ちをぐっと抑え、本当に将来性のある企業とは何かを問い直すきっかけになりました。本書の中では、有望な企業を見極めるためのフレームワークが明快に示されており、四季報の中でどう見分けるのかも段階的に説明されています。
投資を始める前に読むべき知識とは、単なるテクニックではなく、土台となる“観察力”であると実感させてくれる内容でした。
以前の自分にとって、会社四季報は「プロだけが使う専門資料」でした。でもこの本を読んで、四季報の見方そのものが大きく変わりました。四季報は情報が詰まりすぎていて、どこをどう読めば良いのか、何を見落としてはいけないのか、まったく分からなかったのです。
ところが本書では、四季報の構成や意味、読み方が図解的に整理されていて、視点を持ってページを開くことの大切さを知りました。「6つのブロック」に集中して読めば良いという説明は、本当に画期的だと思います。今では四季報を見るたびに、「ここは成長のヒントになる」「ここは安定性を見るところ」と目的意識を持って読めるようになりました。
つまり、今まで見えていなかった“地図の読み方”をこの本が教えてくれた感覚です。同じ情報でも、見方一つでここまで変わるものかと驚きました。
この本を読んで得た最大の収穫は、「企業の中身を見る視点」が持てるようになったことです。株式投資のために読んだはずが、気がつけば経済ニュースや企業のプレスリリースにも目がいくようになっていました。
「この会社の強みは何か」「成長性はどうか」「利益構造は安定しているのか」といった問いを持つようになったのは、この本で“見るべき項目”を教えてもらえたからだと思います。しかもそれは、単に表面的な数字ではなく、企業の根っこにある事業モデルや財務の健全性にまで目を向けさせてくれました。
株を買うための情報収集にとどまらず、「企業を見る」という思考法そのものが鍛えられた実感があります。結果的に、就職や転職の企業選びにも応用できそうな視野が広がりました。
9位 株「会社四季報」の鬼100則
株式投資を始めたばかりの初心者から、経験豊富なベテラン投資家まで、誰もが一度は手に取る「会社四季報」。しかし、分厚いページに詰め込まれた膨大な情報を前に、「どこをどう見ればいいのか分からない」「数字を追っても儲かる株が見つからない」と悩む人は少なくありません。
『株「会社四季報」の鬼100則』は、そんな投資家たちの迷いを解消するために書かれた、まさに“実戦型四季報攻略マニュアル”です。本書では、数多くの銘柄を分析し、四季報を武器に成果を出し続けてきた著者が、自らの経験に基づいて編み出した「100の着眼点」を公開。単なる解説本にとどまらず、実際に利益につながる読み方を、初心者にも理解できるよう具体例を交えながら解説しています。
続きを読む + クリックして下さい
本書の魅力は、従来の株本ではあまり語られてこなかった“プロが注目する微細なサイン”を徹底的に掘り下げている点です。たとえば、業績予想の数字がどのように変化したか、コメント欄の短い一文が意味する会社の本音、株主構成の変化から読み取れる企業のやる気や資金調達力、さらには欄外に載る速報情報が今後の株価にどう影響するかなど、四季報の隅々に潜む重要なヒントを見逃さないための視点を余すことなく解説しています。
また、数字や専門用語に不慣れな読者のために、チャートや具体例、比喩を交えながら「なぜこのポイントが重要なのか」を丁寧に解説。単に情報を詰め込むだけではなく、「投資判断にどう活かせるのか」までを明確に示してくれるため、読んだその日から実践できる内容になっています。
これまで四季報を開いても、「どこから見ていいのか分からない」と感じていた方でも、この一冊を通じて“プロが見る四季報の世界”を体感できるはずです。100の実践ルールを身につければ、膨大なデータが“単なる数字の羅列”から、“未来の株価を読むための強力な武器”へと変わります。

ガイドさん
株式投資で勝ち続けたい、他の投資家より一歩先に動きたい──そんな思いを持つ全ての人に、強くおすすめできる決定版です。
本の感想・レビュー
この本を読み終えたとき、まず最初に感じたのは「すぐに使える知識が詰まっている」ということでした。四季報をどう読み解くのか、ただの情報収集で終わらせず、実際の投資判断にどうつなげればよいのかを明確に示してくれる一冊です。
特に印象に残ったのは、限られた時間で効率よく情報を拾うためのコツや、企業情報の中から何を優先的に見れば良いのかが具体的に書かれていた点です。自分はこれまで四季報を開いても情報が多すぎてどこから見ればよいのか迷っていましたが、この本のおかげで迷いが減り、必要な情報をすばやくつかめるようになりそうだと感じました。
本を読みながら、次に四季報を開いたときにはこの方法を試してみようというアイデアがどんどん湧いてきて、机の横に四季報を置いて試したくなるような気持ちになりました。知識だけで終わらず、行動につなげられる実用書として非常に価値があると思います。
他5件の感想を読む + クリック
投資や株に関する本はどうしても専門用語が多く、情報が詰め込まれていて途中で読み疲れてしまうことがよくあります。しかし、この本は最後まで無理なく読み進めることができました。
各章の冒頭で「これから何を学べるのか」が明確に示されているので、今から読む部分で得られる知識をイメージしながらページをめくれます。さらに、重要なキーワードや実践ポイントが見やすくまとめられているため、読後に再確認したいときもすぐに目当ての箇所に戻れる構成になっています。
説明の流れも自然で、ひとつの章を読み終えるごとに「なるほど、こうすればいいのか」と理解が積み重なっていく感覚がありました。投資の初心者でも途中で混乱せず、安心して読み進められる、読みやすさに配慮された一冊です。
読み進めるうちに、単なる「四季報の読み方」を超えた内容が詰まっていることに気づきました。銘柄の見方や企業分析のポイントだけでなく、リスク管理の重要性や長期的な投資戦略の立て方まで幅広くカバーされており、まるで投資の基礎から応用までを一冊で学べるような充実感があります。
特定のテーマだけに偏らず、投資全体を俯瞰できる構成になっているので、初めて読む人でも全体像をつかみやすいですし、すでに投資を始めている人にとっても知識の整理や新たな発見につながる内容でした。
章ごとに独立したトピックとしても読めますが、最初から最後まで通して読むことで自然に知識がつながっていく作りになっており、読後には「投資をより広い視点で見られるようになった」と感じられる一冊です。
この本を読んでいて一番ありがたかったのは、四季報に出てくるさまざまな指標が一つひとつ明確に解説されていたことです。数字や略語が並ぶページを開くたびに「これは何を意味しているんだろう」と立ち止まってしまうことが多かったのですが、この本ではその疑問が次々と解消されました。
特に、指標の読み方を単なる定義だけでなく、「どう投資判断に活かすか」という視点で説明してくれているので、読むほどに数字の意味が生き生きと見えてきます。以前はただの記号にしか思えなかったデータが、企業の将来性や安定性を判断するヒントに変わる感覚が得られました。
ページをめくるごとに、難解に思えていた四季報の世界が手に取るように理解できるようになり、読み終える頃には投資を考えるうえで数字を頼もしい味方にできそうだと自信が持てました。
今までは四季報を開いても情報が多すぎて圧倒され、結局途中で閉じてしまうことが多かった私ですが、この本を読んでからは四季報を手に取ることが楽しくなりました。
著者が紹介する読み方のステップを踏むことで、ページの中から自分が知りたい情報をスムーズに拾えるようになり、気づけば夢中で銘柄を見比べている自分がいました。情報の洪水に溺れる感覚がなくなり、「今日はどんな発見があるだろう」と前向きな気持ちでページをめくれるようになったのです。
読むほどに「四季報は投資家にとって宝の山なんだ」と実感でき、知識がつくだけでなく“読む体験そのもの”が楽しくなる本だと思います。
投資というとどうしても利益に目が行きがちですが、この本はリスクの捉え方にもきちんとページを割いていて、そのバランス感覚がとても印象に残りました。
著者は投資をするうえで「何を避けるべきか」「どんな兆候に注意すべきか」を丁寧に説明しています。四季報の情報から危険信号を見抜く方法が書かれており、これを知っておくだけで無駄なリスクを減らせると強く感じました。
読み進めるうちに、投資はただ利益を追うものではなく、資産を守りながら増やす行為なのだと再認識させられました。この視点を持てるようになったことが、この本から得られた大きな収穫のひとつです。
10位 株で勝つ! 会社四季報超活用法
株式投資を始めたばかりの人にとって、最も大きな壁となるのは「膨大な情報をどう読み解くか」という問題です。証券会社やニュースサイトから毎日のように流れてくる企業データや株価情報、四季報の分厚い紙面――こうした情報を目にしても、「どこを見ればいいのか」「どの情報が重要なのか」がわからず、最終的に勘や雰囲気で銘柄を選んでしまうというケースは少なくありません。そんな情報迷子の投資家を、正しい判断へと導いてくれるのが『株で勝つ! 会社四季報超活用法』です。
本書は、日本を代表する企業情報誌『会社四季報』を生み出し続けてきた編集部が、自らの取材力と分析ノウハウを惜しみなく公開した、まさに「四季報の使い方バイブル」ともいえる一冊です。四季報は、国内上場企業3,500社以上を網羅し、120名を超える記者が独自取材で作成した業績予想を掲載した唯一無二の企業情報誌ですが、情報量が膨大すぎるがゆえに初心者にはハードルが高いと感じられることが多いのも事実です。本書はそのハードルを取り除き、四季報を“株で勝つための武器”として活用できるよう、基礎から応用まで体系的に解説しています。
続きを読む + クリックして下さい
内容は、四季報の誌面をどう読み解けば有望企業を見つけられるのかを、実際の投資判断に直結するステップごとに紹介する構成になっています。最初に見るべき情報、会社の健全性を見抜く財務データのチェック方法、利益を生み出している企業を探す視点、将来性ある銘柄を先回りして見つけるポイント、株価の動きを左右する要因、売買チャンスを逃さないタイミングの見極め方、さらには四季報の中からお宝株を発掘する裏技まで、プロの投資家が使うような実践的ノウハウが詰め込まれています。
さらに特徴的なのは、専門用語や指標をわかりやすく解説し、初心者でもすぐに理解できる工夫が随所に施されていることです。例えば、財務諸表の自己資本比率やキャッシュフローの赤字など、難解に感じがちな内容も、日常生活の家計管理に置き換えて例えることでスムーズに理解できるようにしています。これにより、数字や会計に苦手意識を持っている読者でも、少しずつ企業の「健康状態」を見抜く力を養えるのです。
また、この本で身につくスキルは投資だけにとどまりません。四季報を使いこなすことで、企業の強みや事業構成を把握できるため、営業先の開拓や就職活動、業界研究にも大きな力を発揮します。企業の競合関係、取引先、平均年収や従業員数など、ビジネスの現場で役立つ情報を効率よく入手できるようになるため、投資以外の分野でも価値ある知識として活かせます。

ガイドさん
『株で勝つ! 会社四季報超活用法』は、単なる投資入門書ではなく、実践で使える“情報の読み解き方”を身につけるための一冊です。
四季報を開いても何を見ればいいのかわからない、株式投資に不安がある、数字に弱くて苦手意識がある――そんな方でも、この本を読めば、企業分析の基礎から実践までを一気に習得でき、自信を持って投資判断ができるようになります。
情報が氾濫する時代だからこそ、正しいデータを正しく読むスキルが、投資で勝率を上げる最強の武器になるのです。
本の感想・レビュー
私はこれまで株式投資を始めたいと思いつつも、決算書や財務データにどうしても苦手意識があり、手を出せずにいました。四季報を手に取っても、数字がずらりと並んだページを前にすると、何をどう見ていいのか全くわからず、途中で投げ出してしまうことがほとんどでした。
この本を読んで最初に驚いたのは、そんな私のような「数字オンチ」に向けて、財務諸表の基本を本当にわかりやすく解説してくれていることです。たとえば貸借対照表の見方一つをとっても、専門書なら小難しい用語で説明されがちな部分を、会社のお金の「貯金箱」と「借金箱」に例えて説明しており、これなら私でもイメージできると感じました。
さらに、自己資本比率や営業キャッシュフローなど、投資判断で重要になる指標がなぜ大事なのかを、ただ数値だけでなくその背景や意味を含めて解説してくれています。数字が苦手な私でも、会社が安定しているか、将来にわたって利益を上げ続けられそうかを判断できるようになったのは、この本のおかげです。今まで株式投資に対して「知識がないから無理」と思っていた気持ちが、初めて前向きに変わりました。
他5件の感想を読む + クリック
以前から「四季報を読めるようになれば株式投資が上達する」と聞いていましたが、実際に四季報を開いてみると、情報が詰め込まれすぎていて、どこをどう見たらいいのか全くわかりませんでした。最初の数ページで疲れてしまい、結局本棚の奥にしまい込むことを繰り返していたのです。
この本を読んで、初めて四季報を使いこなすための道筋が見えました。特に第1章で紹介されている「まず最初に見るべき箇所」は、初心者が迷わずに情報を拾うための地図のような存在です。業績欄の見方、重要な指標の意味、注目すべき見出しのポイントなどを知ることで、ただ数字を追うだけだった四季報が、企業のストーリーを読み解くための道具に変わりました。
この本を読んでから再び四季報を開いた時、以前とはまるで別物のように情報が頭に入ってくる感覚がありました。「最初に読むならこの一冊」と自信を持って勧められる内容だと感じています。
私は株式投資を自己流で続けてきましたが、これまでの判断基準はほとんどニュースや株価チャートの動きに頼っていて、企業分析を深く行うことは少なかったと思います。そんな中でこの本を手にしたのですが、驚いたのは四季報編集部ならではの視点が惜しみなく詰め込まれていることです。
業績予想がどのように作られているのか、取材を通じて記者がどんな情報を裏付けとして持っているのかなど、普段知ることのできないプロの現場の思考法が書かれています。ただ数字を読むだけではわからない背景や、企業ごとのクセをどう把握するかなど、まるで投資のプロと一緒に取材の現場を回っているような感覚でした。
私はこれまで決算発表や株価の短期的な動きに一喜一憂していたのですが、この本を読んでからはもっと広い視野で企業を見ることができるようになりました。中長期で成長できるかを見極める視点、そしてリスクをできるだけ減らすための見方を学べたのは、大きな収穫でした。
四季報を読むたびに「この会社は良さそうだ」と思って投資しても、なかなか思ったように株価が動かず、逆に下がってしまうことも少なくありませんでした。数字を見て判断しているつもりでも、表面的な情報しか拾えていなかったのだと思います。
この本を読んで印象的だったのは、会社の業績予測には「クセ」があるという指摘です。会社によって慎重すぎる予想を出すところ、強気に出すところなど特徴があり、それを理解せずに鵜呑みにすると判断を誤る可能性が高いということでした。四季報の独自予想や強気マークがどうつけられているのか、その裏側の考え方を知ることで、数字を見る目が変わりました。
今では四季報を読むときに「この予想は保守的すぎないか」「独自予想が強気なのは何か理由があるのか」と考える癖がつき、企業をより深く理解できるようになりました。この力がついたことで、投資判断の精度が上がり、株式投資がより面白く、戦略的になったと感じています。
投資目的で読み始めたのですが、読んでいくうちに「これは就職活動や営業にも使える知識だ」と感じるようになりました。四季報には企業の従業員数や平均年収、取引先、関連会社といったデータが掲載されており、この本はその見方を丁寧に解説しています。
特に第2章の内容は、企業研究をする際にどこをどう見ればその会社の実態がわかるのかが具体的に書かれていて、採用活動や営業先の分析にとても役立ちます。これまで断片的な情報しか持てなかった企業に対して、四季報を通して俯瞰的に把握できるようになったことで、投資以外の場面でも情報収集力が高まったと実感しました。
株式投資を始めたい人だけでなく、企業を深く知りたいと考えている人にとっても、一冊手元に置いておいて損はない本だと思います。
株式投資を始めてからずっと「自分の判断に自信が持てない」という悩みがありました。ニュースや噂に流されやすく、根拠を持って投資判断を下せないことが多かったのです。この本を読んでからは、その不安がかなり軽くなりました。
四季報を使って情報を整理し、好業績で割安な銘柄を見つける方法、業績の上方修正が期待できる会社をどう探すかなど、再現性のある手法が明確に書かれているので、「これなら自分でもできる」と思えるようになったのです。
実際に学んだことを取り入れて投資判断をするようになってから、これまで曖昧だった銘柄選びに基準ができ、無駄な売買を減らせるようになりました。株式投資を怖がらず、前向きに続けられるようになったのは、この本のおかげだと強く感じています。