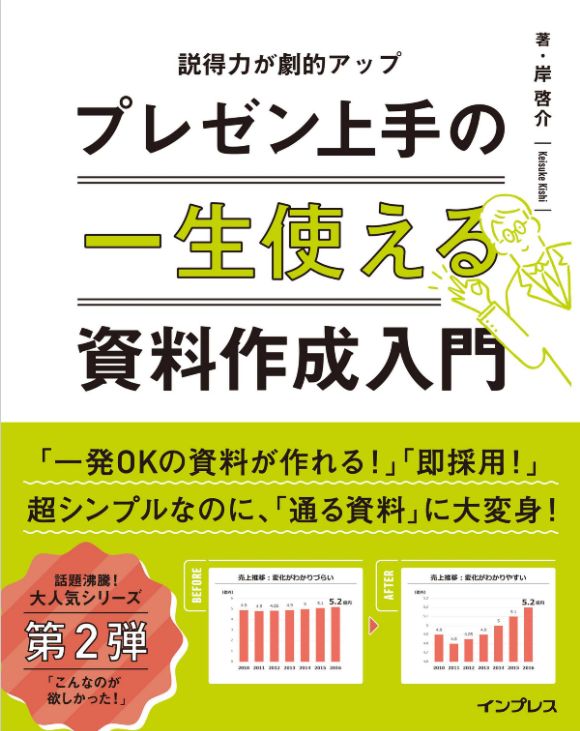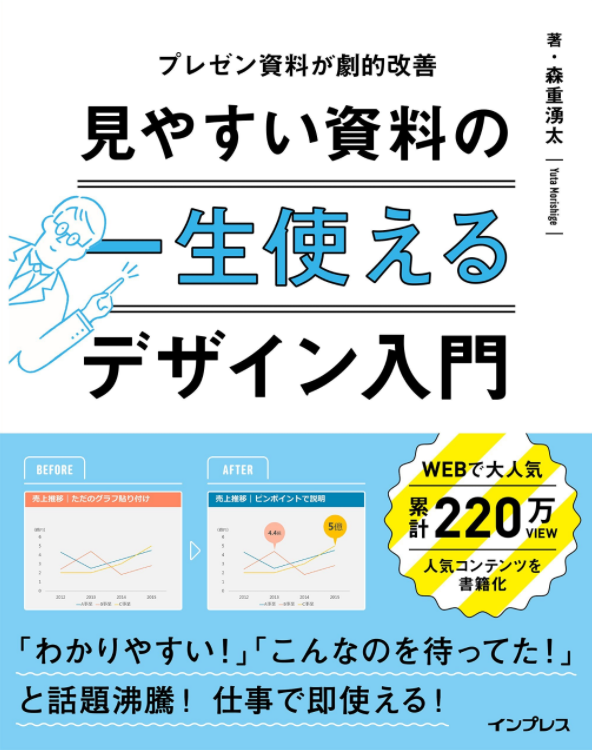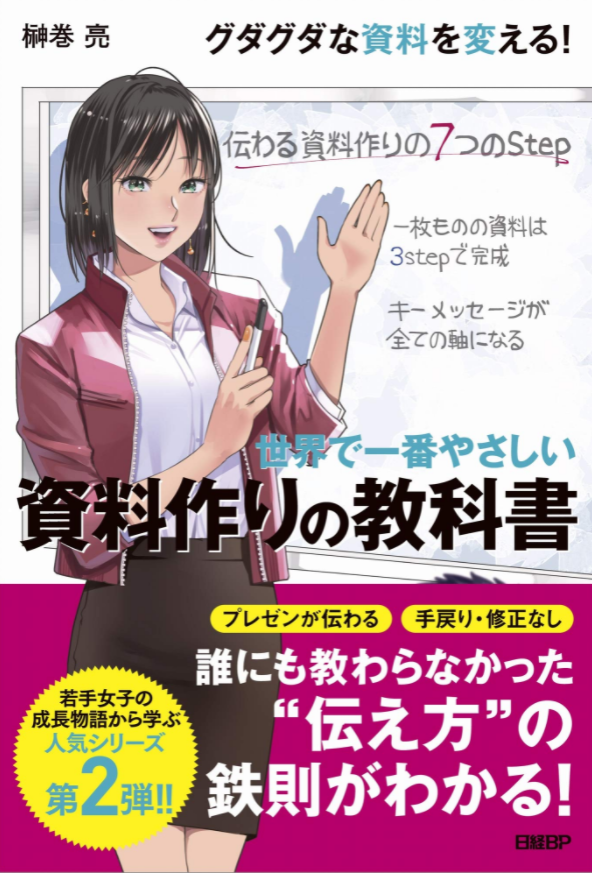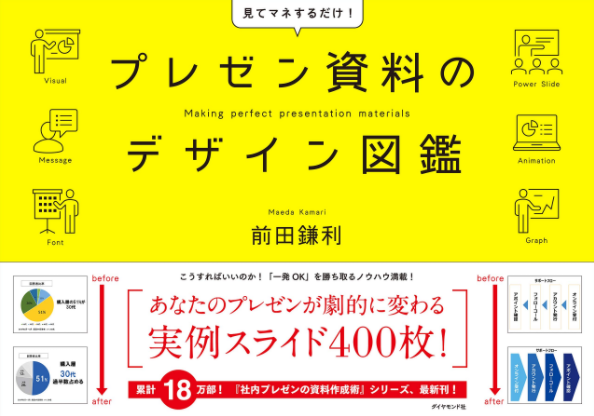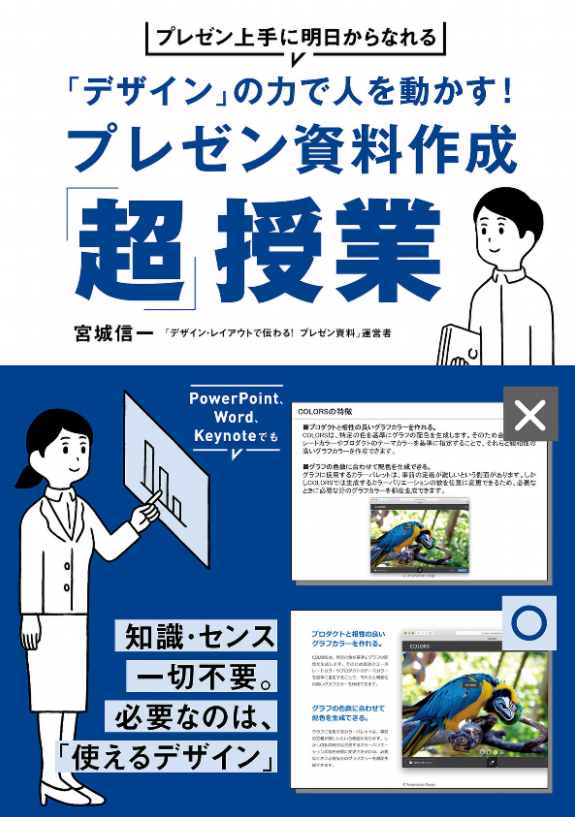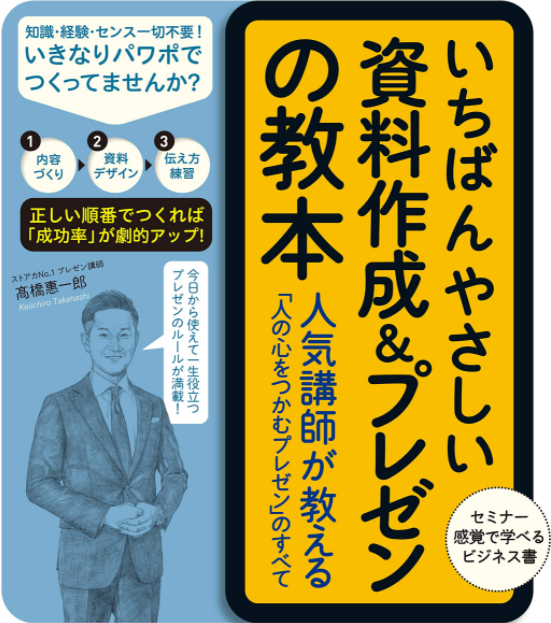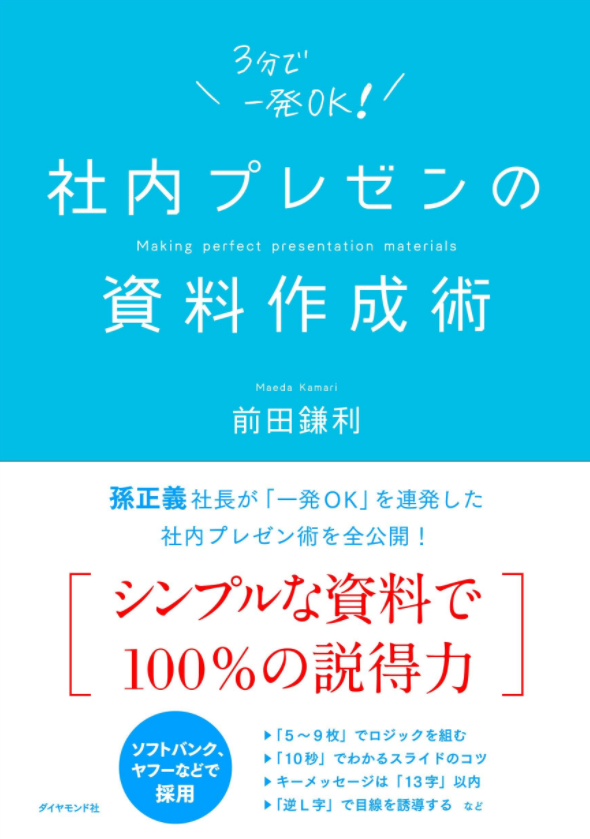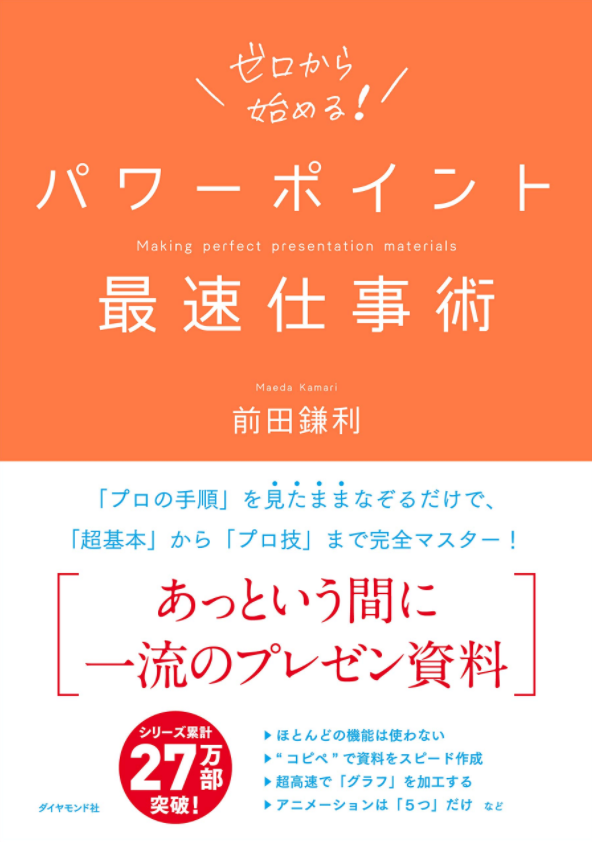もっとプレゼンテーションが上手になりたい、と思ったことはないですか?
実はそれ、プレゼン資料を上手に作ることで解決できるかもしれません。
「百聞は一見に如かず」と言われるように、聴覚で伝わる情報よりも、視覚で伝わる情報のほうが圧倒的に多いのです。
この記事では、プレゼン資料の作成が上手になるおすすめの本を紹介していきます。
資料作成のコツをつかみ、プレゼンをそつなくこなして見せましょう!
合わせて読みたい記事
-

-
スピーチが上手くなるおすすめの本7選【2024年版】
プレゼンや交渉、披露宴などの場でスピーチをそつなくこなせるようになりたいとは思いませんか?パブリックスピーキングに対する不安や緊張感。また、話す技術に対して自信を持てず、スピーチに苦手意識を持っている ...
続きを見る
-

-
語彙力を鍛えることができるおすすめの本6選【2024年版】
この記事では、語彙力を鍛えることができるおすすめの本を紹介していきます。語彙力があれば、類義語や言い換えの言葉をたくさん知っているため、話の内容に合わせて細やかな表現ができるようになります。また、伝え ...
続きを見る
-

-
ビジネスマナーが身につくおすすめの本5選【2024年版】
この記事では、ビジネスマナーが身につくおすすめの本を紹介していきます。ビジネスマナーが必要な理由は、良い信頼関係を構築して組織のイメージを良くしたり、顧客満足度を上げたりするためなどです。 入社直後の ...
続きを見る
一生使えるプレゼン上手の資料作成入門
「やり直しを減らしたい」「図表を見やすくしたい」「ストーリーをわかりやすくしたい」。
そんな要望に応えるために、資料作成の「最低限」の知識をビジュアルで解説!
本書では、IT企業で、各種資料のデザインや投資家向け決算資料、顧客向け提案資料、社内向け業務資料などの資料作成のアドバイスを行っている著者が、実務で役立つ最低限のポイントに絞って解説。
ビフォー・アフターの大きな作例を見ながら、上司や顧客から「OK!」がもらえる説得力のある資料作りのコツを直感的に習得できます。
レビュー・口コミ
見開きごとにポイントが1つずつ解説されており、とても読みやすいです。
伝えたい事が簡潔かつ図解付で分かりやすく解説されていて、誰かに教える時にも活躍する本だと思いました。
すごく助かりました、良い書籍をありがとうございました。
仕事柄プレゼン資料を作成する機会が多く、既に知っていた事も多かったですが、初めて知った内容もあり、大変役に立ちました。
資料作成の初級者からベテランまで、幅広い層に役に立つ良書だと思います。
本書にも書いてある通り、見せるテクニックも必要ですが、最も重要なのは内容なので、パワポで資料を作る前に内容について構想を練る事が良い資料作りの条件です。
【残り5件の口コミを見る クリック】
INTRODUCTION 一発OKがもらえる資料とはどういうものか
1 資料の「説得力」が高まる構成の基本
2 言いたいことが伝わるスライドの基本
3 OKを引き出す!グラフとビジュアルの効果的な使い方
4 効率よく資料の見た目を整えるテクニック
5 資料作成のプラスワンテクニック
【資料作成の3つの手順】
①入れたい要素を最初に書き出す
資料に入れたい要素を洗い出し、1つ10文字程度で書き起こす。
②書き出した要素にキーメッセージをつけてストーリーラインを決める
書き出した要素をタイトルとして、それぞれにキーメッセージを付けながら順番を決める。
③情報や素材を集めてスライドを作成する
【意識するべき4つのポイント】
①資料を見せる相手の立場に立って、相手のメリットを資料に盛り込む
②タイトル・キーメッセージはそれだけでストーリーが分かるような内容に
③重要なキーワードは3回入れる
④1スライド1トピックス
パワーポイント・プレゼン資料作成の指南書を何冊か読みましたが、本書が一番参考になりました。
何よりもこの本自体が大変見やすいので、本書で述べていることを裏付けていると思います。
見やすさのポイントや作る際のテクニックがまとまっています。
資料作成の基本的なコツが網羅されています。
私見ですが、スライドや図解を使い過ぎると一番伝えたいことが頭に残らない印象があります。
メッセージを明確にして、無駄なものは削ぎ落したシンプルで見やすい資料の方が上司からの受けがいいように思います。
OK!がもらえる資料の10箇条
1.「だからどうしたい」が明確
2.相手のメリットが提示されている
3.結論に至るまでのストーリーが見える
4.目次スライドを活用している
5.メッセージの補強要素が盛り込まれている
6.各スライドの意図がはっきりしている
7.ゆとりあるレイアウトで見やすい
8.キーワードは3回、繰り返す
9.まとめスライドで印象が残る
10.頭から終わりまでブレていない
「結局何を伝えたいのか」を意識し、必要な材料とその見せ方に気を配るだけで、資料の仕上がりはぐっと見違えます。
¥1,760
(2023/03/04 23:20:33時点 Amazon調べ-詳細)
一生使える 見やすい資料のデザイン入門
文字や図表、色の使い方、レイアウトにほんの少し気を配るだけで、資料の見やすさは違ってきます。
本書では、Webのスライド共有サービス「SlideShare」の「見やすいプレゼン資料の作り方」をベースに、実務で役立つ最低限のデザインのポイントに絞って解説。
ビフォー・アフターの作例を見ながら、誰でも簡単に見やすい資料作りのコツが習得できます。
作例はビジネスでの使用頻度が高いパワーポイントのスライド資料を使用しています。
直感的にポイントを理解できる構成なので、デザインを学んだことのない人でも大丈夫です。
わかりやすさを左右する「書体」「行間」「色」などの基本から、「図形」や「グラフ」などのちょっとした見せ方のコツまで、簡潔にまとめています。
レビュー・口コミ
これまでプレゼン資料作成は、先輩方が作った資料を見よう見まねでやってきましたが、本書を読んで仕上がりが格段に上がりました。
上司からも評価され、もっと早く参考書を読めばよかったと…。
やりがちな失敗例と、改善例のレイアウトが左右で見比べられるようになっているので分かりやすいです。
この本を一冊手元に置いておくだけで、パワーポイントのスライドの見栄えが変わると思います。
見易いデザインとは何かが図を踏まえて分かりやすく記載されています。
PowerPoint用の本ですが、Wordなどにも生かせます。
officeの使い方はわかってるんだけど、もっと見やすい資料が作りたい!と思っている人にはピッタリの本だと思います。
【残り6件の口コミを見る クリック】
1 伝わる資料とはどういうものか
伝わる資料は文字を「読ませない」
「文字数」「図」「写真」がキーポイント
やってはいけない!確実にダメ出しされるNG資料
1スライド1メッセージ
2 資料が見やすくなるデザインの基本
伝わる資料の文字は「シンプル」が原則
スライドのフォントは視認性が高いメイリオが原則
欧文フォントを使うだけで美しく見える
フォントを使い分けて効果的な資料を作ろう
行間は適度に広げてゆとりをもたせる
改行は「言葉のかたまり」と「長さ」がポイント
余白を作って「すっきりスライド」を目指そう
色をきれいにまとめる3原則
3 スライド全体のデザインを決めよう
ベースデザインを作ればラクラク
スライドサイズは「4:3」を選ぶ
全体のデザイン作りには「スライドマスター」を使う
配色とフォントは事前に設定しておこう
4 資料の見栄えが良くなる!表現のテクニック
まずは作図の基本パターンを知る
フローチャートで流れをビジュアル化する
アクセスカラーで部分に焦点をあてる
円グラフはカラフルにしてはいけない
棒グラフの縦軸は不要!データラベルですっきり見せる
折れ線グラフは「ピンポイント吹き出し」を活用する
5 さまざまな資料に応用しよう シーン別実例集
プロジェクト提案のためのプレゼン用表紙スライド
提案するサービスの特長紹介
見やすいわかりやすい料金プラン表
売上推移グラフ
工期・スケジュール表
1.「1スライド=1メッセージ」になっている
2.フォントの特性を利用している
3.色を使うルールを決めている
4.色の特性を利用している
5.脱・箇条書き
6.装飾がシンプルで無駄な要素がない
7.情報が凝縮されている
8.情報のグループ化を行っている
9.テキストや図が整列されている
10.情報と情報の間には余白をとっている
ビフォーアフターを見開きで比較してくれているのでとても見やすいです。
重要事項がわかりやすく書かれており、プレゼンスキルを高めたい人に最適な本だと思います。
なかなか教えてもらえる分野ではないので、この手の本を読んだことが無い人は一読の価値ありだと思います。
書いてある通りに真似したら、見違えるほどプロっぽくなりました。
この本を読んでから、生活のなかで目にする資料の多くにセオリーに基づいたデザインが施されていることに気付きました。
今まで基本ができていなかったことを気付かせてくれた本です。
資料作りのコツが網羅されています。
知っていること、意識していることもたくさん書かれていますが、あまり意識できていなかったことも書かれてあり、購入してよかったです。
今日からでも改善できることばかりなので、資料の質が向上すること間違いなしです。
初めてパワポで資料を作ることになり本書を購入しましたが、とても参考になりました。
いかに見やすいスライドにするかのテクニック、ポイントが記載されています。
図解でわかりやすく説明されているので見やすい!
¥1,584
(2024/07/26 16:34:51時点 Amazon調べ-詳細)
世界で一番やさしい 資料作りの教科書
物語の主人公は、プレゼンがうまくいかずに悩む入社4年目女子の鈴川葵。
社内のグダグダ会議を改革した葵は、あるプロジェクトチームのメンバーに大抜てき。そこで今度は「資料作り」を学び、社内のコミュニケーションを変えていくことになります。
先輩、恋人からアドバイスや、コンサルタントの父が授けた「資料作りの7つのStep」「コミュニケーションの3つの作法」などを実践し、相手に自分の主張を伝える極意を身に付けていく葵。最後には大きなプレゼンテーションの舞台に立つことに--。
本書では、「無駄のない行動を起こさせる意思疎通」や「自分の思いをストレートに伝えるプレゼンテーション」を実現するための上手なコミュニケーションを、資料作りの実践手法を中心にして解説していきます。
レビュー・口コミ
資料作成の参考書とえば、「デザインの仕方」「図表の作り方」「色使いのテクニック」などの、見栄えを解説している物が多いです。
本書は「資料の見栄え」ではなく「メッセージをいかに伝えるか」に重点を置き、押さえるべきポイントを徹底的に解説している書籍です。
新人社会人を主人公とした小説ベースで資料作りについて解説されています。
著者もあとがきで書かれているように、資料作りというよりコミュニケーションの教科書といった印象です。
資料作りに関するのは、2章と5章だけ。3章は仕事の受け方や依頼の仕方について、4章は会話の仕方について、6章はプレゼンについて書かれています。
【残り4件の口コミを見る クリック】
第1章 伝わらないグタグダな資料
第2章 一枚ものの資料作り
第3章 仕事を受ける/依頼する
第4章 会話をかみ合わせる
第5章 プレゼン資料を作る
第6章 伝わるプレゼンテーション
タイトルに「資料作りの教科書」と書いてありますが、図表を上手に使うコツや色使いのテクニック、体裁のセオリーといった話は一切出てきません。
資料の見栄えは確かに重要ですが、資料の役割は本来「何かを伝えること」なので、仮に見た目が悪くても伝えたいことが伝わるなら、問題ありません。
もっと言えば、伝えたいことが伝わるなら、資料など作らなくてもいいのかもしれません。
では伝えたいことをスパッと伝えるには、何を抑えればよいのでしょうか?
本書はそこを丁寧にひも解いていくものです。
本書は、入社4年目の女性社員が資料作りやプレゼンに励み、成長していく様子が小説形式で描かれています。
タイトルには資料作りの教科書とありますが、伝え方・コミュニケーションの教科書と言った方が正しいのかもしれません。
資料作成、コミュニケーションに関する大切なことが書いてあります。
本書を読み、内容を落とし込んだテンプレートを作成しました。
以前は重要なことを詰め込みながら試料を作っていたのですが、今は順序立てて要点を組み立てられるようになりました。
読み始めた当初は(期待していた本ではないな…)と思っていたのですが、最後まで読んでよかったです。
¥1,584
(2024/07/26 16:34:51時点 Amazon調べ-詳細)
プレゼン資料のデザイン図鑑
“見てマネする”だけで、最強のプレゼン資料を作成できるようになります!
全128のビフォー・アフターと合計400を超える実例スライドを掲載。わかりやすく説得力のあるプレゼン資料をつくるポイントを解説します。
スライド設定、フォント、キーメッセージ、グラフ、図解、フローチャート、画像、アニメーション…。
これらをどう組み合わせれば“パワースライド”が生まれるのか?見て真似るだけで、あなたのスライドが劇的に変わる実例スライド300枚。はじめてのプレゼン資料デザイン図鑑!
レビュー・口コミ
ビフォーアフターが左右見開きに並べられていて、とても分かりやすいです。
グラフの罫線は消す、画像は最大限とする、青字と赤字を使い分ける等プレゼンテーション資料に使えるコツがたくさん書かれています。
社内プレゼンと社外プレゼンの違いについても説明されており、大変勉強になりました。
見開きの左側に実際のプレゼンテーション資料、右側に修正したプレゼンテーション資料を並べる構成となっています。
文字の大きさや写真の扱い、グラフの見せ方など細かい事柄について著者なりの理由が丁寧に書かれています。
伝える内容が一番大事であることは確かですが、スライドを変えることでプレゼンの質が向上しました。
【残り4件の口コミを見る クリック】
第1章 プレゼン資料の基本15
ビジネスプレゼンのロジック展開
社内プレゼンと社外プレゼンの違い
本編とアペンディックス
グラフは「左」、メッセージは「右」
「モノクロ」「カラー」を使い分ける など
第2章 スライド設定
スライド・サイズの選び方
「表紙」のつくり方
ページ番号の置き方
ブリッジ・スライドの見せ方 など
第3章 テキストの見せ方
フォントの選び方
フォント・サイズの選び方
キーメッセージの見せ方
テキストの見せ方 など
第4章 3秒でわかるグラフ
グラフ・スライドの基本
棒グラフの見せ方
円グラフの見せ方
ポジショニング・グラフの見せ方 など
第5章 ビジュアルでつかむ
表スライドの見せ方
フローチャートの見せ方
スケジュールの見せ方
画像スライドの見せ方 など
第6章 パワースライドのつくり方
「数字」でひきつける
「質問」でひきつける
「黒地+白字」でひきつける
「共感」で惹きつける
「データ」で説得する など
第7章 アニメーションの使い方
「フェード」の使い方
「マジック・ムーブ」の使い方
「ワイプ」の使い方 など
会社でプレゼン資料を作成する機会が多く、もっと良い資料が作れないものかと思い参考書を読み漁っていましたが、本書が一番参考になりました。
テキストの見せ方やグラフの見せ方など、見やすくする工夫はまだまだ出来そうです。
スライドは中身が重要なのはごもっともな意見ですが、見やすいスライドでないと共感を得られません。
ソフトバンクで孫社長向けにプレゼンテーションを作成した著者の、ノウハウ集です。
ITエンジニア本大賞2020のビジネス本部門大賞作品。
サンプルが豊富で、見ていて「コレ良いな」と思えるものばかりです。
参考になるスライドがたくさんありました。
同僚が作る資料と比べ見劣りしていると思い、本書を購入しました。
今まで自己流で資料をレイアウトしていましたが、本書を読み自分の未熟さを知りました。
プレゼンや営業資料を作るときには、この本があればもう大丈夫!
自己流で資料作成をしている人は要注意です。
¥1,871
(2024/07/26 16:34:52時点 Amazon調べ-詳細)
「デザイン」の力で人を動かす!プレゼン資料作成「超」授業 プレゼン上手に明日からなれる
「仕事で使うプレゼン資料にいまいち自信が持てない…」
「デザインの良い資料を作れたらいいけど、自分はセンスないんだよね…」
「フツーの資料を作る分には問題ないけど、聞き手の反応はあんまりよくない…」
この本はそんなノンデザイナーのビジネスパーソン向けに、プレゼン資料に特化したデザイン技法を紹介しています。
・「わかりにくい」と言われる
・聴衆が寝ている
・商品の良さがうまく伝わらない
・プレゼンに自信が持てない
・「センスないね」と同僚に言われた
・発表で伝えたはずの内容に質問が出てくる
こういった悩みは、実は「デザイン」で解決できます!なぜなら人間は、「話された内容」より「視覚」から情報を得て、理解するからです。
いくらあなたが論理武装したからといって、分かりやすく情報整理された「デザイン」の力に勝るものはありません!
レビュー・口コミ
本書は、「伝わるデザイン」と「伝わらないデザイン」の双方のサンプルを用意し、何がその肝なのかを、その根拠とともに明記する構成となっています。
デザインは「感性」というもので曖昧にされるケースもありますが、本書ではそういった表現は一切せず、具体的かつ論理的に伝えるためのデザインを明示してくれています。
見切れない位沢山の題材で例示されているので、本書を読み終わる頃にはかなりのレベルアップになっているはずです。
みやすい資料を作るにはどうしたらいいのか?をデザインの面から学んでもらおうとする本です。
この手の本にありがちな、「Before」「After」両方の例がでているので、とても分かりやすいです。
プレゼン資料を作る人にはもちろん、HPやブログなどをデザインする人にも参考になるポイントは多数あると思います。
【残り4件の口コミを見る クリック】
Chapter.1 伝わりやすさに差がつくレイアウトのルール
スライドの要素は「整列」を徹底し、情報を整理して伝える/「視線の流れ」に合わせて要素を配置し、メッセージを伝わりやすくする/「余裕」のあるスライドには「余白」がある/スライドは適宜「分割」し、要素が一番効果的に見えるよう配置する/性質の異なる要素を「対比」させ、コンテンツのインパクトを強める/「反復」でスライドの理解コストを圧縮する/COLUMN 反復を徹底すれば「ハズし」に価値が生まれる
Chapter.2 ロジックを直感で伝える図解のテクニック
込み入った情報を扱うときは「図解」を併用する/作業を「フロー」で可視化する/「表」を活用し、情報の整理と編集を効率化する/「トリミング」と「吹き出し」で図版を伝わりやすく解説する/「線表」でスケジュールを直感的に伝える/COLUMN 図解では要素の干渉に注意する
Chapter.3 データの説得力をアップするグラフ作りの基礎
グラフで数量を視覚化する - 棒グラフ/グラフは読み取りやすさを重視し、シンプルに描画する - 円グラフ/COLUMN 決して万能ではない円グラフ?/グラフ選びは、伝えたいメッセージとの相性を考慮する - 折れ線グラフ/外部ツールで作ったグラフを取り込む際は、デザインを整えて利用する/COLUMN グラフの色選びに困ったら…/COLUMN シンプルな図形で、グラフの要所を補足する
Chapter.4 メッセージを印象づけるカラーの法則
プレゼン資料では「テーマカラー」を決め、ルールに沿った色使いをする/鮮やかなコントラストの効いた色で、重要なポイントを「強調」する/「色が持つイメージ」を使って、スライドの情報を補足する/COLUMN モノクロ印刷時に意味が失われないようにする
Chapter.5 見やすく・読みやすい基本の文字組み
「フォント」と「行間」の調整でテキストを読みやすくする/スライドのとっつきやすさを「見出し」と「行長」で向上する/テキストの文字数や見せ方に応じた「文字揃え」を選択する/「箇条書き」は、原則プレゼンツールの機能を利用する/COLUMN
プレゼンは相手にこちらの意図をどれくらい伝えられたかがカギになります。
作業に熱中していると、ついつい受取手の見え方がおろそかになりがちだったことが本書で気づかされました。
今まで直感的に選んでいたレイアウトや図解の配置に「見やすいルール」があることを初めて知りました。
色使いにもセオリーがあり、反対色や補色の意味合いを理解していれば、重要なポイントで効果的な色使いがプレゼンシートに反映できます。
プレゼン資料作成の参考書を読んだことが無い人には驚きの連続だと思います。
見やすく伝わりやすい、プレゼン資料作成の実践的なテクニックを学べる本です。
ただ見栄えの良いデザインを説いているのではなく、顧客に伝わりやすいプレゼン資料のデザインのテンプレートを紹介しています。
本書では、「何故このようなデザインでなければならないのか」という根拠もあわせて説明されているので、あやふやな感覚ではなく、しっかりとした技術として身に付きます
紹介されているテンプレートは無料でダウンロード可能ですので、実際に資料に触れながらテクニックを覚えることができます。
BEFOREとAFTERの比較ができるので、何がダメなのかを一目で理解することができます。
プレゼン資料作りに慣れてきて、無駄に凝ったスライドを作るようになってましたが、資料は見やすさが重要だということを再認識させてくれました。
¥1,861
(2024/07/26 16:34:53時点 Amazon調べ-詳細)
いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本 人気講師が教える「人の心をつかむプレゼン」のすべて
日本最大級のまなびのマーケット「ストアカ」で人気講師として支持を集める著者が、これまで数々のセミナーで解説してきたノウハウや、受講者の求めるポイントを1冊に凝縮。
難しそうに思えるかもしれませんが、ITの知識やデザインのセンス、プレゼンの経験がなくても理解できるように配慮しているので、心配することはありません。
概念やパワポの操作方法を丁寧に解説するのみならず、「なぜそうするのか」といった疑問に答えられるような説明も随所に入れています。
レビュー・口コミ
プレゼンの資料デザインや伝え方、マインドが体系的にまとめられた良著です。
タイトルに「いちばんやさしい」と書いてあるので、日頃からプレゼン資料を作成している人にはレベルが低いのでは?と思いましたが、全くそんなことはなかったです。
資料作成の全てが網羅的にかつポイントを絞って記載されており、大変参考になりました。
本書を読み、伝えるだけのプレゼンではなく、相手にアクションを促すプレゼンの方法が分かりました。
良い資料には導入があり、簡潔に要点を明示し、その後に詳細を付け加え、最後に具体的なアクションプランを示すというもので、とてもシンプルです。
プレゼンの作り方だけでなく、デザインのルールも丁寧に、理論立てて説明してあります。
この一冊だけで、プレゼンのフォーマットからパワポ資料、そして魅せ方まで、良いプレゼンをするための全てを知ることができます。
【残り5件の口コミを見る クリック】
1 プレゼンの学習を始める前に
2 はじめに知っておきたい“プレゼンの本質”
3 STEP1 内容設計ー人を動かすプレゼンには“型”がある
4 STEP2 資料作成前編ー設計した内容を資料に落とし込む
5 STEP2 資料作成後編ーセンス不要!デザインルールで資料を磨く
6 STEP3 実践練習ー練習で確固たる“自信”をつける
7 プレゼンには“真剣”かつ“気楽”に臨もう
上司からプレゼン資料への指摘があり「このままではまずい…」と思い購入しました。
本書は、プレゼン資料を上手に作る為のルールを教えてくれています。
本の中には「センス不要のデザインルール」という項目がありますが、書かれている通りに作成すれば誰でも上級者の仕上がりにすることができます。
本書を学んでから過去に作った自分の資料を見返してみると、何を伝えたいのかよく分からないなぁ、と恥ずかしくなりました。
プレゼン試料を作る者なら手に取って損はない商品です。
友人にプレゼンの相談をしたところ、こちらの商品を進めてもらいました。
プレゼンにおける気を付けるポイントが分かりやすく書かれてあり、とても読みやすかったです。
色使いや余白等に気を使っているのがうかがえて、流石プレゼン資料作りの参考書といった感じです。
パワポで作成する具体的な手順については順を追って丁寧に書かれており、段取りよく資料作成ができるようになりました。
購入してよかったです。
プレゼンテーションはセンスではなくルールと言われたりしますが、その言葉を体現した参考書となっています。
本書に書かれていることを忠実にこなしていくだけで、すっきりとした、とても見やすい資料が作成できます。
プレゼンテーションをする際の心構えから始まって、詳細なパワポの技術、さらには練習方法まで網羅されています。
完璧な教本です。
プレゼンを上手く成功させるための要素について、例を用いながらどうすればよいかが簡潔に説明されています。
パワポについても基礎が網羅されているので、この本があれば資料作成でつまづくことは無くなるでしょう。
この本に書かれているポイントを押さえてプレゼン作成を行えば、記憶に残るプレゼンに仕上げることができると思います。
¥2,080
(2024/07/26 16:34:54時点 Amazon調べ-詳細)
社内プレゼンの資料作成術
上司や取引先を説得するプレゼン力はすべてのビジネスパーソンに求められます。
しかし、ほとんどの人々が苦手意識を持っているのではないでしょうか?
本書は、ソフトバンクで孫正義氏から何度も「一発OK」を勝ち取った、著者の社内プレゼン術をすべて公開しています。
「キーメッセージは13字以内」「資料は5~9枚」「ビジュアルは左、文字は右」など、誰も教えてくれなかったプレゼン資料作成の奥義!カラービジュアルで徹底解説!
レビュー・口コミ
本書は、筆者がソフトバンクで身に付けた社内向けプレゼンのノウハウを紹介しています。
・社内プレゼンの鉄則は、シンプルかつロジカル。
・3分で終えることを前提に、5~9枚のスライドで道筋を組み立てる。
・①課題→②原因→③解決策→④効果。この4つがこの順番で並んでいること。
・「結論」と「根拠」をワンセットで提示すること。
社内プレゼンの資料作成術と銘打っていますが、社外向けにも使える内容が多いです。
プレゼンの資料作りは独学ではなく、このような参考書を読みフォーマットとして取り入れるほうがいいと思います。
社内プレゼンを控え、本屋でたまたま見つけた本書を手に取りました。
実際に使えるテクニックがいっぱい詰まった良書です。
図解やイラストの少ない資料というのは、受け手の負担になりがちです。
受け手のことを考えるなら、本書のような参考書を頼りにすることも必要かなと思います。
【残り4件の口コミを見る クリック】
第1章 プレゼン資料は「シンプル&ロジカル」でなければならない
第2章 プレゼン資料を「読ませて」はならない
第3章 グラフは「一瞬」で理解できるように加工する
第4章 決裁者の理解を助ける「ビジュアル」だけ使用する
第5章 100%の「説得力」をもつ資料に磨き上げる
第6章 プレゼン本番は資料に沿って話すだけ
プレゼン資料と聞くとついつい写真を多用しがちですが、決裁者に余計なビジュアルは逆効果だそうです。
社内プレゼン資料においては、写真を使用することに意味があるのではなく、あくまでも「わかりやすいこと」に意味があるそうです。
常に決裁者の立場に立って、「理解の助けになるか?」と自問しながら写真の使用不使用を判断する必要があります。
社内プレゼンに求められる資料と社外プレゼンに求められる資料の違いがよく分かりました。
関心の無い社外のクライアントに向けてプレゼンする場合は、写真などを使って感情に訴えると効果的なようです。
逆に、初めから関心のある社内の人にプレゼンする場合は、プレゼンに引き込もうとする必要がそもそもないので、写真などは無駄な情報となるようです。
他にも勉強になる情報がてんこ盛りです。
本書を購入してよかったです。
プレゼンで気をつけるべきことが、コンパクトにまとめられています。
社内稟議がなかなか通らなかったのですが、本書に書かれていることに気をつけながら資料作りをしたら、一発OKがでました。
今まで余計なスライドやおそらく読まないであろう文章が入っていることに気が付きました。
以前より資料作りが楽しくなりました。
パワーポイント最速仕事術
優れた「スライドの型」を知り、必要な操作法をマスターすれば、資料作成スピードは劇的に速くなります。
「資料はコピペ」「超高速でグラフを加工」「アニメーションは5つだけ」など、最速最強のパワーポイント仕事術を伝授します。
はじめてパワーポイントに触れる超初心者でも、「超基本」から「プロ技」まで完全マスターできる待望の一冊です。
レビュー・口コミ
仕事でグラフを用いた資料を作らないといけないことになり、本屋に駆け込んだら参考になりそうな本書を見つけました。
タイトルに「ゼロから始める」と書いてあるように、まったくの初心者の私でもパワーポイントを理解することができ、それなりの試料を作ることができました。
本書の基本の部分しか参考にしませんでしたが、紹介されているテクニックを全てものにすれば、もっと作りこんだ資料が作れそうです。
説明が丁寧で、とてもわかりやすい本でした!
プレゼン資料作成の本を買ったのですが、そもそもパワーポイントをあまり使ったことがないことに気が付き、本書を購入しました。
パワーポイントに関して深い知識が無かったのですが、手取り足取りとても丁寧に解説されているので、パワーポイントを触ったことのない人でも理解できると思います。
パワーポイントの画面の写真を使って解説されているので、「タブ」や「リボン」など専門用語が分からない人でも問題ありません。
パワーポイントを仕事で使う人なら必ず読んでおくべき本だと思います。
【残り5件の口コミを見る クリック】
プロローグ プレゼン資料の大原則
社内プレゼンは「シンプル&ロジカル」がベスト
社外プレゼンは「感情」を動かす
第1章 パワーポイントの「超」基本
「箇条書きスライド」をつくる
「ブリッジ・スライド」をつくる
「白抜き文字スライド」をつくる
「ショートカットキー」は、これだけマスターする
第2章 「図形」をマスターする
「時系列フローチャート」をつくる
「階層フローチャート」をつくる
目線誘導の「▽」をつくる
「スケジュール・スライド」をつくる
最速で「プレゼン資料」をつくる3つのステップ
第3章 「グラフ・スライド」をマスターする
「棒グラフ・スライド」をつくる
「折れ線グラフ・スライド」をつくる
「円グラフ・スライド」をつくる
使いやすい「テンプレート」をつくる
第4章 「ビジュアル・スライド」をマスターする
「画像」をスライドに取り込む
画像を「トリミング」する
「モノクロ」「セピア色」の画像をつくる
「透過スライド」をつくる
「多画像スライド」をつくる
「ショートバージョン」をつくる
第5章 「アニメーション」「画面切り替え」をマスターする
「フェード」を活用する
「ワイプ」を活用する
ワイプで「めくりスライド」をつくる
テキストを「変形」で見せる
「比率変動スライド」をつくる
効果的な「画面切り替え」の方法
データ容量を削減して「保存」する
新人教育の担当になり、改めてパワーポイントを勉強し直そうと思い本書を購入しました。
基本的な部分は勿論理解していましたが、「時系列フローチャートの効率的な配置の仕方」や「オブジェクトの効率的な始め方」など、今まで知らなかったことがあり、大変学びになりました。
初心者からベテランまでお勧めできる参考書です。
わかりやすいプレゼン資料のポイントは2つ。
1.資料全体をどのような構成で組み立てるかということ。
明確なテーマ設定がされているとともに、シンプルなロジックで組み立てられたプレゼン資料でなければなりません。
2.1枚1枚のスライドをどのように作るかということ。
パット見た瞬間に、何を伝えたいのかが直感的につかめるスライドでなければなりません。
長々と文章を記したようなスライドや、複雑なグラフをそのまま張り付けたようなスライドではいけません。
相手に考えさせる手間をできるだけかけさせないような、シンプルなスライドが求められます。
本書は、「一瞬で理解できるスライド」を、パワーポイントで最速で作るノウハウを伝えるものです。
第1章以降で、分かりやすいスライドの例を示しながら、そのようなスライドを最速で作るノウハウを詳しく解説しています。
限られたパワポの機能をマスターするだけで、サクサクとスライドを作ることができるようになります。
PowerPointで資料を作る必要があり、参考のために購入。
まず初めに構成を組み立てることや字体の決定、スライドの枚数、心構えなどが書かれてあり、テクニックの部分以外でこんなに参考になる部分があるのかと驚いた。
テクニックの指南も素晴らしい。簡単により質の高いプレゼン資料をつくれる。
PowerPointで作業することのある人には必須の本かと思う。
ダイヤモンド社
¥1,980
(2024/07/26 16:34:55時点 Amazon調べ-詳細)